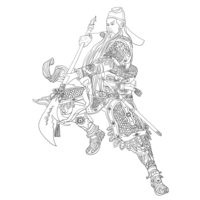①感情面の問題
■ ①感情面の問題
①感情面の問題
良くも悪くもこの点は大きいでしょう。例えば劉表が亡くなる際、諸葛亮は荊州を奪えと進言。仮にですがその言葉通り荊州を奪還していれば曹操と立ち向かうだけの戦力がもっと早い段階で整えられていたでしょう。
諸葛亮が度々助言するものの優しさからそれらを固辞。結果、諸葛亮は他の作戦を考慮して遠回りするケースも珍しくありませんでした。これではいくら諸葛亮といえどもやはり天下統一は難しかったでしょう。
もしも、劉備(玄徳)が諸葛亮の言葉に従っていれば歴史は変わっていたかもしれません。その一方では反対された夷陵の戦いは決行。
こちらは領土拡大云々ではなく、単純に関羽の仇討ちなだけ。諸葛亮としてもその点を分かっているからこそ止めたものの、結局は強行。
もしも、呉を倒して領地を手に入れていれば話は変わっていましたが、結果だけを見れば戦力を消耗しただけのまさに「無駄な戦い」にしかならなかったのです。いくら素晴らしい配下が居ても、決断するのは君主。ここぞという時にどうしても良くも悪くも感情的に動いてしまっていた以上、天下統一が難しくなったのかもしれません。
②曹操が凄すぎた
■ ②曹操が凄すぎた
②曹操が凄すぎた
これもあるでしょう。劉備(玄徳)自身の問題ではなく、曹操が素晴らしい能力を持った人間だったからこそ、上手く立ち回れなかったのです。
劉備(玄徳)は黄巾の乱以降、蜀を手に入れるまでは流浪の身でしたが、そもそもその原因の大半は曹操にあります。仮に曹操が大したことのない男であれば劉備(玄徳)がここまで追い回されることもなかったでしょう。
しかし曹操が破竹の勢いで領土を拡大していくと、結局は山間部である蜀しか劉備(玄徳)が付け入る隙がなくなっていました。
曹操がもっと中原の制覇に時間がかかっていれば劉備(玄徳)としても違う所で一旗揚げられたかもしれません。しかし天下三分の計という言葉の格好良さとは裏腹に、蜀という消去法的な山岳地帯を望まなければならない状況の時点で既に勝負の趨勢は付いていたのかもしれません。
どうしても「悪役」なイメージが強い曹操ですが、中国大陸の3分の2を統一したのはそれだけの力量があればこそ。決してただの悪役ではなく、大きな存在なのです。そんな曹操がライバルであった以上、さすがに天下統一は厳しかったでしょう。
③諸葛亮との出会いが遅かった
■ ③諸葛亮との出会いが遅かった
③諸葛亮との出会いが遅かった
たらればを言い出したらキリがありませんが、諸葛亮との出会いがもう少し早ければ劉備(玄徳)の運命はまた違ったものになっていたのかもしれません。そもそもそれまでの劉備(玄徳)は軍略というものがありませんでした。流れに身を任せて戦い、勝てば官軍、負ければ流浪。黄巾の乱以降、結局はこの繰り返しでしかありませんでした。
しかし諸葛亮、厳密に言えばその前に出会った徐庶のような、いわゆる知略家との出会いがもっと早ければ目の前の戦いだけではなく、長い目で物事を考える戦略があったでしょう。
劉備(玄徳)と諸葛亮が出会った頃は劉備(玄徳)が劉表の元に身を寄せていた時代。
既に官渡の闘いにて袁紹に勝利した後で、天下の趨勢が曹操に傾いていた頃でした。この頃の曹操はいわば破竹の勢い。ましてや曹操は並の男ではありません。それだけに、結局は曹操の勢いを止めることは出来ませんでしたが、もう少し早く諸葛亮のような軍略家に出会い、長期的なビジョンを聞かされていたらまた違った形になっていたかもしれませんが、諸葛亮と出会えたのも流浪の身となって劉表の元に身を寄せたからこそ。運命の歯車はなかなか都合よくは回ってくれないものですね。
④荊州を奪われてしまったから
■ ④荊州を奪われてしまったから
④荊州を奪われてしまったから
現実的に考えるとこれも大きいでしょう。荊州はとても豊かな場所でした。この地が自分の物か、あるいは他人のものかによって蜀の価値そのものまで変わると言っても決して過言ではなかったでしょう。そのようなことは劉備(玄徳)とて分かっていたからこそ、関羽という最も頼れる武将に守らせていたのは言うまでもありません。理由の如何はともかく、結局荊州は呉の手に渡ってしまい、関羽も亡くなります。
これにより先にも触れた夷陵の戦いが行われることになるのですが、荊州を落としていなければ夷陵の戦いも起きていませんでした。
無駄な戦力を対呉に使うことなく、対魏に使うことが出来たでしょう。そもそも荊州を落とす直前、劉備(玄徳)は漢中を曹操から奪っているのです。益州を手に入れ、戦力も整い、これから曹操の喉元を…という時の出来事なだけに大きな出来事となってしまったのはもちろんですが、荊州という立地を考えてもここを守り切れなかったのは致命傷でした。
では関羽以外であれば荊州を守れたのかといえばそれも難しいでしょう。劉備(玄徳)だけではなく、曹操も孫権も荊州を欲しがっていたのですから。
⑤中国が広く、更には蜀が山岳地帯だったから
■ ⑤中国が広く、更には蜀が山岳地帯だったから
⑤中国が広く、更には蜀が山岳地帯だったから
天下統一した人間がいる以上、言い訳にしかならないかもしれませんが、蜀という立地を考えるとどうしても、どこかに戦いに行こうとすればすべてに於いて大々的なものとなってしまいます。例えばですが北伐の際、漢中から長安だけを見ても日本の立地に当てはめると名古屋と東京程度離れているのです。電車も飛行機もない時代、その距離を移動するだけでも兵士は疲れていたでしょう。
ましてや蜀は山岳地帯。平野部の300キロメートルと山岳地帯とでは訳が違います。
魏や呉は山岳地域ではないので兵の移動も行いやすかったため、どうしても蜀は不利な立地でした。もしも、これが逆で魏が山岳地帯で蜀が平原であれば、或いは劉備(玄徳)は曹操とも決着をつけられていたかもしれません。しかしこの点は言い出したらキリがない部分ではあります。そもそも、このような場所だと分かって領地を手に入れたのは他ならない劉備(玄徳)ですし。
まとめ
■ まとめ
まとめ
豊富な人材が多々あつまる不思議な仁徳を持つ劉備(玄徳)。もっと上手く立ち回っていれば天下統一が出来たのではないかとの声もありますが、志半ばにしてこの世を去ります。最後は夷陵の戦いでの大惨敗の後、悲嘆の中での死去となったようですが、もしもまだまだ長生きしていたら三国志の歴史はまた違ったものになっていたのかもしれません。それを思うと、やはり荊州陥落は蜀、劉備(玄徳)にとって想像以上に大きなものだったのでしょう。