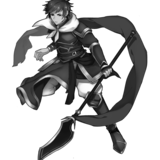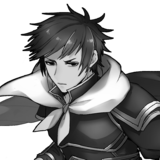死せる 孔明 生ける 仲達 を走らす
■ 死せる 孔明 生ける 仲達 を走らす
死せる 孔明 生ける 仲達 を走らす
魏・呉・蜀の三国が鼎立した三国時代。
街亭の戦いから6年後、諸葛亮の北伐遠征は5度目を迎えていた。
蜀軍は五丈原に布陣したが、対する魏軍は食料枯渇を狙って動かない。
幾度も諸葛亮の戦術にやられていた魏軍は、絶対に動かないと、持久戦に持ち込もうとしていた。
諸葛亮は、度々、司馬懿に戦いを挑んでいる。
しかし、司馬懿は、籠城して戦いに出てこなかった。
そこで、諸葛亮は、司馬懿の臆病者と挑発するため、女性物の髪飾りと服を送ることにした。
諸葛亮の使者が司馬懿の陣地にやってきた。
司馬懿は使者に諸葛亮の寝食や仕事が忙しいか暇かなどを尋ねたが、軍事については質問が及ばなかった。
このあたりは、司馬懿の賢者ぶりがよくわかる出来事だ。
使者は、諸葛亮は朝は早くに起き、夜は遅くに寝られ、杖で20回叩く以上の罰については全て自分でご覧になられます。
お食事の量は1日で数升に満たないほど少ないですと・・・。伝えてしまったのだ。
使者が去った後、司馬懿が、諸葛亮孔明は、食が細く、仕事が忙しい。
どうして長く生きられようか?
いや生きられないだろうとまわりに告げた。
しばらくして諸葛亮は重病になった。
ある夜、大きな星が現れ、赤い尾を引きながら諸葛亮の陣中に落ちていった。
そして、まだそれほど経たないうちに諸葛亮は死んだ。
諸葛亮の死を受けて蜀の楊儀は諸葛亮の遺言に従って帰還することになる。
人々は、大急ぎでその事を司馬懿に伝えた。
これを聞いた司馬懿は蜀の軍を追った。
諸葛亮に後継者として可愛がられていた姜維は、楊儀に旗を持たせ、進軍の太鼓を鳴らし、今にも司馬懿に向かおうとするようにさせた。
これを見た司馬懿は、諸葛亮がまだ生きていて、魏軍を罠にかけようとしていると感じてしまい無理に迫ろうとはしなかった。
人々は、この出来事をことわざにして言った。
「死んだ諸葛亮が生きている司馬懿(しばい)仲達を逃げさせた。」
これを聞いた司馬懿は、笑って言った。
私は生きている人間の行動を推し量ることは出来るが、死者の行動を推し量ることはできない。
と・・・
実際に孔明は死んでいたのだが、これまで孔明に何度も痛い目を見させられてきた司馬懿にとって、それほど孔明の影響力は大きなものであり、この出来事から死せる孔明、生ける仲達を走らすという諺が生まれたのだ。
司馬懿(しばい。179~251)は、三国志のかくれた主役でもある。
諸葛亮孔明の好敵手で勝ててはいないが、最終的に天下を統一したのは、司馬懿の孫・司馬炎の晋王朝である。
司馬懿は実質的な創業者として「宣帝」となる。
どれほど、諸葛亮孔明が、偉大であったのかがわかるエピソードだ。
司馬懿が、かつての敵陣に踏み入った時、死に際でも全てを整え去っていった孔明の聡明さに感嘆し、この状況を目に焼き付けるよう、息子たちに諭したのであった。
武田信玄公は、天下統一目前 志半ばで亡くなる。
徳川を破った後 信長との勝負目前だった。
信玄は、病の中、信玄が死んだとあっては反撃にあってしまうと思い、その死を3年間秘密にするよう遺言を残した。
日本でも同様なことがあります。
甲斐の武田信玄が天下統一目前で死に、そのことを3年間隠せとの遺言でした。
諸葛亮 孔明の蜀も、武田信玄の甲斐も、滅亡する結果となります。
やはり、偉大な聡明なリーダーの影響力は、すさまじいということです。