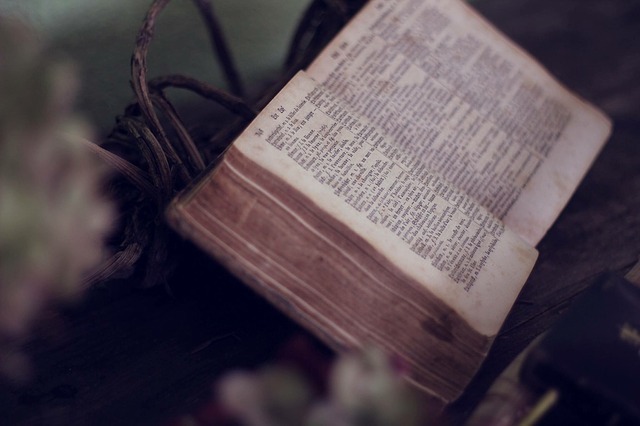1.曹丕の生涯
■ 1.曹丕の生涯
1.曹丕の生涯
曹操の三男として誕生
■ 曹操の三男として誕生
曹操の三男として誕生
曹丕は、曹操の三男として誕生しています。なぜ三男なのに曹操の後を継ぐことができ、魏の初代皇帝になれたのかというと、長男・次男が早くに亡くなっているからです。曹丕は、8歳にして、上手な文章を書くことができ、騎射や剣術にも秀でていたとされています。また、11歳にして曹操の軍中に従軍するなど、幼い時から活躍しているのです。
一人前になってからは、曹操の不在を守ることが多くなります。そして217年、曹丕は太子に指名されます。ちなみに、太子の指名については、弟である曹植と激しい後継者争いがあったとされており、曹丕は後継者争いを勝ち取ったとされているのです。
曹操の死から魏の初代皇帝に!
■ 曹操の死から魏の初代皇帝に!
曹操の死から魏の初代皇帝に!
太子に指名された3年後の220年、曹操が亡くなります。これにより、魏の君主として曹丕が君臨するようになります。そして、曹丕は検定に禅譲を迫ったのです。しかも、家臣たちに禅譲するよう上奏させ、献帝に禅譲を迫ったとされています。そして、献帝が禅譲を申し出ると辞退し、2度の辞退をした後に即位して魏の初代皇帝となったのです。
その後、曹丕は内政の様々な制度を整え、国内を安定させることに主軸を置きます。また、呉に対して3度の外征を行っています。しかし、いずれも失敗に終わっており、軍事面ではあまり活躍できていません。
40歳で死去…
■ 40歳で死去…
40歳で死去…
そんな曹丕ですが、226年に肺炎によって亡くなっています。まだ40歳のことであり、風邪をこじらせたことによる肺炎という説が一般的です。皇帝としての在位期間はわずか5年半ほどとなっており、志半ばで崩御されています。また、皇帝の在位期間の短さから、王朝の基盤を盤石にする前に亡くなったと言われており、魏の滅亡につながったとされているのです。ちなみに、曹丕が亡くなる間際、司馬遷や曹真、曹休などに太子である曹叡のことを託したとされています。
2.曹丕はどんな人物だった?
■ 2.曹丕はどんな人物だった?
2.曹丕はどんな人物だった?
残忍な性格
■ 残忍な性格
残忍な性格
曹丕は残忍な性格だったと言われています。残忍な性格だったことがわかるエピソードはたくさんあるのですが、その中でも甄夫人のエピソードが有名です。甄夫人は曹丕の側室であり、曹丕の寵愛を受けます。しかし、次第に曹丕からの寵愛が薄れていくことになります。そして、つい曹丕に恨み言を言ってしまったのです。その結果、まさかの死を賜ったのです。側室に対してあまりの仕打ちであり、残忍な性格であることがよくわかります。
また、于禁への仕打ちも残忍な性格であることがわかるエピソードです。于禁は、樊城の戦いで敗れ、関羽に降伏して捕虜となっています。その後、孫権が荊州を奪うと、今度は孫権捕らわれて賓客として扱われます。そして、曹丕が皇帝になると、孫権は于禁を魏に送還したのです。曹丕は于禁を慰め、曹操の墓を参拝させます。実は曹丕は、予め于禁が降伏した際の様子の絵を墓に描かせており、于禁は辱めを受けたのです。これが原因で憤死したとも言われています。このように、曹丕には残忍な性格であることがわかるエピソードがたくさんあるのです。
内政に力を入れて安定させる
■ 内政に力を入れて安定させる
内政に力を入れて安定させる
悪い部分ばかり注目される曹丕ですが、実は内政に力を入れた人物でもあります。宦官が一定以上出世することを制限させたり、太后に直接上奏するのを禁止したりしています。さらに特徴的なのが、九品官人法を制定したことです。この制度は、これまで地方主導だった人材登用を国主導に変えた制度です。国が任命した役人が人物を9等に分けて評価し、直接国に推挙して人材確保をするという制度となっています。
このように、曹丕は内政面を重視しています。その甲斐もあり、曹丕の治世は安定していたとされているのです。そのため、統治者としての評価は意外と高い傾向があります。
3.曹丕が魏滅亡の戦犯と言われる理由
■ 3.曹丕が魏滅亡の戦犯と言われる理由
3.曹丕が魏滅亡の戦犯と言われる理由
一族を権力から遠ざける
■ 一族を権力から遠ざける
一族を権力から遠ざける
曹丕が魏滅亡の戦犯とされる理由としては、一族を権力から遠ざけたことが挙げられます。父親である曹操は、身内を上手に登用して強い国を作り上げました。しかし、曹丕は真逆の国造りを行い、身内をできるだけ権力から遠ざけています。
曹操の後継者争いのライバルだった曹植の力を削いでいきます。曹植を後継ぎにしようとした武将らを誅殺しており、さらに曹植に政治的な力を全く与えませんでした。しかも、曹植は何度も転封とされ、亡くなるまで各地を転々とさせられています。ちなみに、曹植は突然死とされるのが一般的ですが、曹丕による毒殺との説もあります。
他にも曹彰を冷遇したり、過去に借財を拒否された曹洪を死罪にしようとしたりするなど、一族を大事にしなかったのです。これにより、曹家の力がどんどん弱まり、後々の魏の滅亡につながったとされているのです。
司馬懿の台頭を招く
■ 司馬懿の台頭を招く
司馬懿の台頭を招く
曹丕が魏滅亡の戦犯と言われる理由としては、司馬懿の台頭を招いたことも挙げられます。先ほど紹介したように、曹丕は身内の勢力を削いでいます。そして、司馬懿を重用したのです。司馬懿は最終的にクーデターを起こし、西晋の礎を築いています。つまり、曹丕が身内を重視し、司馬懿を重用しなければクーデターを阻止することができ、魏の滅亡を防ぐことができたかもしれないのです。そのため、曹丕は魏の戦犯の1人と言われているのです。
早過ぎた死
■ 早過ぎた死
早過ぎた死
曹丕が魏滅亡の戦犯とされる理由としては、早過ぎた死も関係しています。曹丕が皇帝として在位した期間は、たったの5年半ほどです。曹丕は身内の力を削いで、中央集権化を目指していました。しかし、早くに死んでしまったため、中央集権体制を完成させる前に亡くなってしまっています。中央集権体制をしっかりと築けていれば、その後の歴史がどうなっていたのかはわかりません。それだけに、曹丕の早過ぎた死が魏滅亡の戦犯とされる理由となっています。
4.まとめ
■ 4.まとめ
4.まとめ
今回は、曹丕がどんな人物だったのかを中心に紹介してきました。曹丕は、魏が滅んだ戦犯の1人とされています。この理由は、「一族を権力から遠ざける」「司馬懿の台頭を招く」「早過ぎた死」が挙げられます。これらの3つの要素が重なったことにより、曹丕は魏滅亡の戦犯とされているのです。
そんな曹丕ですが、性格はとても残忍だったとされています。実際に、曹丕が残忍な性格であることがわかるエピソードがたくさんあります。また、曹丕は内政面を重視した人物でもありました。宦官の出世を制限したり、九品管人法を制定したりしており、曹丕の治世は安定していたとされているのです。それだけに、曹丕が長生きしていたら、どうなっていたのかが気になるものです。