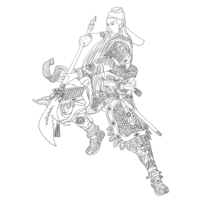ライバルが見ぬいた本性 「董卓を殺せ!」
■ ライバルが見ぬいた本性 「董卓を殺せ!」
ライバルが見ぬいた本性 「董卓を殺せ!」
前回までの記事で、董卓の青年期を見てきましたが、なにやらいいコトずくめですね。
しかし、後に朝廷の「魔王」となる董卓の恐ろしさを、見ぬいていた人間もいました。
それは、後に董卓とはげしい戦いをくりひろげることとなる、孫堅(そんけん)でした。
張温(ちょうおん/過去記事を参照)は涼州の反乱討伐に出陣するにあたり、主な将軍たちを招きました(作戦の打ち合わせをするのはもちろん、出陣前に上官にあいさつに来い、という意味です)。
しかし董卓は遅れて参上したばかりか、張温に叱責されても不遜な(ごう慢な)態度を取りました。
このとき孫堅は、張温に耳打ちしていいました。
「董卓を斬るべきです」
あいさつに遅刻し、態度がデカいとはいえ、いきなり死刑というのもどうかと思いますが……この驚くべき提案を、張温は戸惑いつつも却下します。
「董卓は涼州やその周辺では、武将として名声がある男だ。彼を殺せば、いまから西を攻めるうえで、頼りにする武将がいなくなる」
こうして孫堅の進言は退けられ、董卓は処刑されずに済みました。
董卓は武将としてたしかな力量があった反面、他人に対しごう慢な態度を取ることはあったようです。孫堅は、そんな董卓の振る舞いを見て「漢王朝に災いをもたらす者だ」と思ったのかもしれません。
事実、もしここで董卓が斬られていれば、後漢王朝はもう少しマトモな道を歩んだかもしれないのです。
目の上のタンコブ 名将・皇甫嵩
■ 目の上のタンコブ 名将・皇甫嵩
目の上のタンコブ 名将・皇甫嵩
ともあれ、張温の率いる朝廷軍は、涼州を完全に平定することはできませんでした(過去記事参照)。
この涼州がまた乱れます。先にも反乱を起こした韓遂(かんすい)が、今度は王国(おうこく)なる人物をトップに立てて、ふたたび兵を挙げたのです。
こうして董卓はふたたび、涼州の反乱討伐を命じられました(188年)。
このとき朝廷軍の総司令官に着任し、董卓の上官となったのが、黄巾の乱の鎮圧で大活躍した名将・皇甫嵩(こうほすう)でした。後漢王朝の英雄ともいうべき人物であり、董卓よりもはるかに高い名声をほこる武将です。
勢いに乗る反乱軍は、朝廷側の城を包囲し、攻撃しました。この城を救うことが、地域の防衛上とても重要です。董卓は急いで軍を進めるよう意見しました。
しかし皇甫嵩は聞きいれず、こう言ったのです。
「いまは反乱軍の戦力・気力が充実しており、攻撃すべき時ではない。城の守りは堅く、反乱軍の攻撃はしのげる。少ない犠牲で勝つには、しばらく城を攻めさせておいて、敵が消耗するのを待つべきだ」
こうしてしばらく様子をみていたところ、皇甫嵩の予言どおり、反乱軍は城攻めをあきらめて退却をはじめました。ただちに追撃しようとする皇甫嵩に対し、董卓は反対意見を述べました。
「あまり敵を追いつめてはいけない。相手が死に物狂いで戦えば、こちらの犠牲も大きくなる」
しかし皇甫嵩は、またしても董卓の進言を却下し、いいました。
「私がしばらく時を待ったのは、反乱軍の戦力・気力が衰えるのを待っていたからだ。敵軍が疲れきって、戦意をなくして逃げていくいまこそ、奴らを叩く好機なのだ」
2人の意見は最期まで合わず、皇甫嵩は董卓を置いて、反乱軍を単独で追撃しました。皇甫嵩の言うとおり、反乱軍は疲れきったうえに戦意もありません。朝廷軍は連戦連勝をおさめ、皇甫嵩は反乱軍を1万人以上も討ち取ったといいます。
こうして、皇甫嵩の名声はいよいよ高まり、功績はすべて彼のものとなりました。その一方で、評価を落としてしまった董卓は大いに恥じ入り、皇甫嵩をはげしく憎んだといいます。
(なんだか、逆ウラミのような気もするのですが……)
董卓も皇甫嵩も一線級の武将であり、兵法書(へいほうしょ)に書かれた理論に基づいて戦っていることに、変わりはありません(董卓の主張にも一理あるのです)。しかし、軍事理論の実戦での応用については、後漢の名将・皇甫嵩が一枚上手だったということなのでしょう。
オレの兵隊は、だれにもわたさん!
■ オレの兵隊は、だれにもわたさん!
オレの兵隊は、だれにもわたさん!
その後、朝廷は董卓にある命令を下します。
高い官職につけてやるから、持っている軍隊を皇甫嵩にあずけるように……というものです(あるいは朝廷も、董卓に軍を持たせておくのが危険だと思ったのかもしれません)。
しかし董卓は「涼州の治安が、まだまだ良くなっていない」として、命令を拒否しました。
その後、朝廷はまた同様の命令を下します。今度は并州(へいしゅう)の長官にしてやる代わりに、やはり皇甫嵩に軍をあずけて任地に向かえ……というものでした。
このときも董卓は「軍を率いて任地に向かってこそ、国のお役に立てる」と、またしても命令を拒否したのです。
朝廷からの命令とは、皇帝の名前で出されています。つまり勅令(ちょくれい/皇帝からの命令)です。
勅令に2度も逆らうなど、普通は考えられません。董卓という男は、自分の軍隊はなにがなんでも手放したくないこと、いざとなれば皇帝の命にも逆らう人物だということが、よく分かりますね。
(別の観方をすれば、地方のいち将軍が2度も続けて勅令を拒否できるほど、後漢王朝の権威は地におちていたということでもあります)
董卓は最期まで勅令に従うことはなく、自分の軍勢を率いたまま、時局をうかがっていたといいます。武将として各地を転戦するうちに、彼は後漢王朝の衰えを肌で感じたのでしょう。
「近いうちに、歴史は大きく動く。その時のために、いまは俺の軍勢を温存しておるのだ」
……董卓は、こんな風に考えていたのだと思います。
そして、彼の目論見は見事に当たりました。
大将軍・何進(かしん)より、軍を率いて都に入れとの命令が下ったのです。
何進の死! 次はオレの時代だ
■ 何進の死! 次はオレの時代だ
何進の死! 次はオレの時代だ
都(首都)は皇帝の居城であり、おいそれと軍隊を率いて入ることはできません(下手をすれば反乱者と見なされてしまいます)。
しかし、武官の最高位である「大将軍」からの命令であれば、堂々と軍を率いて都に入城できます。
大将軍・何進の命令は、野心家の董卓に、その口実を与えたのです。
何進は、美人の妹が先帝(霊帝)に愛されたおかげで出世した男です。
彼女は霊帝の男子を産んで皇后となり、霊帝の死後は息子が皇帝に、自身が皇太后となりました(何太后(かたいこう)と呼ばれています)。
この皇太后である妹との連携で、何進は長く大将軍の地位にありました。
その何進には、国の政治を乱す元凶である宦官(かんがん/注)を打倒するという、大きな政治目標がありました。しかし肝心の何太后が宦官と親密なため、賛成してくれません(皇太后の権威は絶大であり、いくら妹とはいえ、その意思にそむくことは簡単ではなかったのです)。
「何太后に言うことを聞かせるには、軍事力でおどしをかけるしかない。諸国の軍勢を集めろ」
ということで、何進は董卓らを都に呼び寄せたのです(あまり上手い策だとは思わないですが…)。
しかし何進は、宦官打倒を成しとげられぬまま、逆に宦官の謀略で殺されてしまいました。
ここから一気に、時局が動きます。
そう。董卓の望む、さらなる乱世がやってきたのです。