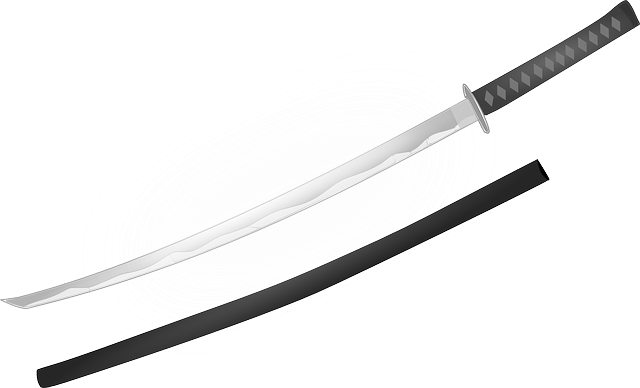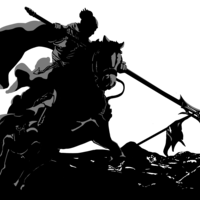時は三つ巴の219年
■ 時は三つ巴の219年
時は三つ巴の219年
219年と言えば、三国志の時代では激動の1年です。
1月には益州を制した劉備(玄徳)は、定軍山の戦いで曹操の重臣・夏侯淵を討ち、漢中も平定して、7月に漢中王となりました。
さらに8月には荊州の関羽が北上し、曹操の領地に侵攻。しかし江東の覇者・孫権はその隙を突いて荊州南部に侵攻。
まさに三つ巴の激戦が繰り広げられています。
曹操は216年に魏王となっていますが、皇帝には即位していません。漢王朝は以前として存続している状態です。譲位を迫り、皇帝に即位するのは曹操の死後、子の曹丕の代になります。
劉備(玄徳)が蜀の皇帝に即位するのは、その後の221年。同年に孫権は魏より呉王に封じられています。孫権が呉の正式な皇帝に即位するのは229年のことです。
厳密には219年には魏呉蜀が成立していたわけではありませんが、三大勢力がしのぎを削っていたことには違いがありません。
もし日本の戦国時代から一人スカウトできるとしたら
■ もし日本の戦国時代から一人スカウトできるとしたら
もし日本の戦国時代から一人スカウトできるとしたら
ここで、「もし、この219年に、日本の戦国時代から一人スカウトできるとしたら誰を選ぶのか?」を想像してみましょう。
13世紀以上未来からの引き抜きにはなりますから、完全に仮想のお話にはなりますが、三国志に登場する個性豊かな英雄たちに負けず劣らぬ顔ぶれですので、想像するだけでもワクワクしますね。
戦場で関羽や張飛に匹敵するような活躍を見せる猛将を選ぶのか、周瑜や諸葛亮(孔明)に匹敵するような戦略家を選ぶのか、曹操や劉備(玄徳)に匹敵するようなカリスマを選ぶのか……
はたしてどんな人材を選ぶと、さらに勢力を拡大することができるのでしょうか?
魏・呉・蜀でそれぞれ考えていきましょう。
魏がスカウトするのはこの人!
■ 魏がスカウトするのはこの人!
魏がスカウトするのはこの人!
魏の君主は優れた人材であればどんどん重用する曹操です。ですから家臣の顔ぶれを見ても優秀な文官、武官ばかりになっています。領土や兵力、経済力だけでなく、人材面でも最も有利だったのが魏ということになるでしょう。
人材不足ではありませんが、ここは北上する関羽の猛攻を撃退できる戦上手が欲しいところです。
そう考えると、「軍神」、「越後の龍」、「毘沙門天」として畏怖された「上杉謙信」でしょうか。謙信であれば、関羽と互角以上の戦いができるはずです。
孫権の力を借りずに関羽を撃退し、荊州を制圧してしまえば、魏のアドバンテージは決定的なものになります。さらに謙信がいる限り、荊州は安泰です。
問題は義に篤い謙信が、曹丕による禅譲を許すのかということになるかもしれません。もしかすると曹丕の皇帝即位に反対して、反旗を翻し、より一層話がこじれる可能性もあります。劉備(玄徳)の蜀漢に協力するような事態になるかもしれないのです。
呉がスカウトするのはこの人!
■ 呉がスカウトするのはこの人!
呉がスカウトするのはこの人!
呉の君主は孫権になります。周瑜、魯粛亡き後、軍事面の大黒柱は呂蒙です。さらに陸遜が頭角を現すことになりますが、やはり他国に攻め込むには人材不足ではないでしょうか。
ここは戦場での活躍だけでなく、他国を上手に吸収することのできる手腕を持つ「武田信玄」をスカウトすべきです。「甲斐の虎」の異名を持ち、徳川家康を破り、織田信長を震え上がらせた戦国時代の最強クラスの英雄のひとりになります。謙信と激突を繰り返した川中島の戦いは有名です。
呉は守りにおいては水軍が威力を発揮しますが、他国に侵攻するとなると、やはり陸上戦に強くならなければなりません。そうなれば曹操の領土である揚州北部(寿春・合肥近郊)、豫州の切り取りも可能です。
信玄は騎馬隊の統率にも優れていますから、呉が北に領土を拡大するためには貴重な存在になります。武勇では曹操軍トップクラスである張遼を破り、合肥に拠点を築くことができれば、今後の選択肢も増えていきます。荊州、豫州、徐州とどんどん領土拡大ができるはずです。
問題は関羽が北上した際に、曹操と手を結び関羽の留守を狙うのかどうかでしょう。史実ではこれに成功して荊州南部を制圧することができ、陸遜の活躍によって復讐戦に出てきた劉備(玄徳)を撃退しています。
先に荊州南部制圧を狙うのか、それとも劉備(玄徳)と協力する形で呉は揚州北部制圧を狙うのか、信玄のような存在がいれば話は大きく変わっていたかもしれません。
蜀がスカウトするのはこの人!
■ 蜀がスカウトするのはこの人!
蜀がスカウトするのはこの人!
最も問題なのは人材不足、兵力で劣る蜀でしょう。
君主は劉備(玄徳)になります。四方を高い山脈で囲まれている益州は、まさに自然要塞で守るには有利ですが、攻めるには逆に兵站などの問題が浮上し、足枷になります。
荊州南部には最強を誇る関羽がいますが、プライドが高く、孫権に対しての傲慢な言動も問題になっており、つけ入る隙がまったく無い状態ではありません。さらに劉備(玄徳)には荊州にも益州にも地縁があるわけでは無いのです。皇族宗家の血統と、これまで築き上げてきた人望が頼りになっています。
ここはやはり最優先で荊州南部の守りを固め、孫権に隙を見せないことです。そのためには先々を見通し、戦略に優れた人材が必要になります。諸葛亮(孔明)がいますが、益州から離れられません。白眉の異名を持つ馬良が関羽の参謀に付いていたと考えられますが、プライドの高い関羽にどこまで的確なアドバイスができたのかは不明です。
その辺りの機微にも敏感な人物と言えば、「真田信繁」(真田幸村)でしょうか。豊臣秀頼方について徳川家康を最期まで苦しめました。味方がどのような不利な状態に陥っても裏切ることはないでしょうし、戦術にも長けています。正しいと思うことははっきりと主張することもできます。
関羽が北上し、曹操の領土である襄陽や樊城を攻めている間も、信繁が留守をして、守っていれば間違いはないでしょう。呂蒙や陸遜の策略も信繁は看破できるはずです。孫権も荊州南部への侵攻を諦めて、合肥攻めに全力を注ぐことになるかもしれません。
まとめ・この三人が加わったら話がまったく変わる
■ まとめ・この三人が加わったら話がまったく変わる
まとめ・この三人が加わったら話がまったく変わる
ということで、「魏には上杉謙信」、「呉には武田信玄」、「蜀には真田信繁」がスカウトされました。荊州一帯はより混迷が深まり、先が読めなくなりましたね。もしかしたらこれによって、曹氏の天下が一気にひっくり返される可能性もあります。
どうでしょうか、皆さんの想像と一致したでしょうか?あなたは誰が加われば、最適だと思いますか?
三国志の転換期に当たる219年、そんな想像をしてみて楽しむのも結構面白いですよ。