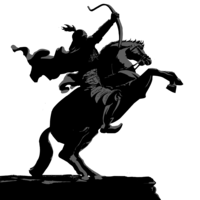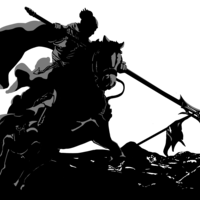1.劉備(玄徳)が天下を取れなかった理由!
■ 1.劉備(玄徳)が天下を取れなかった理由!
1.劉備(玄徳)が天下を取れなかった理由!
同世代に曹操がいた!
■ 同世代に曹操がいた!
同世代に曹操がいた!
劉備(玄徳)が天下を取れなかった理由としては、曹操の存在が挙げられます。劉備(玄徳)が161年生まれだったのに対し、曹操は155年生まれとほぼ同世代と言っていいでしょう。つまり、劉備(玄徳)が天下を取るためには、曹操は必ず越えなければならない相手だったのです。
しかし、曹操は素晴らしい能力を持っており、劉備(玄徳)が純粋に戦って勝つのは厳しいです。史実では、赤壁の戦いで劉備(玄徳)は曹操に勝っていますが、孫権と同盟して連合軍だったから勝てたと言っていいでしょう。劉備(玄徳)にとって、同世代に曹操がいたのは、天下を取れなかった理由のひとつなのです。
荊州を死守できなかった!
■ 荊州を死守できなかった!
荊州を死守できなかった!
劉備(玄徳)が天下を取れなかった理由は、荊州を死守できなかったことも挙げられます。荊州はとても豊かな土地であり、荊州を手に入れることで、天下に近づけると言っても過言ではありません。劉備(玄徳)ら蜀は、一時荊州を手に入れています。劉備(玄徳)も、荊州の重要さについては認識しており、関羽に守られているのです。
しかし、関羽は荊州を守り抜くことができませんでした。これは、関羽のミスと言ってもいいでしょう。関羽は政治家として三流であり、孫権との関係を悪化させてしまったのです。その結果、樊城の戦いで敗北することになり、関羽は亡くなり荊州も呉のものとなってしまったのです。
劉備(玄徳)が天下を取るためには、何が何でも荊州を守らなければいけませんでした。それが天下を取るための最低条件と言っても過言ではなかったのです。つまり、関羽に荊州を任せ、呉に荊州を掠め取られた時点で、劉備(玄徳)の天下統一は詰んだようなものだったのです。
名君ではなかった!
■ 名君ではなかった!
名君ではなかった!
劉備(玄徳)が名君でなかったのも、天下を取ることができなかった理由だと考えることができます。劉備(玄徳)は人徳があり、名君をイメージする方が多いと思います。しかし、実際には名君とは言い難いのが現実です。
名君なら、現実主義的で国の為に決断をしていく必要があります。しかし、劉備(玄徳)は自分の感情を優先させる傾向があるのです。劉表が亡くなる際、諸葛亮は劉備(玄徳)に対し、荊州を奪うように進言しています。だが、劉備(玄徳)はその進言を受け入れなかったのです。受け入れて、荊州を奪うことができていれば、天下を取ることもできたかもしれません。
また、夷陵の戦いでは、逆に諸葛亮の助言を無視して強行しています。この強行した理由は、関羽の弔い合戦としての意味合いが強いです。もちろん、強行して勝っていれば問題ないのですが、結局は戦力の消耗をしただけであり、無駄な戦いでしかなかったのです。このように、自分の感情を優先してしまう劉備(玄徳)は名君ではなく、天下を取る器ではないと言えるでしょう。
2.劉備(玄徳)に足りなかったらもの!
■ 2.劉備(玄徳)に足りなかったらもの!
2.劉備(玄徳)に足りなかったらもの!
人材
■ 人材
人材
劉備(玄徳)に足りなかったもののひとつは人材です。三国志演義のイメージが強いため、劉備(玄徳)は多くの有能な部下がいたと思われています。しかし、史実を見る限り、人材が枯渇していたと言えるのです。確かに、諸葛亮は軍師・政治家としては有名ですし、関羽や張飛の武力は目覚ましいものがあります。だが、曹操陣営に比べれば、圧倒的に人材が足りません。そのため、劉備(玄徳)が天下を取るために足りなかったのは、人材と言えるのです。
スタートライン
■ スタートライン
スタートライン
そもそも、スタートラインから足りないと考えることもできます。曹操や孫権などの曹家や孫家は名門ですが、劉備(玄徳)は没落した王族の末裔となっています。この時点で大きな差があるのです。王族の末裔と言えば大きなメリットと思えますが、そうではありません。なぜなら、王族の末裔は何十人もおり、大きなメリットにはならないのです。
一方、曹家や孫家のように名門なら、それだけで人材が集まってきます。人の名声に群れるものであり、名門は何もせずとも人材を集めることが容易です。しかも、名門なのでもともとの勢力や軍資金も豊富です。
このように、劉備(玄徳)と曹家・孫家とはスタートラインが全然違うのです。劉備(玄徳)が名門の出であり、もともとの勢力や軍資金があれば、天下を取ることができたのかもしれません。運も実力のうちと言いますが、生まれ家はまさに運であり、この点において劉備(玄徳)は足りなかったと言えるのです。
戦略眼
■ 戦略眼
戦略眼
劉備(玄徳)が天下を取るために足りなかったのは、戦略眼と言えます。天下を取るためには、計画が必要であり、そのためには戦略眼がとても重要となっています。しかし、劉備(玄徳)には戦略眼を持つ人材が不足しているのです。諸葛亮は戦略眼を持っているとのイメージがありますが、劉備(玄徳)を始め他の蜀の人物は戦略眼を持っているとは言えません。蜀軍は、行き当たりばったりで戦っている印象が強いです。やはり、劉備(玄徳)やその周りには戦略眼がなかったことが、天下を取るため足りなかったものと言えるでしょう。
優秀な親族
■ 優秀な親族
優秀な親族
劉備(玄徳)に足りなかったのは、優秀な親族でもあります。天下を取るためには、信用できる人材が必要です。そして、手っ取り早く信頼できる人材を確保するためには、親族を利用するのが一番です。実際、曹操には夏候惇や夏侯淵、曹仁など多くの親族で脇を固めています。しかし、劉備(玄徳)には優秀な親族がおらず、信用できる人材の確保が難しかったのです。人材が足りなかったというのにつながるのですが、優秀な親族がいなかったことも、劉備(玄徳)が足りなかった部分と言えるでしょう。
3.まとめ
■ 3.まとめ
3.まとめ
今回は、劉備(玄徳)が天下を取ることができなかった理由と足りなかったものを紹介してきました。劉備(玄徳)が天下を取ることができなかった要因としては、曹操の存在や荊州を死守できなかったことなどが挙げられます。同世代に曹操が立ちはだかったのは、劉備(玄徳)からすれば不運だったと言えるでしょう。また、荊州を死守できれば、天下を取る可能性はありました。しかし、呉に掠め取られた時点で、天下取りは実質詰んだようなものだったのです。
劉備(玄徳)に足りなかったのは、人材や戦略眼などが挙げられます。史実を紐解いていくと、どうしても劉備(玄徳)陣営の人材は不足しています。しかも、戦略眼を持っている人物がいません。そのため、戦略的に行動ができず、天下を取ることができなかったのです。とは言え、劉備(玄徳)は天下を取れなかったからこそ、魅力的に映るのかもしれません。