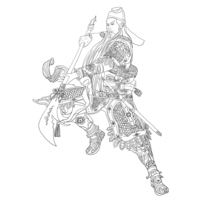遼東の反乱を征する
■ 遼東の反乱を征する
遼東の反乱を征する
司馬懿は諸葛亮との激闘を終え、しばらく平穏な時期を過ごしていましたが、魏の北東に位置する遼東で公孫淵が反乱を起します。遼東の地は元々公孫氏が台頭していましたが、曹操によって臣下の礼がとられていたものの、実際には心服していませんでした。公孫淵は呉の孫権ともつながっており、魏と天秤にかけた状態で勢力を保っていきました。しかし、呉の使者を惨殺し、魏に送り届けたことで孫権の怒りを買う事態となっていきます。
孫権は朝鮮の高句麗と通じ、遼東への進出を図りますが、魏からはカン丘倹が派遣されており、北方の単于を動かしたことで孫権は遼東を諦めました。魏は公孫淵に対し、明らかな臣従を求めるために上洛を示唆します。表向きは従う振りをするものの、公孫淵はカン丘倹の軍を攻めて完全な反乱を起しています。
公孫淵の反乱は魏国内でも問題になり、皇帝の曹叡は司馬懿を派遣する決断を下します。曹叡は公孫淵がどうやって自軍に対応するかを問われた司馬懿は、「城を捨てて逃げるのが上策ですが、公孫淵は城を捨てるような知恵者ではありません」と答えています。
さらに、遼東を制圧するのに1年もあれば十分といい、自信満々に出征していきました。遼東では雨が続き、遠征軍にとって厳しい環境となっていました。曹叡の側近たちが心配して遠征の中止を訴えますが、曹叡は司馬懿の実力を十分信頼しているので、全く相手にしませんでした。
圧倒する司馬懿
■ 圧倒する司馬懿
圧倒する司馬懿
司馬懿が布陣するころ、公孫淵は呉に援軍を求めますが、先の一件があったこともあり、孫権は全く相手にしませんでした。自軍だけで魏軍を相手にしなくてはならず、公孫淵は数万の軍を率いて仕掛けますが、司馬懿の配下によって蹴散らされています。
公孫淵は守備を固くしていきますが、司馬懿は公孫淵の本国を叩くように仕向け、偽りの退却を見せています。慌てた公孫淵でしたが、司馬懿の用兵の前に連敗し、本城を包囲されて籠城しました。
長雨によって作物が収獲できず、さらに規模の大きい兵力を囲っていたことから、公孫淵が食料不足で自滅するのは間違いないと司馬懿は予測していました。司馬懿は自分の配下に対し、兵力を持って兵糧が少ない場合には城から速攻で打ってでるのが正しく、兵力が少なくて兵糧を持っているときには籠城するのが得策と告げます。
司馬懿からすれば公孫淵の取った行動はまさに真逆であり、将としてふさわしくない人物に映っていたはずです。事実、公孫淵は兵糧不足から降伏を決断し、遼東は魏の支配下に置かれることとなりました。
しかし、司馬懿は公孫淵の降伏を許さず、一族もろとも粛清し、後遺の憂いを断つために15歳以上の男子をすべて処刑しました。司馬懿の恐怖ともいえる粛清に魏国内でも取り上げられますが、だれも司馬懿に意見できるものはいなかったといいます。
権力闘争に巻き込まれる
■ 権力闘争に巻き込まれる
権力闘争に巻き込まれる
遼東を制圧したのち、皇帝の曹叡が病に倒れます。曹叡は曹丕が若くして亡くなり、急きょ即位しましたが、文学だけでなく軍事面でも才を発揮し、聡明な皇帝として曹丕以上の評価を得ていました。しかし、自身まで若くして死ぬこととなり、曹真の長男である曹爽と司馬懿に次期皇帝となる少年の曹芳の補佐を託しました。
司馬懿は権力闘争には嫌気を差していましたが、自分が思っている以上に周囲が委縮しており、畏怖を感じている曹爽ら皇帝の親族たちからは邪見にされていました。しかし、軍権を掌握している司馬懿をおいそれと扱うことはできないので、曹爽らは司馬懿を名誉職に栄転させて権力を剥奪するように努めていきました。
曹爽との対立
■ 曹爽との対立
曹爽との対立
呉では魏の若い皇帝が即位したことを受けて、国内は混乱しているに違いないと考え、魏への遠征を考えていきました。孫権の号令のもと、大軍が荊州方面や揚州方面に軍を分けて進軍していきました。呉の朱然らが樊城を包囲すると、司馬懿は周囲が反対するのを退けて、自ら兵を率いて進軍し、呉軍を退けています。
朱然は司馬懿の前に慎重に退却を指示しますが、司馬懿はこれも見破り、呉軍を大いに破っています。元々蜀の司令官として戦ってきた司馬懿ですので、対呉でも功績を残すこととなり、いまだ目立った功績のない曹爽陣営は大慌てで蜀を攻める準備を始めました。
244年に曹爽が大規模な遠征軍を起こすと、司馬懿は失敗を恐れて猛烈に反対しました。司馬懿を見返すチャンスと考えた曹爽はなりふり構わず15万もの大軍で出征していきました。もとより蜀を制圧することは考えておらず、漢中を攻略するだけでも十分な戦果として帰国する予定であり、曹爽に気負いはなかったといえます。
しかし、漢中を守るのは北伐でも大活躍した王平であり、3万ほどの軍を率いて懸命に守備しました。王平は魏の大軍を狭い峡谷に誘い込み、身動きが取れない状況にして蜀からの援軍を待ちました。王平の思惑通りにはまり、蜀の援軍までも到着してしまったので、長期戦となってしまった曹爽は撤退を指示しています。
これに蜀軍は追撃してきたので、魏軍は惨敗を喫し、曹爽は命からがら帰国することができました。発言力を大きくできなかった曹爽と司馬懿の対立は深くなっていきます。さらに246年に呉へと侵攻したときにも司馬懿の反対を押し切って失敗した曹爽は、権力闘争には自身が軍事面で貢献するよりも司馬懿の失脚を狙うほうに照準を定め、暗殺を含めた手段を講じていきます。
一時引退する司馬懿
■ 一時引退する司馬懿
一時引退する司馬懿
身の危険を感じた司馬懿は70歳を超えて高齢と病がちと称して引退を決意し、一庶民として暮らすようになります。司馬懿の活躍を知っている諸将らは幾たびもその元を訪れるようになり、曹爽は警戒を怠ることはありませんでした。これに困った司馬懿は、一計を案じ、曹爽の側近が見舞いにきたとき、わざと言葉を聞き間違え、狼狽する姿を見せており、痴ほう症の素振りを見せつけました。その姿を伝え聞いて安心した曹爽は、司馬懿への警戒心を解いてしまいます。
クーデターを興し、息子たちに受け継ぐ
■ クーデターを興し、息子たちに受け継ぐ
クーデターを興し、息子たちに受け継ぐ
司馬懿は曹爽と曹芳が洛陽を留守にしたのを受け、曹叡の妻である郭太后を味方に付けて曹爽一派の官職を解任させました。そのまま宮殿に入り、洛陽を占拠すると、司馬懿は曹爽を捕えて降伏させています。司馬懿は曹爽を処罰し、曹氏の実権を取り戻さんとする勢力の反乱軍までも封じ込み、皇族や政務、軍事といった魏国のすべてを掌握するようになっていきます。
司馬懿はクーデターを起こした年に亡くなりますが、息子たちが跡を継ぎ、孫の司馬炎が晋を興して新皇帝に即位することとなっていきます。司馬懿が成功できたのも、自身が魏の権力者であった曹氏や夏候氏といった一族ではなかったので、いらぬ疑いをかけられぬよう慎重に行動したことが幸いしたといえます。