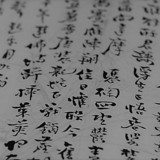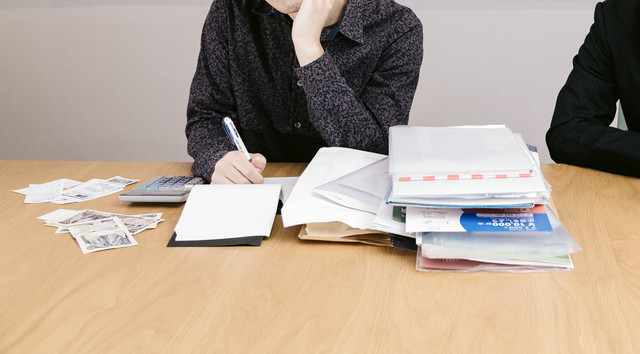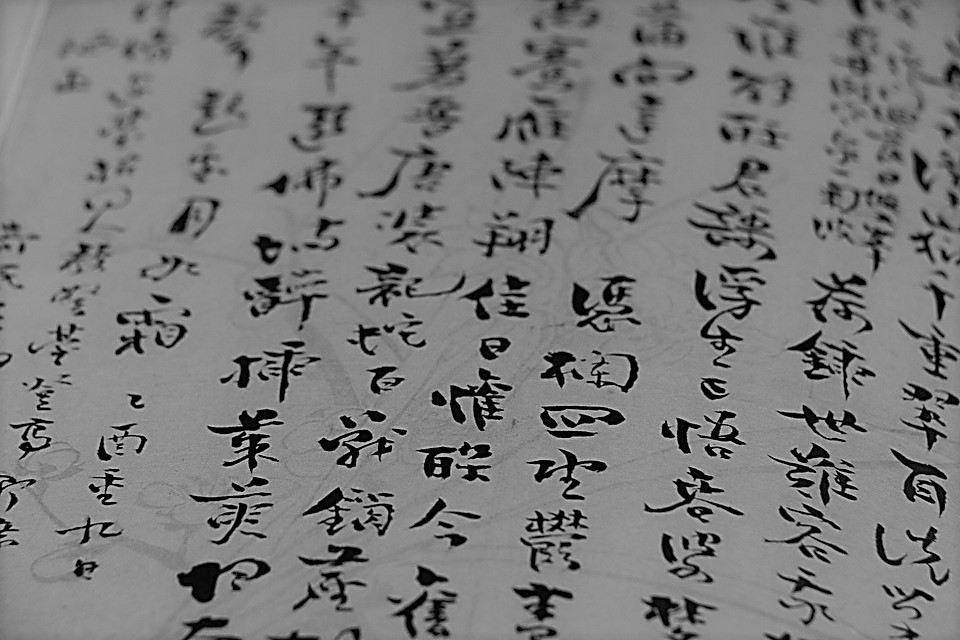そもそも記録が残っていない
■ そもそも記録が残っていない
そもそも記録が残っていない
三国志は日本のみならず現在ではアジア圏の枠を越え、欧米諸国の人々からも愛されている世界的な物語です。日本と三国志の舞台の中国は古くから交流があり、紀元前の時代からの付き合いです。そのことについては金印を受領したことで有名な奴国の王や親魏倭王の称号をもらった卑弥呼などを義務教育で学習するので、ご存知の方も多いことでしょう。
ゲームや小説、映画、ドラマなど三国志を題材とするエンタメは多くあります。日本人なら誰もが知っている戦国武将や政治家などの歴史的な偉人たちも歴史書や講談という形で三国志に触れてきました。しかしながら、「三国志はいつ日本に入ってきた」という記述は日本の歴史書、偉人たちの日記など歴史的な史料のどれを読んでもありません。
そのため、三国志が日本に入った件について我が国では古くから謎とされてきました。
それ以前では?というところまで解明できている
■ それ以前では?というところまで解明できている
それ以前では?というところまで解明できている
先に示すとおり厳密に「いつ三国志が日本に入ってきた」という記述はどこにも存在しません。それでも「これ以前に入ってきたはず」というところまでは解明できています。この考察を示した人物の名は渡邉義浩先生です。渡邉義浩先生は三国志研究の大家。現役早稲田大学の教授にして数多くの書籍を出版。三国志のドラマの日本語吹き替えの監修やテレビのコメンテーターとしても活躍しており、三国志学会事務局長を務められている研究者なので、信用するに足る情報であると判断します。
三国志が入ってきたのは奈良時代以前
■ 三国志が入ってきたのは奈良時代以前
三国志が入ってきたのは奈良時代以前
三国志が入ってきたのは陳寿が正史三国志を書いてから約500年後である奈良時代以前であると渡邉義浩先生は「三国志と日本人」という書籍で考察を述べています。
その根拠は日本の歴史書である古事記の書き方です。そもそも古事記にどのようなことが書かれているのかご存知でない方のために古事記の概要を説明しましょう。
古事記は聖武天皇が稗田阿礼(ひえだのあれ)らに命じて作成に当たらせた史上初の日本の歴史書です。それ以前までは日本の歴史に関する書物はなく、国の成り立ちやそれまでに起きた歴史的な事件はすべて口伝で伝えられてきました。聖武天皇は皇室の系譜などが曖昧でした。そしてこの古事記の書き方は紀伝体という体裁をとっています。
紀伝体とは人物や事件などに「○○紀」や「○○伝」という章を立て、それについて時系列に書き表していく書き方のことを指します。
陳寿の書いた正史三国志は紀伝体で書かれています。これはどういうことかというと、古事記の制作に携わった稗田阿礼たちはそれまで日本に歴史書がなかったため、お隣の中国の歴史書の書き方を見本とするしか方法がなかったと考えられています。
三国志を日本に持ち込んだとされる者
■ 三国志を日本に持ち込んだとされる者
三国志を日本に持ち込んだとされる者
三国志が日本に入ってきたのは奈良時代以前ということを前提として考えると、三国志が日本に入るためには誰かが三国志の写本を日本へ持ってくるか、学んできた人々が帰国する際に持ち帰るしか方法がありません。
そこで三国志を日本に持ち込んだこの者ではないのか?と考えられているのが遣唐使です。遣唐使と言えば、日本から中国へ仏教を学ぶために海外留学をした人々です。遣唐使たちは仏教だけを学んできたのかと言えばそうではありません。例えば琵琶を日本に持ち込んだのも遣唐使、日本には当時いなかった猫を持ち込んだのも遣唐使、暦学や天文学を学んできたのも遣唐使、お茶を日本に持ち帰ったとされる栄西という僧侶も中国でお茶を学び日本に持ち帰りました。
以上のように遣唐使は文化的資源や仏教以外の学問も日本に持ち帰っている実績があります。経典や歴史書、医学書など中国から持ち帰ったさまざまな書物の中に三国志が紛れている可能性がないとは言い切ることができません。残念ながら具体的な人物名までは解明できていませんが、少なくとも遣唐使のうちの誰かではないか?というところまでは結論づけられています。
読み物としての三国志である三国志演義の場合は?
■ 読み物としての三国志である三国志演義の場合は?
読み物としての三国志である三国志演義の場合は?
歴史書としての三国志は西暦200年代後期に陳寿によって書かれ、約500年後の奈良時代以前には日本に持ち込まれていたと考えられています。それでは羅貫中の書いた読み物としての三国志である三国志演義の場合はいつ頃なのでしょうか?
まず羅貫中がどの年代の人物であるのかそこから説明しましょう。羅貫中は元末明初の時代を生きた作家です。元は元寇の元であり、そのころの日本は鎌倉時代であり執権政治が行われていた時代に相当します。鎌倉時代の日本社会はまさに武家社会。貴族や皇族よりも武士たちが大きな権力を持ち、人々を支配していました。
武士による武士のための法律や武士とは何か、武士道とはどのようなものかそれらが確立されたのも鎌倉時代です。三国志は武士たちの心を鷲掴みにし、鎌倉時代には既に武士のバイブルとして武家が学習しなければならない学問へとなりました。
太平記には三国志演義からパクってる記述が?
■ 太平記には三国志演義からパクってる記述が?
太平記には三国志演義からパクってる記述が?
源平合戦の一部始終を源氏サイドから見て描く太平記には、作者は絶対三国志演義を読んでいると裏付けられる記述が点在します。
まず、源頼朝、義経兄弟の長兄である悪源太こと源義平が平勢の捕虜となり処刑される直前、三国志演義の一説を語って斬首されます。
そしてこれはもう完全にパクっているだろうと疑惑が上がるのが、武蔵坊弁慶の立ち往生です。なぜなら、張繍の邸宅にて曹操(孟徳)が暗殺されようとしたときに、親衛隊長を務めていた悪来の異名をとる典韋が曹操(孟徳)の命を守らんとその身を盾に目をカッと見開き何百本もの矢をその身に受けながらも立ち続けて命を散らした名シーン。武蔵坊弁慶は源義経をお堂で切腹させんがため、トレードマークの大薙刀を手にお堂の扉の前に立ち、何百本もの矢をその身に受けて立ったまま最期を迎えたシーン。どちらも巨漢が立ったまま、主のためにその身を盾にして絶命しています。
源義平は源氏の棟梁の長男なので三国志を学習していたので、太平記の作者がその描写を加えたのか、あるいは源義平が本当に言ったのか定かではありません。しかし、武蔵坊弁慶の立ち往生の場合は太平記の作者が羅貫中の書いた三国志演義の描写に感銘を受けて加えた脚色であることは間違いないでしょう。
実際、源義経について最も詳しく書かれていると言われている義経記には武蔵坊弁慶が立ち往生をしたという記述は見られません。もし、それが本当なら太平記と義経記、吾妻鏡にもそのことが書かれてしかるべきなのではないでしょうか?
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志がいつどのようにして日本に持ち込まれたのか、それらを厳密に証明する記述はありません。しかし、時代背景や古事記などの史料から奈良時代以前にはすでに正史三国志は日本へ入ってきていたと考えられています。また、正史三国志を日本に持ち込んだのは遣唐使であると考えられており、三国志演義の場合は太平記などに引用している記述がみられることから、鎌倉時代中期から室町時代初期にかけての間に入ってきたものと考えられています。