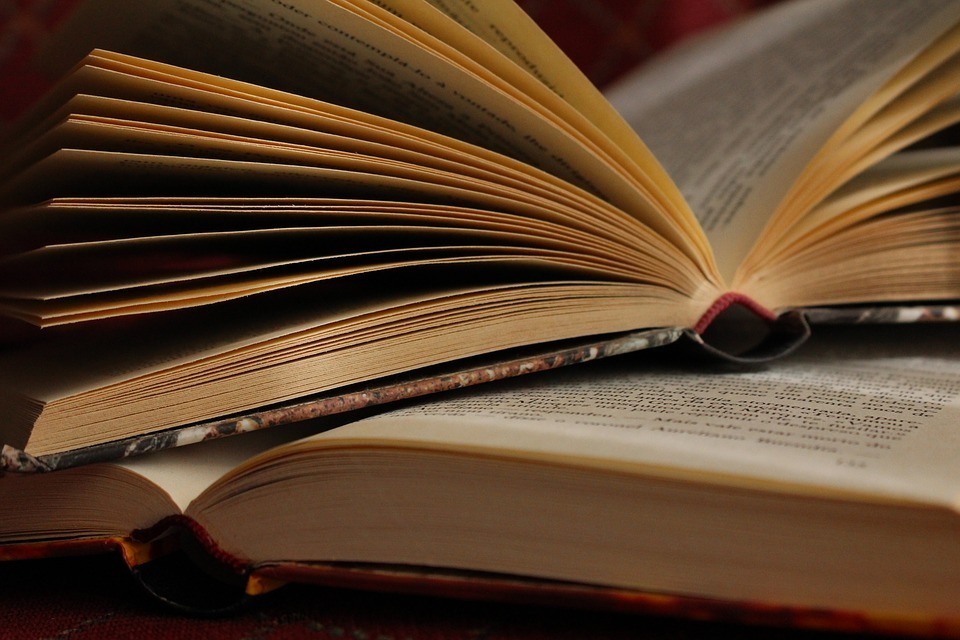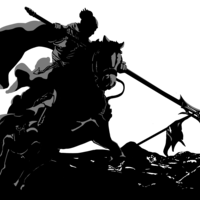三国志正史に描かれる陶謙
■ 三国志正史に描かれる陶謙
三国志正史に描かれる陶謙
配下が曹操の父親を殺したことにより、曹操から攻められ、数十万の住民が虐殺されることになる徐州牧の陶謙。
「三国志演義」では、徐州の民のために徐州牧の座を劉備に譲って病没した設定になっています。そのため陶謙には、徳の高い君主というイメージが強くあります。善か悪かで判断すると、断然「善キャラ」なのが陶謙なのです。
しかし「三国志正史」によると、印象が違います。
黄巾の残党を鎮圧するために徐州の刺史に命じられた陶謙は、見事にその役目をまっとうするのですが、鎮圧後の治政では正常な法律・刑罰を行わなかったというのです。
さらに天子を自称する闕宣と結託し、略奪行為を働き、成果が出た後には闕宣を討ってその軍勢を吸収しました。
反董卓連合にも参加せず、日和見を続けています。その裏で朝廷に貢ぎ物を送り、感謝されて徐州牧に昇進しました。
一筋縄ではいかぬ、かなり腹黒い奸雄といった感じです。三国志演義とはまるで描かれ方が異なるのです。
陶謙が同盟を結んでいた相手
■ 陶謙が同盟を結んでいた相手
陶謙が同盟を結んでいた相手
そんな陶謙が同盟を結んでいた相手が、北の雄・公孫瓚と四世三公の名声を誇る袁術でした。敵対勢力は、袁術と袁氏の家督を巡って対立し、さらに河北の覇者の座を公孫瓚と争った袁紹です。
さらに袁紹は、袁術・公孫瓚・陶謙の勢力に対抗するために荊州の劉表や兗州の曹操と結託します。
そんな中で、曹操の父親殺害事件が発生することになります。
193年、曹操は兗州から徐州へ侵攻。陶謙は徐州の入り口となる彭城で曹操を迎撃しましたが、大敗したと記されています。陶謙は徐州の中央に位置する郯県へ撤退し、籠城。曹操はそれを追撃しますが、郯県の城を落とすことはできませんでした。
曹操は南下して徐州南部の下邳や夏丘で大虐殺を行うことになります。そして兗州へと戻るのです。
陶謙への援軍
■ 陶謙への援軍
陶謙への援軍
ここまでの経過では、同盟軍の盟主・袁術からは援軍が駆けつけておらず、公孫瓚からわずかな援軍が来ただけです。
実はさかのぼること192年に公孫瓚は袁紹と激突し、「界橋の戦い」で敗れ、主力を失っていました。さらに袁術も193年に兗州の曹操を攻め、「匡亭の戦い」で大敗し、拠点だった南陽を捨て、揚州の九江郡まで逃走していたのです。
つまりまともな援軍を出せない状態だったわけです。曹操の徐州侵攻はその隙を突いていたことになります。
曹操は193年の1年の間に袁術を撃退し、次いで陶謙を攻めるという強行策を実行したことになりますが、当然のように兵站の問題も発生します。兵糧不足に陥った曹操は一度兗州に退いてから、再度準備を整えて、194年にまた徐州に侵攻しました。大虐殺を行った要因のひとつに兵糧の確保があったのでしょう。
劉備の登場
■ 劉備の登場
劉備の登場
劉備は公孫瓚の勢力下にあり、冀州平原国の相となっていました。
陶謙の援軍要請に対し、公孫瓚は劉備を青州の臨淄にいる田楷と合流させます。田楷もまた公孫瓚の勢力下にあり、青州刺史でした。さらに公孫瓚家臣の趙雲も騎兵を率いて劉備に協力しています。
一度目の曹操の侵攻に対し、劉備らが間に合ったのかどうか、どのような活躍をしたのか不明ですが、陶謙は劉備を厚遇して4,000人の兵を与えたと記されています。そして豫州刺史に推薦し、曹操の侵攻ルート上の豫州・小沛に駐屯させます。
しかし曹操は二度目の侵攻に際し、小沛を通過せず北から攻めるルートを選び、徐州北部で5つの県城を落とし、凄まじい勢いで郯県に押し寄せました。
そして郯県の東方で劉備の軍勢と衝突するのです。かなり軽めに流されがちな場面ですが、これが曹操と劉備の記念すべき最初の戦いということになるのです。
劉備には関羽・張飛・趙雲という一騎当千の猛将が揃っていたはずです。善戦はしたことでしょうが、曹操軍の猛攻の前にあえなく敗退。曹操はまたも住民を虐殺しながらさらに前進します。
陶謙はこの時、故郷である揚州の丹陽郡まで逃走しようと考えていたと伝わっています。
しかし、曹操の本拠地である兗州で張邈・陳宮らが呂布と共に反乱を起こし、曹操は急遽撤退することになるのです。
陶謙が病没する
■ 陶謙が病没する
陶謙が病没する
最大の危機から逃れることのできた陶謙は、心労がたたってか病で倒れます。問題は陶謙の後継者が誰になるのかということでした。陶謙には陶商と陶応という二人の息子がいましたが、州牧は世襲制だったわけでなく、さらに曹操に再び攻め込まれたらこの二人ではとても防ぎきれません。徐州はあっという間に飲み込まれてしまうことでしょう。
ここで、三国志演義では陶謙が劉備に直接徐州を譲ろうとしています。
三国志正史にはそのような遺言を家臣の麋竺に託したと記されています。
どちらにせよ劉備は一度拒否しますが、徐州の名士である陳登や北海国の相で孔子の末裔である孔融に説得されて、ようやく劉備は受け入れるのです。
蜀書には「劉備にあらざれば、この州を安んずる能わず」という陶謙の遺言が記されています。二人の息子の将来を考えると、劉備に守ってもらうしか手がなかったということなのかもしれません。
まとめ・袁術の謎の行動には理由があった
■ まとめ・袁術の謎の行動には理由があった
まとめ・袁術の謎の行動には理由があった
こうして徐州を拠点にした劉備でしたが、196年にはその支配権を失います。直接的な原因は。流浪していた呂布に留守にした下邳を奪われたからなのですが、発端は寿春を拠点にした袁術が徐州に侵攻してきたことにあります。
袁術は公孫瓚や陶謙の同盟相手で、曹操という共通の敵がいました。それがなぜ、陶謙の後継者である劉備の領土を攻めたのでしょうか?
これには理由がありました。
豫州はもともと袁術の支配下にあり、かつては袁術が孫堅を豫州刺史に任じたことがあったほどです。そこに陶謙の勢力が少しずつ入り込んでいったのです。陶謙が劉備を豫州刺史に推挙し小沛に駐留した時点で、陶謙と袁術の関係はこじれていたわけです。陶謙の離反行為ともいえます。
恨まれていることを知っていた劉備は、袁術の侵攻を恐れ、公孫瓚と手を切って、袁紹と結びました。つまり、ここで袁紹・曹操・劉備の同盟関係が成立したことになります。劉備がその後、呂布に追われて曹操を頼り、さらに曹操に追われて袁紹を頼って落ち延びていくのはこういった理由があったのです。