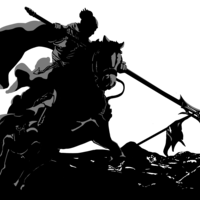蜀を建国して初代皇帝となる
■ 蜀を建国して初代皇帝となる
蜀を建国して初代皇帝となる
関羽が死んでしまった後、一大勢力を築いた魏の曹操が病で亡くなります。次いで呉の呂蒙も病死し、関羽の呪いではないかとも後世では伝えられています。君主の曹操や都督の呂蒙といった、実際に戦地に赴いて戦っていた指揮官が亡くなった両陣営は、すぐに出兵することがままなりませんでした。
諸葛亮は劉備(玄徳)に早く立ち直ってもらい、人心を安定させたい狙いがありました。その矢先、曹操の後継者になった曹丕が後漢の献帝から禅譲されて、魏を建国し、初代皇帝となりました。後漢の復興を目指していた劉備(玄徳)たちにとって、想定外のことだったといえます。
魏を倒し、漢王朝を復権するためには、皇帝の血脈を持った劉備(玄徳)しかいないと群臣たちが騒ぎ始めると、諸葛亮は蜀を建国し、劉備(玄徳)が初代皇帝として魏に対抗する案を練ります。
劉備(玄徳)は自分が皇帝になることを拒みますが、このままだと漢王朝のために挙兵した意味も無くなり、それを夢見て劉備(玄徳)に命を預けたや配下たちがいたたまれないと諸葛亮に諭され、建国することを決定しました。
張飛の死と呉への遠征を決定
■ 張飛の死と呉への遠征を決定
張飛の死と呉への遠征を決定
劉備(玄徳)や関羽とともに挙兵した張飛は、劉備(玄徳)の晴れ姿を見て恐らくは泣き崩れたことでしょう。張飛は劉備(玄徳)と謁見し、関羽の弔い合戦として呉への遠征を固く誓い合いました。もともと張飛は部下を叱咤激励するとき、暴力も使い、ときに恨まれることもありました。
また、暴力をふるってきつく叱った部下を降格させることなく、自分の側近として信頼を置いてもいました。当然ながら、今度は殺されるかもしれないと恐怖におののく部下もおり、関羽が死んだことで、精神的に不安定になっていた張飛は、部下に八つ当たりもしていました。
そんな中、張飛の部下である張達らが反逆を起し、寝ている張飛を殺害しています。普通に暗殺するのは張飛相手に成功しないでしょうから、恐らくは酒を呑ませて寝込みを襲ったと思われます。しかも、張達らはその首を持って呉へと逃亡してしまいます。
劉備(玄徳)は張飛の使いが訪れた時、自然と「ああ、飛(張飛)が死んだ」と悟ったといいます。張飛を殺害した張達らが呉へと降ったことで、孫権の仕業と考えるようになってしまいました。とても蜀と呉の共同関係を維持するのは難しく、関羽の弔い合戦として、大規模な呉への遠征を計画した劉備(玄徳)ですが、今度は張飛も弔う意味でも、この戦いにかける意気込みは凄まじい思いが募っていきます。
諸葛亮は呉と戦うのは妥当ではなく、あくまでも呉と連携して魏に立ち向かうべきであると説得を試みます。しかし、劉備(玄徳)の思いは変わらず、諸葛亮は仕方なく説得を諦め、自分は蜀に残って国力を安定するように注力しています。
夷陵の戦いへ
■ 夷陵の戦いへ
夷陵の戦いへ
劉備(玄徳)は221年、呉への報復として遠征を開始します。蜀入りに貢献した策士の法正やホウ統はすでに亡く、本来ならば諸葛亮を帯同させたいところでした。しかし、益州を手に入れたばかりで、国政を怠ることはできず、蜀の要といえる劉備(玄徳)と諸葛亮はどちらかが残る必要があったのです。
怒りに任せて行動を起こしている劉備(玄徳)に対し、諸葛亮はこの戦いで恐らく勝てないだろうと推測しています。その心情を察してか、古参の一人である趙雲が劉備(玄徳)に遠征を中止するように諭します。
劉備(玄徳)は今更引き下がれないとして却下し、趙雲を江州に残しています。これは国境を接する魏への備えと、自分が呉に敗れた際、万が一の抑えとして、独自に判断して救援に動ける適任者を趙雲だと決めていたからです。
快進撃を続ける
■ 快進撃を続ける
快進撃を続ける
呉は劉備(玄徳)への備えとして、大都督に関羽討伐で功績があった陸遜を抜擢します。陸遜は呂蒙や魯粛に比べると、まだまだ諸将の信頼は皆無に等しいといえました。劉備(玄徳)は呉の総大将が陸遜であると聞き、まだ配下の信頼はおけてないことを想定して、遠征軍の速度を速めて呉の領地を攻撃し始めます。
支城を撃破された陸遜は、劉備(玄徳)軍と戦いますが、連携がとれずに敗北を喫します。勢いにのる劉備(玄徳)軍は、呉の領地の奥深くまで侵入し、長江の夷陵にまでたどり着きます。劉備(玄徳)配下の黄権はあまりに進み過ぎてむしろ棄権な状態だと進言し、自身が兵を率いるので、劉備(玄徳)は後から付いてきて欲しいと懇願します。
しかし、劉備(玄徳)は呉への復讐が頭をよぎり、黄権の意見を却下しました。長江の北岸へ黄権を派遣し、自分はそのまま長江を渡り切って呉軍と対決しています。
陸遜の火計で惨敗
■ 陸遜の火計で惨敗
陸遜の火計で惨敗
夷陵まで侵入されたら、もう後がない陸遜は再度劉備(玄徳)軍の陣営に攻め込みます。しかし、劉備(玄徳)の勢いは止められず、陸遜は退却を余儀なくされます。このとき、陸遜は劉備(玄徳)の陣地が火計に弱い布陣であることを見抜きます。
陸遜は夜襲で総攻撃を開始し、一斉攻撃で混乱させて劉備(玄徳)軍の陣地を焼き払います。陣が近くにあるので、一気に燃え広がり、劉備(玄徳)軍はさらに混乱を極めていきました。
劉備(玄徳)は退却を始めますが、すでに陸遜は退路を断っており、劉備(玄徳)が通るであろう道を塞いでいました。多くの武将が討ち死にし、北に構えていた黄権は呉軍と火に挟まれて行き場を失い、仕方なく魏へと降伏しています。劉備(玄徳)軍は総崩れとなってしまい、数万規模の死者を出してしまいました。
劉備(玄徳)の最期
■ 劉備(玄徳)の最期
劉備(玄徳)の最期
その頃、異変に気付いた趙雲が早馬で駆付け、劉備(玄徳)はかろうじて助かりました。白帝城に逃げ込んだ劉備(玄徳)でしたが、すでに戦意は喪失しており、夷陵の戦いでの惨敗と関羽や張飛の弔いができなかったことを悔やみ、とうとう病に倒れます。劉備(玄徳)は自分の死期を悟り、この地を永安と名付けました。
劉備(玄徳)は223年、諸葛亮と自身の子どもを呼び出し、これからは諸葛亮を自分たちの父であると思うようにしなさいと言い聞かせます。また、劉備(玄徳)は諸葛亮にこれまでもことを感謝し、今後のことを一切託しました。特に、嫡男の劉禅が皇帝の器でない場合は、諸葛亮自身が君主となって蜀を治めてほしいと願います。劉備(玄徳)はそれだけ言い残すと、静かに息を引き取ったといいます。
これほどまでに信頼されていることに感激した諸葛亮は、劉備(玄徳)が自分を取り立ててくれたことに感謝し、劉禅を補佐し、自分はあくまでも臣下の礼を取り続けていくことを誓いました。
三国志の主人公的存在になっている劉備(玄徳)は、時に流浪の身となり、ライバルとして描かれている曹操よりも精力的に劣り、多くの戦いで負け続けていました。しかし、劉備(玄徳)は人格に優れ、人望を集めており、その魅力に優秀な人材が結集することとなって、益州を手に入れることが可能になったといえます。