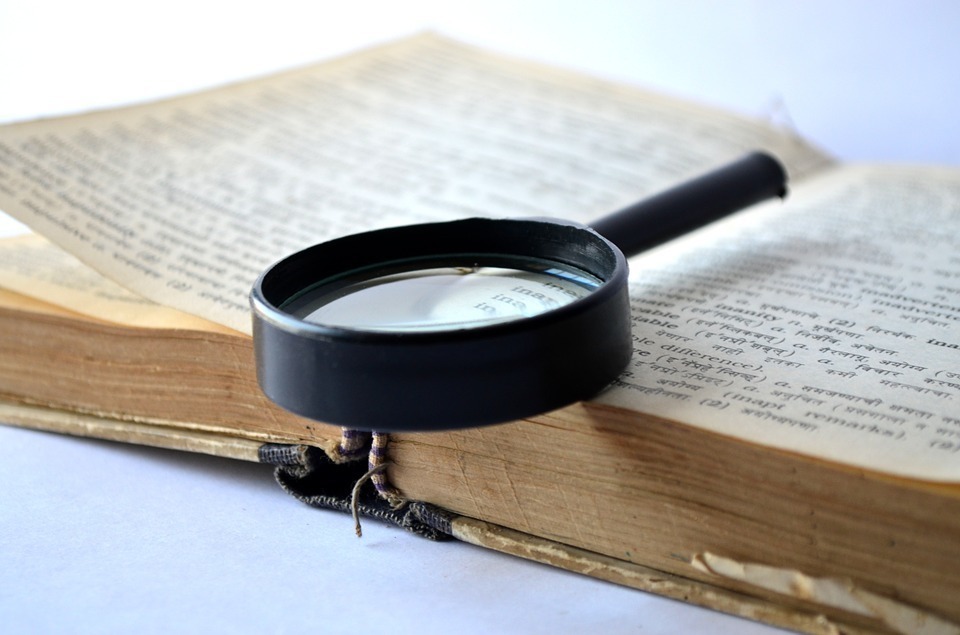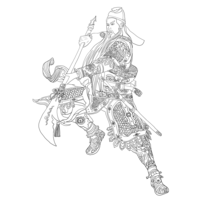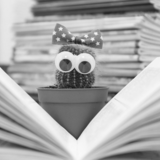関羽--関勝
■ 関羽--関勝
関羽--関勝
天勇星・大刀関勝はなんと関羽の子孫という設定で水滸伝に登場します。大刀というあだ名から想像できるように、青龍偃月刀の使い手で、そこも関羽と同じです。また、関羽同様、髭も見事に蓄えていました。役職も同じで五虎大将軍の筆頭となります。
ところが、この設定には実は大きな問題があります。実は、関羽の子孫は蜀漢が滅亡した際に、皆殺しにされているのです。関羽に処刑された魏の武将である龐徳の息子龐会の手によってです。演義では堂々と渡り合って、最後は潔く処刑されたように書かれていましたが、家族は関羽のことを心底恨んでいたのですね(当たり前といえば当たり前ですが)。
関羽みたいに一つの州(荊州)のトップともなれば、愛人や妾もいたでしょうし、庶子も多くいたかもしれません。ですが、関羽の正統な子孫と呼べる人物は水滸伝の時代にいたはずはないのです。
関羽--朱仝
■ 関羽--朱仝
関羽--朱仝
天満星・美髯公朱仝は美髯公というあだ名からわかるように、関羽を意識して作られた登場人物です。見事な髭と義に厚い性格という、関羽からとった設定を伺うことが出来ます。
関羽の髭はよほど見事なものだったのでしょう。正史に残されている話では、馬超が劉備軍に降ってきた時に関羽が諸葛亮に
「馬超とはどんな人物か?」
と尋ねました。それに対する諸葛亮の回答が
「馬超は張飛の相手にちょうど良く、ひげ殿には及ばない」
だったそうです。ひげ殿で通じるくらいですから、周りの人も皆関羽のひげのことを知っていたのでしょうし、本人も「ひげ殿」と呼ばれることにまんざらでもなかったようです。
演義では、関羽が曹操に降伏した際、献帝にお目通りします。その時に献帝が関羽のひげを見て
「まさしく美髯公だのう」
と言います。美髯公というあだ名はここから来ています。
張飛--林冲
■ 張飛--林冲
張飛--林冲
天雄星・豹子頭林冲は日本で一番人気のある水滸伝の登場人物ではないでしょうか?彼の描写は「豹頭環眼燕頷虎鬚」となっております。意味は「豹のような頭、ギョロッとした眼、燕のような顎、虎ひげ」です。つまり、張飛が書かれている描写と全く同じです。そして、得物は蛇矛。明らかに張飛を意識して作られた登場人物です。ところが、何故か日本では林冲はイケメンで線が細く書かれることが多いです。イケメンで線の細い張飛が書かれていたらさぞかし読者はびっくりするでしょう。林冲がそのように書かれるのは「妻を悪役の息子に奪われそうになり、そのために悪質な計略にはまり、流刑にあう」という悲劇の主人公のような設定があるからでしょう。
妻とのエピソードという意味では張飛も負けてはいません。張飛の妻はなんと魏の夏侯淵の姪、夏侯覇の従姉妹です。敵国の重臣の一族なのですから、当然略奪です。林冲とは違い、張飛は妻を奪った側だったのです。夏侯氏は前漢が興った時の功臣である夏侯嬰の子孫(ということになっています)です。なので、当時では間違いなく名家です。劉備以外の士大夫を見下す癖のあった関羽と違い、張飛は士大夫に敬意をもって接していたとのことですので、さぞ喜んだことでしょう。
呂布--呂方
■ 呂布--呂方
呂布--呂方
地佐星・小温侯呂方は「温侯」という言葉が入っている通り、呂布を意識して作られた登場人物です。呂布の武勇に憧れて、彼の得物とされていた方天戟を学び使い手となります。呂布を意識して作られたにしては、あまり武勇で活躍するシーンはありません。
温侯というのは呂布が董卓を討った時に与えられた地位です。呂布を代表するあだ名のように使われています。小温侯という名称だけで呂布を意識させるくらい呂布に結びつく呼び方だったのでしょう。
呂布の武器として有名な方天画戟ですが、なんと三国志時代にはまだ実在しません。宋の時代には存在したようなので、呂方が実在していたら方天画戟を振り回すことが出来たかもしれません。ですが、呂布が方天画戟を振り回す姿は、タイムスリップが出来るようになったとしても、絶対に見ることが出来ないのです。
孫策--周通
■ 孫策--周通
孫策--周通
地空星・小覇王周通は孫策と同じく「小覇王」のあだ名を持っています。ですが、水滸伝の中では武芸が上手な方でもなく、ものすごく小物で、取り立てて功績を残さないまま、最後は戦死します。孫策ファンが水滸伝を読んで小覇王の活躍を期待していたらさぞかしがっかりするでしょう。
そもそも孫策が小覇王と呼ばれたのは、江東で領土を広げている時のことでした。敵軍の武将二人を、一人は大声で吠えて落馬させて殺し、もう一人は怪力の腕で締め上げて殺しました。その姿が楚の国の覇王「項羽」のようであったということで、小覇王というあだ名が孫策に付きました。項羽と孫策、二人の豪傑に由来するあだ名をもらった武将としてはあまりにも残念な周通です。
ちなみに、孫策が小覇王と呼ばれるのは演義での話です。正史には「小覇王」のあだ名は出てきません。小覇王孫策の称号が好きなファンの方には残念なお話です。
関索--楊雄
■ 関索--楊雄
関索--楊雄
天牢星・病関索楊雄のあだ名には見ての通り「関索」という言葉が入っています。頭についている「病」という文字は今とは意味が違うみたいで「黄色い」という意味です。決して楊雄が病気がちだったり身体が弱かったという意味ではないです。
何故、関索なのでしょうか?大人気の関羽の息子とは言え、三國志演義では大して活躍しておらず、なにより架空の人物です。実は、昔の中国では関索は「花関索伝」という、今で言うスピンアウト小説が出来てしまうくらい民衆の間では人気でした。武勇に優れた色男で登場します。そんな人気の関索にゆかりのある人物を水滸伝にも登場させたい、そういう願いが反映されたのでしょう。
張遼--張文遠
■ 張遼--張文遠
張遼--張文遠
張文遠は魏の名将「張遼文遠」を当時の中国での一般的な呼び方である、名を省略して姓と字で呼んだ「張文遠」と同じです。彼は一言で言えば間男です。水滸伝の主役である宋江が世話していた女性と密通していました。そして、その女性が成り行き上、宋江に殺されると宋江の逮捕をしつこく知事に訴えます。三国志演義で三本の指にも入るであろう名将の張遼も、自分にゆかりある名前をもつキャラクターがこんな情けないやつだと知ったらどう思うでしょうか?
おまけ--張横--張横
■ おまけ--張横--張横
おまけ--張横--張横
天竟星・船火児張横は三国志演義に登場する張横と全く同じ姓名です。
しかし、三国志演義での張横は涼州の出身なので、馬に乗って陸戦のスペシャリスト、かたや水滸伝の張横は船頭さんで水の中での達人です。同じ姓名ですが、設定も全く違い、おそらく作者も全く意識していなかったのでしょう。何百人も登場する小説二つを比べてみるとこんなこともあるのですね。
他にも調べてみればまだまだ三国志演義と水滸伝には共通点や関連点たくさんありそうです。興味がある方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか?