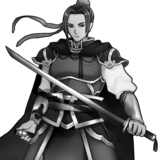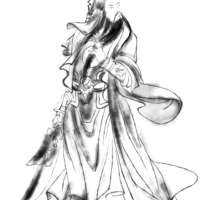蜀の名君である劉備玄徳の最期
■ 蜀の名君である劉備玄徳の最期
蜀の名君である劉備玄徳の最期
義兄弟である関羽雲長や張飛翼徳という弟たちを次々と亡くした劉備玄徳は、関羽雲長の仇討ちのために夷陵の戦いにて呉に戦いを挑みます。この頃の蜀の勢いは二人を失った悲しみからかすさまじく、連戦に次ぐ連戦で荊州を奪取するかどうかの瀬戸際まで駒を進めます。
しかし、呉の陸遜伯言の火計によって数万人の兵を失うといった大敗を喫したがために戦況は大きく劣勢となりました。この戦によって失ったものは大きく、その疲れもあったのか劉備玄徳は病に倒れてしまいます。最期は後のことを諸葛亮孔明に託しこの世を去ったのでした。二人の弟を亡くし仇討ちを果たせず死んでいった名君の最期は失意のどん底だったと言われています。
この劉備玄徳の最期だけを見ても物語にするにはドラマチックなので蜀人気が高い理由がわかります。しかし、病に倒れなかったのならば仇討ちを果たしてほしかったと思うのは私だけでしょうか。劉備玄徳の気持ちを考えると悔しくてたまりません。
三国志の風雲児と言われた曹操孟徳の最期
■ 三国志の風雲児と言われた曹操孟徳の最期
三国志の風雲児と言われた曹操孟徳の最期
三国志の風雲児と呼ばれた事実上の三国志の覇者である曹操孟徳ですが、その最期は謎の頭痛に悩まされて亡くなりました。この頃は謎の片頭痛として片付けられていますが恐らく実際は脳腫瘍だとかそういう関連の病気だったのではないかと考えられています。
三国志演義などの影響もあり、曹操孟徳は晩年に関羽雲長の亡霊に悩まされたというエピソードが広まっていますが、実際のところ曹操孟徳を関羽雲長が恨む理由などないというのが正解でしょう。というのも確かに関羽雲長が亡くなったあと、その首を保管したのは曹操孟徳ですが、首を取ったのは呉であるので呉に亡霊として現れるべきだと考えられるのです。
病にかかった曹操孟徳は自分が亡くなった後のことを考えて周囲のものたちを呼び寄せて遺言を書きました。死後の整理を生きているうちにやっておくことは必要不可欠だとわかっていた立派な人間だということがここからは読み取れますね。風雲児とはいえ、常識がなっているからあれだけ多くの人間が曹操孟徳を慕ったのでしょう。病に倒れてしまうとは本当に残念です。
勢いがありすぎたが故にあっけない最期を迎える孫堅
■ 勢いがありすぎたが故にあっけない最期を迎える孫堅
勢いがありすぎたが故にあっけない最期を迎える孫堅
孫堅といえば三国志前半を語る上では欠かせない重要な人物ですが、その最期は本当にあっけないものでした。ここでは、その孫堅のあっけない最期について語っていきます。
捕らわれた帝を董卓から取り戻すために集結した反董卓連合軍は帝を取り戻して褒美をもらうことを考えていたのにかなわなかったためにモチベーションが落ちていました。そんな中、洛陽に一番乗りをした孫堅は焼け落ちた王宮の中で伝国の玉璽を見つけました。本来ならば、皇帝に返さなければならないのですが、孫堅は手放したくなかったので報告せずに自分のもとにおいてしまいました。
このまま事が済めば良かったのですが、連合軍のリーダーである袁紹に告げ口をするものがいました。袁紹も伝国の玉璽が欲しかったので孫堅に自分が皇帝に返すからといって巻き上げる算段でしたが、それを見破ってか孫堅は伝国の玉璽など知らないと無視してしまいます。
おさまりの利かない袁紹はどうしても伝国の玉璽が欲しかったので劉表に命じて孫堅を殺してしまおうと企てます。仲間内でのもめ事についには反董卓連合軍は袁紹に愛想をつかしてバラバラになってしまいます。これが引き金となって中国は戦国時代に突入しました。
孫堅は伝国の玉璽欲しさに自分の命を狙った袁紹に対して怒りの感情を抑えきれなくなります。その最中、かつての上司であった袁術から袁紹が自分の領土である江東を狙っているということを聞かされます。それならばやられる前にやってやろうと袁紹の味方をした劉表を攻めます。
ここから破竹の勢いで劉表軍の本拠地襄陽を包囲するまでとなりますが、劉表軍の軍師の策にハマってしまいます。援軍を求めて抜け出した呂公を欲をかいて孫堅は追撃しようとしたのですが、このことが原因で空から降ってくる無数の矢によって命をおとしてしまったのです。
怒りと自身の強さにおぼれてしまった孫堅はたった一度の判断のミスであっけなく命をおとしてしまうという最期を迎えたのです。こうしてみると桶狭間の戦いで織田信長に敗れてしまった今川義元をなんとなく思い出してしまいます。これが彼の運命だったのでしょうか。
誰もが知るお馴染みの董卓の最期
■ 誰もが知るお馴染みの董卓の最期
誰もが知るお馴染みの董卓の最期
董卓の最期と言えばお馴染みですね。義理の息子という立ち位置の呂布奉先に裏切られてぶった切られることでその生涯を終えます。当然ながら権力に溺れてふてぶてしい態度をとっていたので当然といえば当然ですが、大きな原因になったのは貂蝉を呂布に嫁がせるフリをして自分が貂蝉を可愛がっているという部分に腹を立てたのが対立のはじまりでした。
その事を貂蝉の父である王允に伝えると董卓を討つように呂布は煽られました。筋は通ってるとはいえ、前にも父殺しをしている呂布はさすがに世間体を気にして一度は拒みますが説得されて董卓を討つことにしたのです。裏切者と思われがちな呂布ですが、父に恵まれなかったが故に起こしてしまった悲劇でした。
董卓も天下を手中に収められるかどうかとなったときに、調子に乗らずに良い父親になれれば息子の呂布奉先にこんな悲しい決断をさせずに済みましたし、もう少し長生きできたかもしれませんね。世の父親は董卓を反面教師にしてもらいたいものです。
まとめ
■ まとめ
まとめ
国のリーダー、主君、名君とはいえ死に方は実際問題選べないということは今回わかりました。志半ばで病気に倒れるものやたった一度の失敗によって命を落とすもの、どんな理由はあろうとも味方からの裏切りを受けるものと本当にその死に方は様々ですね。
あなたは一体どんな死に方をしたいですか?今回出てきたような死に方は避けたいですよね。できれば、寿命を全うして眠るように亡くなるのが幸せだと感じます。しかし、この時代に立場のある人間というのはそういった死に方が許されなかったというのが本当のところなのかもしれません。最期まで読んでくださってありがとうございました。