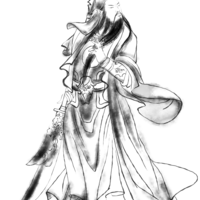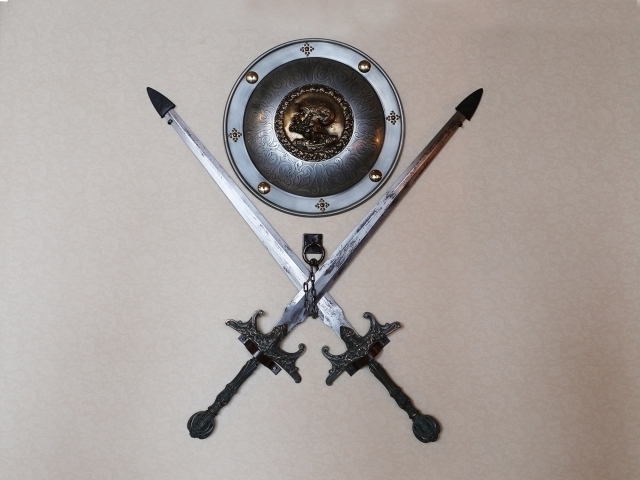劉備(玄徳)の妻子を守るために曹操軍に投降 そして曹操(孟徳)の厚遇
■ 劉備(玄徳)の妻子を守るために曹操軍に投降 そして曹操(孟徳)の厚遇
劉備(玄徳)の妻子を守るために曹操軍に投降 そして曹操(孟徳)の厚遇
決定的不利な状況に追い込まれた関羽(雲長)。劉備(玄徳)の妻子の守備を任されていたため、討ち死にを思い留まり曹操軍に投降します。また、投降を許されたのは曹操(孟徳)が関羽(雲長)を召し抱えたいという強い意欲を持っていたからです。
曹操(孟徳)は関羽(雲長)の武勇だけではなく、主君劉備(玄徳)への一途な忠誠心に一目も二目も置いており、「彼(関羽)のような武将から慕われるような主君になりたい」「自ら(曹操)の義によって彼(関羽)を従わせてみせる」と考えていました。
そして、関羽(雲長)投降後は、酒宴でもてなし、恩賞を与え、漢の偏将軍に任命するなどこの上ない厚遇を続けます。しかし、関羽(雲長)の心は動きません。自らへの厚遇のみならず「宿敵劉備」の妻子に対しても十分な待遇をしてくれている曹操(孟徳)に対して恩義は感じているものの、翻って二君に使える気持ちは起きないのです。この葛藤に関羽(雲長)は苦しみます。
時は官途の戦い 三国志前半の山場となる一大決戦の最中
■ 時は官途の戦い 三国志前半の山場となる一大決戦の最中
時は官途の戦い 三国志前半の山場となる一大決戦の最中
この頃、当時の大勢力であった河北の袁紹(本初)と曹操(孟徳)とが決戦していました。「官途の戦い」です。その後の中国の情勢に決定的な影響を及ぼす重要な戦いでした(曹操が勝利)。なので、当時袁紹(本初)も曹操(孟徳)もはっきり言って関羽(雲長)、劉備(玄徳)どころではありませんでした。
様々な思惑の下に、劉備(玄徳)も関羽(雲長)も官途の戦いに関わることとなるのですが、このことがふたりを再会に導きます。
戦場で劉備(玄徳)が関羽(雲長)を見つけ出し「自分(劉備)は河北にいる」と密偵を使って関羽(雲長)に伝えます。三国志前半の山場となる一大決戦が劉備(玄徳)と関羽(雲長)にはプラスに働いたのです。
関羽の千里行 曹操支配下の5つの関所を強行突破
■ 関羽の千里行 曹操支配下の5つの関所を強行突破
関羽の千里行 曹操支配下の5つの関所を強行突破
関羽(雲長)は劉備(玄徳)のいる河北に行くことを決意します。そして、今までの恩義にしっかりと報いるために官途の戦いに参戦し、敵将顔良を討ち取り、それまでやや不利だった曹操側の戦局をひっくり返してしまいます。
ただ、一説には顔良は劉備(玄徳)に頼まれ、劉備(玄徳)の所在を伝えるために戦場で関羽(雲長)に近づいたとも言われています。猛将と言われた顔良が関羽に(雲長)にあっさり討ち取られてしまった原因は、元より戦う気がなかったのでは…という説もあるのです。
劉備(玄徳)の生存が判明し、戦場にて大功を立てたことで恩義にも報われた形となった曹操(孟徳)。あの手この手を使って引留めようとしますが、関羽の気持ちは変わりません。最後は曹操(孟徳)から関羽(雲長)にエールを送るような真義の別れとなります。
ところが、関羽(雲長)は関所の通行証を持っていませんでした。現代で言えば「トップの声、現場に届かず」といったところですね。そのために関羽(雲長)は曹操領内の関所でことごとくトラブルとなり、やむなく東嶺関、洛陽、沂水関、滎陽、黄河の5つの関所を強行突破します。
この報を聞いた曹操(孟徳)は怒り狂うどころか「私(曹操)の配慮が足らなかった」と反省して関羽(雲長)の行動を許してしまいます。このあたりからも、曹操(孟徳)が関羽(雲長)をどれほど敬愛していたのかが分かります。
関羽(雲長)に5つの関所を突破させた原動力は何だったのか
■ 関羽(雲長)に5つの関所を突破させた原動力は何だったのか
関羽(雲長)に5つの関所を突破させた原動力は何だったのか
関羽(雲長)の千里行、5関突破の原動力はもちろん劉備(玄徳)への忠誠心であったことは間違いありません。しかし、曹操(孟徳)も十分な人格者であることも間違いありません。関羽(雲長)が劉備(玄徳)に対して絶対的な忠誠心を抱いていたのはなぜでしょうか?
「桃園の義」によって劉備(玄徳)、関羽(雲長)、張飛(翼徳)が義兄弟となったのはあまりにも有名です。関羽(雲長)は劉備(玄徳)が旗揚げした時からの宿将です。物語の中でも本人が語っていますが「貧しい時代に生死を共にした仲」です。戦場で功を成し、大物(曹操)から声が掛かったところで、劉備(玄徳)の生死も不明なところで主君を変えること‥はできなかったのでしょう。
曹操(孟徳)は戦場を駆け巡る姿を見て関羽(雲長)を知る訳で、状況的に仕方のないことですが、曹操(孟徳)は恩賞、官位で待遇するしかありません。「貧しい時代から積み上げてきた思い出」には到底かなわないのかも知れませんね。
夷陵の戦い 関羽の死後 劉備(玄徳)も我を忘れて呉を攻める
■ 夷陵の戦い 関羽の死後 劉備(玄徳)も我を忘れて呉を攻める
夷陵の戦い 関羽の死後 劉備(玄徳)も我を忘れて呉を攻める
後年、関羽(雲長)は麦城にて呉軍に包囲されてその生涯を閉じますが、その報を聞いた劉備(玄徳)の悲しみと怒りは計り知れないものでした。その度合いは、70万の軍勢を起こして呉を攻めた(夷陵の戦い)ことからはっきりと伺えます。
当時、この戦いを諸葛亮(孔明)は反対していました。「いかに大軍で攻めようとも、弔い合戦として士気高揚を唱えても、時の大国「呉」が正陣を敷いているうちは勝つことはできない」というのが諸葛亮(孔明)の意見でした。
劉備(玄徳)も歴戦の強者。数々の戦場を生き抜いてきた人物です。そのくらいのことは十分承知だったでしょう。でも劉備(玄徳)は戦いを決行しました。戦いにおいて、決して行ってはならない「無理押し」であると薄々思いながらも…このあたりが劉備(玄徳)と関羽(雲長)の絆の深さを物語っていますね。
そして、この「夷陵の戦い」は劉備(玄徳)自身にも最後の戦いとなってしまいます。
呉軍は総大将陸遜(伯言)の指揮の下に籠城作戦を採ります。攻める気満々の蜀軍でしたが、身動きできず、夏の暑さを避けるために山間部に陣を移動しますが、長期戦となり乾季となったところを呉軍に狙われ、火計により万事休すとなります。
劉備(玄徳)は命からがら白帝城に逃げ込みますが、関羽(雲長)の敵討ちが達成できなかったこと、大軍を失い、蜀に多大な損害を出してしまったことへの心労から病に倒れ、そのまま命を落としてしまいます。