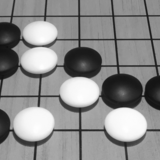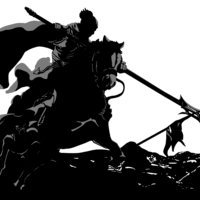『三國志』ってどんなゲーム?
■ 『三國志』ってどんなゲーム?
『三國志』ってどんなゲーム?
コーエーテクモゲームスの『三國志』シリーズ(真ん中の字が国ではなく國なのがポイントです)は、世に数ある三国志のゲームの中でも最も長く、そして重厚な歴史を持った作品です。
第一作目『三國志』は、1985年12月、当時の光栄からシミュレーションゲームとして発売されました。以来約32年、2017年の最新作『三國志13 with パワーアップキット』に至るまで十と三のナンバリングタイトルを数え、多くの外伝・スピンオフが製作され、そしてそれぞれが多くのハードウェアに移植され、膨大な作品群を形成しています。
簡単に概略を説明しますと、まずいくつか設定されている舞台の年代(たとえば董卓討伐の時代、あるいは三国鼎立が成立した後など)を選び、そして国を選んで、自らの率いる国の旗のもと、中国の統一を目指します。プレイヤーの自作によるオリジナル武将でのプレイ、あるいは国の君主ではなく一武将の立場でのプレイなどの要素も順次付け加えられていきました。
「三国志ブーム」の火付け役
■ 「三国志ブーム」の火付け役
「三国志ブーム」の火付け役
ところで、1985年ということは、三国志の漫画を代表する存在である横山光輝『三国志』全60巻が、まだ完結するよりも前に登場した、ということです。横山光輝による『三国志』の執筆は、1971年から1987年にかけてのことだからです。
「自らが演義や正史の武将となって、三国志の歴史の舞台に参加するゲーム」。今となってはそのようなことは当たり前と言えましょうが、1985年においてはそうではありません。光栄の歴史においても、1983年の『信長の野望』第1弾と並ぶ初期の傑作であり、多くの三国志ファンたちを虜にしました。
横山光輝で三国志を知り、光栄で三国志の世界にどっぷりとハマる。それが、当時起こった三国志ブームの、最も基本的な流れであったのです。まあ、それ以外のルートで三国志ファンになった方がおられなかったとは申しませんが、少なくとも筆者はその一人でした。
その黎明と興隆 『三國志』初代から第6作目まで
■ その黎明と興隆 『三國志』初代から第6作目まで
その黎明と興隆 『三國志』初代から第6作目まで
それでは、ナンバリングタイトルのシリーズを、発売順に見ていきましょう。前述のように1985年に発売された初代『三國志』は、基本のコマンドが20しかありませんでした。「1.移動」「2.戦争」といった具合です。内政フェイズと戦争フェイズ、外交、などの概念は既に存在していました。
『三國志Ⅱ』は1989年発売です。グラフィックスが大きく向上し、システムの面では、「1国につき1回のコマンド」だったものが、1ターンごとに「武将1人に対し1回の命令」になり、戦略性は大きく奥行きを増しました。また、オリジナル武将(この作品での呼称は“新君主”)という要素が初めて持ち込まれました。
『三國志Ⅲ』、1992年。コンシューマーゲームはスーパーファミコンの時代になっています。「国ごと」であったマップが、「都市ごと」に変更されました。ゲームとしての仕上がりはよくも悪くも複雑化し、Ⅲだけで消えた要素が結構あったりします。
『三國志Ⅳ』、1994年。Ⅲからうってかわってユーザーフレンドリーな設計が増え、同じ操作を何回も繰り返さなくてもオートでやってくれる、などの要素が組み込まれました。なお、「パワーアップキット」が登場するのはこのⅣからです。
『三國志Ⅴ』、1995年。武将1人につき1命令、という方式が撤廃され、「名声」の値によってコマンド入力回数が決まる、というシステムになりました。コマンドのオート化はさらに進み、ワンボタンですべての支配領域の内政コマンドを同時実行、などということもできるようになります。
『三國志Ⅵ』、1998年。三国志の登場人物たちに対するキャラクター性の掘り下げが進む、という新たな方向性からのアプローチが進むようになります。ただ、まだ過渡期的で、成功したとは言い兼ねるという意見も。
全武将プレイの導入、そして原点回帰……『三國志Ⅶ』から『三國志12』まで
■ 全武将プレイの導入、そして原点回帰……『三國志Ⅶ』から『三國志12』まで
全武将プレイの導入、そして原点回帰……『三國志Ⅶ』から『三國志12』まで
さて、『三國志Ⅶ』の発売は2000年、とうとうゼロ年代に入ります。ここから、シリーズの変遷の中でも最大級の変更が加わります。君主以外の武将でのプレイが可能になったのです。ちなみに、この方式自体は、やはり光栄の『太閤立志伝』(1992年~)で誕生したものでした。とはいえ、三國志での導入はまだやはり実験的な側面が強く、完成度に対する評価は賛否両論となりました。
『三國志Ⅷ』、2001年。Ⅶをより掘り下げたような作品で、システムは踏襲しつつ、シナリオ面の強化などが行われました。
『三國志Ⅸ』、2003年。Ⅶまでの路線から一端逸れ、Ⅵ当時の国家経営シミュレーションゲームに回帰します。なお、「政治マップ」と「戦争マップ」の区別がついに排除されました。
『三國志Ⅹ』、2004年。ⅦとⅧの路線に戻り、極めて自由度の高い全武将プレイを可能とするゲームに仕上げられました。
『三國志11』、2006年。表記が煩雑になりすぎるためかと思われますが、タイトルがアラビア数字表記になりました。ゲームシステムはまた国家経営シミュレーションゲームに戻ります。その分、戦略は複雑化し、歯ごたえのある作品となりました。
『三國志12』、2012年。間が6年も空いています。ちなみに11と12の間に社名がコーエーテクモホールディングスになりました。11が複雑すぎた反省か、一気に『三國志Ⅳ』にまで回帰し、お手軽サクサク感覚シミュレーションゲームとして世に送り出されました。
さて、次が最後、最新作のご紹介となります。
そして史上最大のパワーアップ『三國志13 with パワーアップキット』の登場
■ そして史上最大のパワーアップ『三國志13 with パワーアップキット』の登場
そして史上最大のパワーアップ『三國志13 with パワーアップキット』の登場
ナンバリングタイトル最新作『三國志13』は、2016年1月28日に発売されました。ちなみにWindows版、Play Station3版、Play Station4版、Xbox One版が全て同時発売でした。「史上最大のパワーアップ」と銘打ったパワーアップキットは2017年2月16日に発売されています。
用意されているシナリオ(時代設定)は6。シリーズの中には50を越えるシナリオが用意されていた作品もあったのですが、今回は手堅くまとめて184年「黄巾の乱」から214年「益州平定」までの6つとなっています。
システムは、Ⅹ以来となる「全武将プレイ」が採用されました。マップはフル3Dとなり、都市の内部までが造り込まれています。プレイアブルキャラクターはオリジナル版(通称バニラ)では700名、パワーアップキット版では800名にまで及びます。
それだけのキャラクターを選ぶことができ、また、ゲーム設計の自由度も高いので、やれることがとにかく多い、という仕上がりになりました。「天下統一を目指す」という基本コンセプトも、なくなったわけではありませんがプレイヤーを拘束しなくなり、その気になれば君主ではなく義勇軍の長になったり、賊の頭目になったり、暗殺者になったり、果ては商人として生きていくことさえできる仕様です。
まとめ (コーエー三国志 おすすめ)
■ まとめ (コーエー三国志 おすすめ)
まとめ (コーエー三国志 おすすめ)
以上、歴史の概略と13作品のご紹介でした。『三國志13 with パワーアップキット』が最新作だから一番おすすめ、というほど単純な話ではないとはいえ、「三国志の時代を自由に駆け抜けてみたい」という三国志ファンにとっては、まさに垂涎の仕上がりになっていると言えるでしょう。
ちなみに、過去の作品も遊びたい場合、一番手っ取り早いのは12までを完全収録した『「三國志」30周年記念歴代タイトル全集』を購入することですが、絶版な上に高価なのが難点です。
13のものはないようですが、12には体験版があります。とりあえず触れてみる程度なら、これが一番お手軽と言えるでしょう。