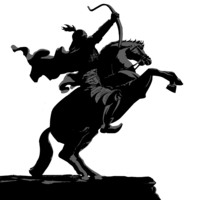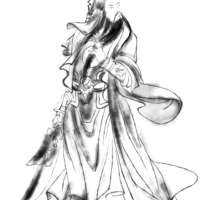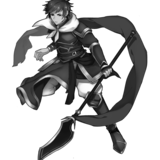諸葛亮に見出されたショウ周
■ 諸葛亮に見出されたショウ周
諸葛亮に見出されたショウ周
ショウ周(允南)は巴西郡出身で、幼いころに父を亡くして、一家は貧しい暮らしを強いられていました。それでもショウ周(允南)は少年時代から学問の才があり、成長していく中でもよく勉強したので蜀の丞相を務める諸葛亮(孔明)に見出されています。
皇帝だった劉禅(公嗣)に直接仕えており、ショウ周(允南)は評判も良かったといわれています。諸葛亮(孔明)が北伐中に死去すると、ショウ周(允南)は悲しみのあまり、急きょ駆け付けたといいます。蜀の圧倒的な中心人物だった諸葛亮(孔明)が死去したことにより、国内では意思を継いで北伐を再開するか、時期を待って国力を高めるかに意見が分かれていきました。
北伐再開を諌める
■ 北伐再開を諌める
北伐再開を諌める
ショウ周(允南)は諸葛亮(孔明)でもなし得なかった北伐に否定的であり、推進派の姜維(伯約)らが行動に出ると、国力の低下を心配して劉禅(公嗣)を諌めるように努めました。魏の強大さもあることから、ショウ周(允南)の忠告も功を奏して、しばらく北伐を行っていませんでした。しかし、蜀の四相といわれた諸葛亮(孔明)、蒋エン(公琰)、費イ(文偉)、董允(休昭)が相次いで亡くなると、北伐推進派の姜維(伯約)が諸葛亮(孔明)の意思を継いで北伐を再開してしまいます。
ショウ周(允南)は学問や教育という中では権力がありましたが、政治には参加せず、むしろ姜維(伯約)らからしたら、北伐反対派で劉禅(公嗣)に近い存在のショウ周(允南)は目の敵であり、遠ざけていたというほうが正しいかもしれません。
姜維(伯約)の北伐はたびたび行われましたが、どれも成果を挙げることができず失敗に終わり、ショウ周(允南)の杞憂した通り、蜀の国力は大きく低下していくことになります。
蜀が疲弊しているのを予想し、263年には魏の実権を握っていた司馬昭(子上)によって蜀への攻撃命令が下され、トウ艾(士載)や鍾会(士季)を中心とした大軍が攻めてきました。蜀と魏の戦力差を考慮して、ショウ周(允南)は真っ先に劉禅(公嗣)へ降伏を進言しています。蜀の土地は険しく、義軍の大軍では攻めるのも難しく、時期がくれば退却していくだろうと考えていた諸将らが抗戦を主張し、蜀軍は迎え撃ちます。しかし、名将であるトウ艾は蜀を翻弄する動きを見せ、敢えて過酷な道を切り進み、蜀の裏をかいて攻めたてます。
魏の進軍を受けて劉禅(公嗣)へ降服を勧める
■ 魏の進軍を受けて劉禅(公嗣)へ降服を勧める
魏の進軍を受けて劉禅(公嗣)へ降服を勧める
頼みの姜維(伯約)も敗れて孤立し、首都を守る戦力が乏しくなると、劉禅(公嗣)はショウ周(允南)の進言に従って降伏を決意します。ショウ周(允南)は無駄に血を流さない決断を取ったことを司馬昭に評価されています。
ショウ周(允南)の下へは羅憲(令則)や三国志を執筆した陳寿が師事を仰いでおり、その影響力は後世にも伝わることとなっていきます。ショウ周(允南)は予言をしていたこともあり、司馬昭(子上)の死や魏が滅んで新しい国家が誕生することを記しており、また宮中の大木が自然に折れてしまったことを受け、蜀が滅ぶのを悟ったともいれわれています。
劉備(玄徳)や諸葛亮(孔明)の意思を継いで漢王朝の復興をかかげるか、魏に対抗するべく国力を高めるか、歴史を後で見れば、どちらが正しかったかは一目瞭然であり、ショウ周(允南)の先を見る目が素晴らしいことを物語っていますね。
若き日から勉学に励んでいた羅憲
■ 若き日から勉学に励んでいた羅憲
若き日から勉学に励んでいた羅憲
羅憲(令則)の父は蜀の広漢太守を務めていました。それほど不遇な少年時代を過ごしていたわけではなく、羅憲(令則)は若くして勉強熱心で、大人たちの評判も良くて学問では名がしれた存在でした。羅憲(令則)は蜀でショウ周(允南)の下でさらに勉強に励でいます。
羅憲(令則)は規律正しく真面目に過ごし、才能のある人材には積極的に会いに行き、私服を肥やす悪徳役人のような真似は一切せずにおり、むしろ他人に財産を分け与えるなどして、周囲からの人望を集めていました。羅憲(令則)はその後、蜀に出仕して劉禅(公嗣)に仕えています。羅憲(令則)は同盟国である呉への使者として訪れることもあり、呉の人々からも喝采を浴びるほどの人望を得ていました。
黄皓の恨みを買ってしまう
■ 黄皓の恨みを買ってしまう
黄皓の恨みを買ってしまう
蜀の四相が目を光らせていた当時、劉禅(公嗣)の側近には宦官の黄皓が付いていました。劉禅(公嗣)のお気に入りだった黄皓は、費イ(文偉)や董允(休昭)が亡くなると次第に本性を現していき、自身に背く恐れのあるものを劉禅(公嗣)に諫言していきました。
羅憲(令則)は黄皓に対しても凛として臨み、恨みを買うようになってしまいます。羅憲(令則)は急な人事で巴東太守に左遷されてしまい、都から離れさせられてしまいました。
蜀の降伏後も民を守る
■ 蜀の降伏後も民を守る
蜀の降伏後も民を守る
魏軍が押しかけてくると、羅憲(令則)は永安城の指揮を執ることになります。しかし、首都では劉禅(公嗣)が降伏する事態に陥り、永安城でも大規模な擾動が起こってしまいます。役人らが城を見捨てていきますが、羅憲(令則)は毅然とした態度で叱りつけ、混乱を招く恐れのある発言をしたものを斬り捨てて治安を守っていきました。
同盟国の呉は、蜀の降伏を知ると、方向転換して攻め込んできます。荊州との窓口的位置にあった永安は、格好の餌食となり、呉軍に付け狙われます。蜀への援軍という名目で攻めてきますが、羅憲(令則)は城兵をまとめ上げ、魏に援軍を要請し、自ら率先して武具をまとい、城壁の修繕に繰り出します。
民を見捨てなかった羅憲
■ 民を見捨てなかった羅憲
民を見捨てなかった羅憲
呉は3万の兵で永安城を囲みますが、羅憲(令則)は半年間粘り込みました。城中には疫病が発生したこともあって、配下が羅憲(令則)に脱出して逃げるようにと伝えたれますが、民衆を見捨てることはできないと述べ、徹底抗戦を受けて立つ覚悟でいました。そんな中、魏の援軍が到着して呉軍を退却に追い込んでいきます。
司馬昭(子上)は羅憲(令則)の忠義に感激し、旧職をそのまま与えて評価しています。羅憲(令則)は多くの民衆に慕われていき、さらに昇進を重ねていきました。晩年には皇帝となった司馬炎から召集され、羅憲(令則)は陳寿を始め、多くの有能な家臣を推薦していき、全員が採用されています。