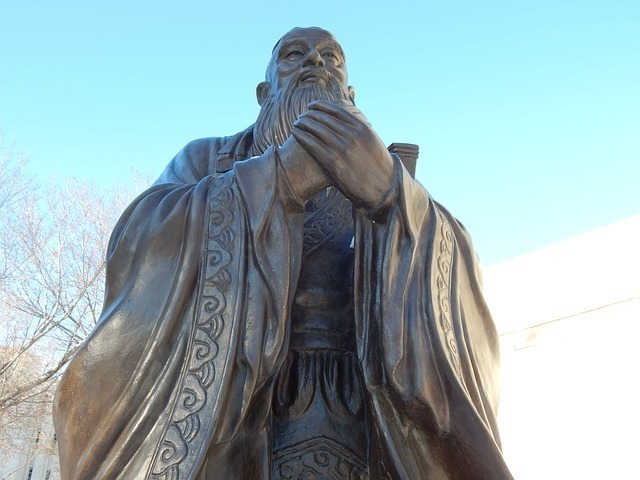三国志と大河ドラマで見る人々の服装
■ 三国志と大河ドラマで見る人々の服装
三国志と大河ドラマで見る人々の服装
三国志の登場人物と大河ドラマに登場する人物たちの服装をよく見ると、大きな違いがあることがわかります。国や文化の違いはもちろんのことですが、着こなしについて注目してもその差は歴然です。日本ではまだ麻で編んだ服と毛皮を着ていた当時、中国では宮中に参内するときの礼服、普段着として着用する服、戦闘服など目的や職業によって服装が定められていました。中国服装史が後世に伝える漢~三国時代の服装について、ご紹介します。
胡服(ごふく)
■ 胡服(ごふく)
胡服(ごふく)
胡服とは、中原の人々のゆったりとした服と異なり、北方の少数民族(匈奴など)がよく着用していたものです。一説には、もともとは内地の労働者の服の様式であると考えられています。胡服の特徴は、短い丈の上着に長いズボンと革靴履くか、または足巻をしてズボンの裾がかさばらないようになっています。袖口も小さく、動きやすさを重視した服装になっています。
胡人が着用していた服を漢人が着るようになったキッカケ
■ 胡人が着用していた服を漢人が着るようになったキッカケ
胡人が着用していた服を漢人が着るようになったキッカケ
かつて春秋戦国時代に趙国の六番目の君主・武霊王が趙の武器は胡人のものより優れているのに、士官も兵士も長袍を着用し、鎧がかさばって重そうにしており、加えて動作の素早い騎兵が少ないことに気がつきました。そのため、胡服を採用し、胡人が得意としていた騎射(馬に騎乗した状態で弓を射ること)を学ばせようと考えました。まさに、軍事的戦略における改革を行おうとしたのです。
武霊王は胡服と騎射を導入する際「今わしは胡服と馬上で弓を射ることをみんなに教えようと考えて
いるのだが、世間は必ずわしを非難するであろう。さて、どうしたらよいものか?」と臣下に事前に
相談しました。そこで肥義という者が「王はすでに世俗と異なることの非難を負われる決心をされたのですから、天下の誹謗中傷を顧みる必要はありません」と答えました。
そこで武霊王は「世にわしに従う者がいればあ、胡服の効用ははかり知ることができないほど大きいだろう。
世間が挙げてわしを笑いものにしても、胡の地と中山は、必ずわしのものになるであろう」と言って、胡服と騎射の導入を命令しました。
すると、やはり反対意見を述べる臣下が現れました。その臣下はこれまでの習わしなどを持ち出し、
武霊王を嗜めようとしましたが、武霊王はこの者を叱りました。
「先王とて風俗を同じくされたわけではない。どの古いしきたりに従えというのか。古の帝王も、べつに前代を踏襲していたわけではない。どの礼制に従えというのか」と。続けてこのように説得しました。「法度や制令はおのおのその宜しきに従い、衣服や器はおのおのその使用に便利であるようにするべきだ」と。この堂々とした説得に反対意見を発言できる臣下などいる訳もなく、趙では胡服と騎射の導入がなされたのですが、果たして趙国は急速に強大な軍事国家となり、それにつれて胡服の様式が漢民族の軍服に取り入れられるようになりました。
長袍(ちょうほう)
■ 長袍(ちょうほう)
長袍(ちょうほう)
三国志の幕が開ける漢の時代、男子は長袍という着物を貴びました。長袍は漢民族の服装の古い制度の中にあり、それは三皇五帝時代の帝舜の時世から存在していたそうです。また、『国語』という書物には、「袍は、すでに朝廷に参る時の服となった」という記述が残されています。秦の始皇帝在位中には、三品(当時の官吏の階級)以上の者は緑の袍か深衣を着用するようにと規定されていました。
庶民は白い袍で、素材は絹で作られていました。漢の治めた約四百年もの間、袍はずっと礼服とされてきました。その形は大袖がおおく、袖口は小さくすぼまり、それを「袪(そ)」と、袖全体のことを「袂(へい)」と呼びました。したがって、ゆったりした袖の服を着た人の服装のことを揶揄して
「袂を広げて日陰ができる」と言われるようになりました。
衿(えり)や袖口に菱形あるいは格子の文様を刺繍し、前むくみは斜めの衿(えり)にし、衿元(えりもと)を低く開け、その衿端から下着をのぞかせ、袍の裾に花文様で縁を作り、あるいは一行の細いひだを縫い取るか、三日月のような形に切って、さらに裾の形に合わせて曲裾袍(きょくきょほう)か直裾袍(ちょくきょほう)かを作り分けていました。
曲裾袍(きょくきょほう)
■ 曲裾袍(きょくきょほう)
曲裾袍(きょくきょほう)
春秋戦国時代の深衣の様式を引き継ぎ、前漢の初期にはほとんどの人々に着用されていました。後漢の頃になると、その流行も廃れてしまい、着用する者も少なくなりました。曲裾袍の特徴は、それを着たときに腰元から裾にかけて曲線を描くような衿になっています。裾が広い上着で、着こなしのイメージとしてはラッパをさかさまにしたような様子になります。その下にズボンをはき、動物の皮でできた長靴を履くのが通例でした。
直裾袍(ちょくきょほう)
■ 直裾袍(ちょくきょほう)
直裾袍(ちょくきょほう)
前漢期の頃に作られはじめ、後漢期に中国全土で流行しました。三国志に登場する人々が着ている着物がまさにこれです。
直裾袍が作られた当初は、正式な礼服にしてはなりませんでした。これは、裾の下に股のない袴を履いたとき、それを直裾袍がちゃんと覆えていないことに関係しています。袍の下に履いていた袴は当初まちがありませんでした。
まちとは奥行(厚み)をもたせるために部分的に縫い付ける布のことです。袴がまち付きのものに発展していくと、深衣は余分なものになり、直裾袍がますます好まれるようになって普及しました。
褝(たん:ひとえ)
■ 褝(たん:ひとえ)
褝(たん:ひとえ)
役人が平日くつろぐための服で、袍の形とほぼ同じものですが褝は上と下がつながっており、裏地はなく袍の下に着るか、あるいは夏に家にいる時の下着であったと考えられます。つまり執務室や家の居室などにいるときは褝のみを着ているが、外出したり接客するときは袍を羽織ってすぐに出られるようにしていたということです。イメージとしては、学校の先生がスーツの上にジャージを着ていたり、サラリーマンがスーツの上に作業着を着ているのと同じような感覚です。
まとめ
■ まとめ
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では三国志に登場する文官や武将が普段着として着ていたものや、仕事着として着ていた着物のについて紹介させて頂きました。文武百官が集まる朝廷では長袍を戦争時には胡服を普段着には褝や長袍を着ていたことがわかりました。今度三国志の漫画やドラマを見る際には、ぜひ服装にも注目してみてください。