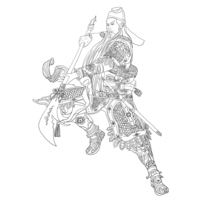司馬氏への反乱
■ 司馬氏への反乱
司馬氏への反乱
三国時代を統一に導いた人物が晋の初代皇帝・司馬炎になります。司馬炎は司馬昭の息子であり、司馬懿の孫にあたります。曹丕が建国した魏王朝を司馬氏が簒奪することになるのです。もちろん魏王朝に仕える家臣たちは司馬氏の専政に抵抗します。魏の皇帝・曹髦自らが司馬氏打倒のクーデターを起こしたくらいです。今回は251年に起きた司馬氏への反乱から振り返ってみましょう。はたしてどの反乱が最も成功に近づき、司馬氏を追い詰めたのでしょうか。265年には司馬炎が皇帝に即位しています。この間の15年間に起きた司馬氏への反乱をご紹介いたします。
251年司空の反乱
■ 251年司空の反乱
251年司空の反乱
251年には三公の一つである司空に就任していた「王淩」が司馬懿に対して反乱を起こそうとしました。王淩は董卓をクーデターによって抹殺した王允の甥にあたります。曹操に仕えてからは各州の刺史を歴任し、孫権との戦いで成果をあげています。征東将軍であり、かつ司空であった王淩は、曹操の息子である楚王・曹彪を担ぎ上げて魏の皇帝である曹芳を廃そうとしたのです。曹芳は司馬懿の傀儡と化していたからです。密告によってこの計画を知った司馬懿は老練にこれを攻略し、王淩は自害しています。楚王・曹彪もまた自害を命じられました。この反乱は挙兵には至っていません。司馬懿はこのすぐ後に病没しています。司馬氏への反乱はここから始まったのです。
254年皇帝外戚の反乱
■ 254年皇帝外戚の反乱
254年皇帝外戚の反乱
254年には司馬氏の専政に対して張緝が立ち上がります。張緝は魏の皇帝・曹芳の皇后の父親です。これに中書令の李豊が与し、名士である夏候玄を担ぎ上げました。司馬懿の跡を継いだ司馬師を除き、夏候玄をその後釜に据えようと皇帝の勅命を利用します。夏候玄は度量が大きく志が高く、交友関係も広かったようです。それ以前にクーデターによって司馬懿に処刑された曹爽もまた夏候玄の盟友でした。従弟でもあります。曹爽勢力の再興という側面もあったのかもしれません。しかしこちらの反乱計画も事前に漏れてしまい張緝、李豊、夏候玄だけではなく皇后すら処刑されてしまいます。さらに司馬師は曹芳を廃位します。次の皇帝には曹髦が即位しました。
255年寿春の反乱
■ 255年寿春の反乱
255年寿春の反乱
255年、曹爽や夏候玄と親しかった文欽と毌丘倹が寿春で反旗を翻します。寿春は呉との戦闘の最前線ともいえる重要拠点です。文欽は揚州刺史であり、毌丘倹は鎮東将軍でした。共に魏の重臣です。これが6万を超える兵と共に挙兵したのです。この危機的状況を打破すべく司馬師は自ら10万を超える軍勢を率いて出陣します。
呉の丞相であり大将軍である孫峻はこの隙に寿春を手に入れようと出陣しますが、魏の諸葛誕に防がれました。反乱軍も司馬師の軍勢に敗北し、主だった将は呉へ亡命していきます。この際、毌丘倹は捕縛され処刑されています。文欽親子は逃げ延びました。この反乱で司馬師が感じたプレッシャーも大きかったのか、鎮圧直後に司馬師も病没しています。
257年寿春の反乱
■ 257年寿春の反乱
257年寿春の反乱
257年、寿春で再び反乱が起きました。首謀者は魏の諸葛誕です。諸葛誕は毌丘倹・文欽の反乱の際にはその鎮圧に活躍しましたが、司馬師の後継者である司馬昭との関係が悪化し、挙兵を決断します。諸葛誕もまた夏候玄とは親しい間柄でした。諸葛誕は10万を超える兵を率いていたうえに、すでに呉と内通していました。息子である諸葛靚を人質として呉に送り、臣従を約束していたのです。
呉は大軍を率いて寿春を目指します。大将軍である孫綝が自ら出陣しました。丁奉、朱異、全端などの将軍の他に呉に亡命していた文欽親子も続々と諸葛誕の救援に向かっています。司馬昭は魏の皇帝・曹髦と皇后の親征を決断。26万に及ぶ軍勢で寿春を攻めました。さらに念を入れて対蜀の兵力も寿春に投入しています。
蜀の姜維は好機と見定めて北伐を再開します。こちらでは司馬望、鄧艾らが守りを固めて半年間持久戦を展開しました。まさに三国が同時に戦力を注ぎ込んだ大戦になったのです。司馬昭も強い危機感を感じていたでしょう。寿春での戦いに負けるようなことがあれば魏は大きく崩れることになります。
しかし司馬昭は冷静でした。力攻めをせずに寿春の城を包囲し、諸葛誕や呉に対して内応の調略を仕掛けて混乱させていきます。呉軍の将たちが魏に寝返っていくのです。鍾会の手紙偽造なども効果を発揮しています。呉の大将軍・孫綝は指示に従わないという理由で、味方の大都督である朱異を処刑しています。敵が一致団結できていないことが司馬昭にとっての追い風となりました。寿春の城内では諸葛誕と文欽が仲たがいし、文欽が殺害され、息子の文鴦が魏に逃れるという事件も起こります。諸葛誕と呉は内側から崩れ自滅していったのです。
関中でも鄧艾が姜維の挑発に対して我慢し続け、防衛ラインを死守します。寿春では魏に降伏し投降する兵が続出、最期に諸葛誕は城を出て戦いますが討ち取られました。蜀の姜維は寿春陥落の報告を受けて撤退。呉の孫綝も大敗での帰還となります。司馬昭は最大のピンチを切り抜けることができたのです。
まとめ・260年皇帝の反乱
■ まとめ・260年皇帝の反乱
まとめ・260年皇帝の反乱
そして最後に魏の皇帝自ら挙兵して反乱を起こしています。以前ご紹介しました260年の皇帝・曹髦のクーデターです。しかし反司馬氏の勢力はこれまでの一連の反乱によって摘み取られていました。曹髦のクーデターは影響力をほとんどもたず、司馬氏にまったくダメージを与えることなく、曹髦は殺害されて終了します。
こうして司馬氏の勢力を盤石なものにした司馬昭は晋王に進み、司馬昭が病没した265年に後継者である司馬炎が魏から禅譲を受けて皇帝となります。蜀に続き、魏は滅び、三国は統一へ加速していくのです。
こうして振り返ってみると、やはり257年の諸葛誕の反乱が最も司馬氏を追い詰めたものだったのではないでしょうか。ただ残念なのは呉にこの好機をものにできるほどの器量のある武将がいなかったということでしょうか。もし諸葛誕の反乱が成功し、寿春から魏に攻め込むような形になっていたら時代は変わっていたでしょう。司馬氏は滅ぼされ、魏の王朝も長く続いたかもしれませんね。