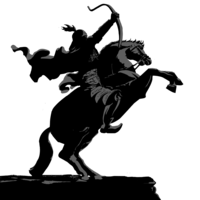曹髦の祖父と父親
■ 曹髦の祖父と父親
曹髦の祖父と父親
曹髦、字は彦士。魏の初代皇帝(文帝)・曹丕の孫にあたります。父親は東海王(東海定王)・曹霖です。曹霖は二代目皇帝(明帝)・曹叡の異母弟ということになります。曹霖はDVがひどかったようで、相手女性を殺害してしまうことも度々あったと伝わっています。曹髦はこの曹霖の嫡子というわけではなく、東海王を継承したのは兄である曹啓でした。こう見てみると、初代皇帝・曹丕の嫡流からは遠い血筋です。通常では皇帝即位は考えらえません。日本で例えると、徳川秀忠の嫡流から遠い徳川吉宗が将軍に就任するのと似ているかもしれませんね。当然のように強力な権力者の後ろ盾がないと成り立たない話です。
魏・三代目皇帝
■ 魏・三代目皇帝
魏・三代目皇帝
嫡流が途絶えたのは曹髦の代の話ではありません。先代、魏の三代目皇帝・曹芳からです。曹芳は二代目皇帝・曹叡の実子ではなく、養子になります。曹叡には男子が数名いましたがいずれも早世しており、跡継ぎがいない状態だったのです。そこで養子として迎い入れられたのが曹芳なのですが、実の父親が誰なのかはっきりとしていません。一説には曹操の子・曹彰の子孫という話もあります。曹叡の危篤状態の際に皇太子に立てられ、その日のうちに皇帝に即位しました。わずか8歳のことです。後見は曹爽と司馬懿でした。やがてこの二人は激しい政争を繰り広げることになります。
司馬氏の専政
■ 司馬氏の専政
司馬氏の専政
司馬懿がクーデターを起こし、曹爽勢力を一掃すると、司馬氏に権力が集中していきます。司馬懿の死後はその息子である司馬師が権力を継承しました。これに異を唱えたのが曹芳の皇后の父親・張緝ら反司馬氏勢力です。張緝や李豊は司馬師を誅殺し、名士である夏候玄を大将軍に据えて司馬氏の専政に対抗しようと考えましたが、露見して処刑されてしまいます。張緝の娘も皇后を廃されました。司馬師は23歳となった曹芳では操りにくくなったのか、皇帝すらも廃して斉王に降格させます。曹芳は皇帝から王へ、やがて公にまで降格させられます。子孫の詳細もまったく記されていません。このように、魏は三代目皇帝の時点でまったく権威を失っていたのです。
魏・四代目皇帝
■ 魏・四代目皇帝
魏・四代目皇帝
司馬氏は名目上、二代目皇帝・曹叡の皇后であった郭皇太后の名前を出して命令を下していました。司馬懿がクーデターを起こし曹爽を倒したときも郭皇太后の指示という形をとっています。司馬師が曹芳を廃するときも郭皇太后の指示となっています。司馬師は四代目皇帝に曹操の子である曹璩を推していましたが、郭皇太后の反対にあい、郭皇太后の推す曹髦が四代目皇帝に即位しました。当時の曹髦は14歳で、高貴郷公です。とても聡明だったと伝わっています。魏朝再興の望みをかけての曹髦の即位だったのです。司馬師としては内心面白くなかったはずです。
曹髦の人物評
■ 曹髦の人物評
曹髦の人物評
司馬師は曹髦の才気について鍾会に尋ねています。鍾会は「才は陳思王(曹植)と同じで、武は太祖(曹操)に類す」と答えています。文武ともにまさに英雄の才です。また石苞は曹操の生まれ変わりだと称賛しています。周囲の期待に応えるかのように、曹髦は向上心が高く、学問と武芸に熱心でした。群臣との交流も盛んで、群臣を集めて詩作をしたり、儒教の経典について議論をしています。曹髦の鋭さを見て、石苞は曹操の生まれ変わりだと称賛しています。曹髦の鋭い問いに返答に窮した学者たちも多かったようです。このまま健やかに育っていってくれれば、魏朝は再興されます。
司馬師の死と跡を継いだ弟の司馬昭
■ 司馬師の死と跡を継いだ弟の司馬昭
司馬師の死と跡を継いだ弟の司馬昭
255年に毌丘倹と文欽が司馬師の専横に憤り反乱を起こします。司馬師は心労がたたり、この年に亡くなりました。後継は弟の司馬昭です。257年の諸葛誕の反乱では皇帝である曹髦と郭皇太后が司馬昭の指示で親征を行っています。このあたりの司馬昭はやはり老練です。曹髦は司馬昭を相国に任じ、晋公と封じようとしましたが、司馬昭は拒否します。2年後の260年には準備が整ってきたのか、相国・晋公に封じられ、九錫を授けられました。曹丕が後漢王朝より譲位を受けたときの流れを踏襲しています。魏王朝に代わって晋王朝が建国されるのももう時間の問題だったのです。
曹髦のクーデター
■ 曹髦のクーデター
曹髦のクーデター
司馬昭が相国・晋公に封じられ、九錫を授かった同年、曹髦は一大決心をします。なんと、側近や宮中で働く奴隷を引き連れクーデターを実行したのです。それだけ司馬氏に追い詰められていたということですが、皇帝が直々に剣をとってクーデターを行うのは異例です。しかしあまりにも急な動きのために数百人という規模のクーデターになってしまいました。反司馬氏勢力に呼びかければまだまだ勢力は伸ばすことができたはずです。しかしせっかちな曹髦は「これを忍ぶべくんば、なにをか忍ぶべからざらん」と詔を投げ捨てて、宮中を打って出ました。これにはさすがの司馬昭も驚き、対応に困ります。皇帝に歯向かうということは逆賊ということになるからです。しかし放置しておけば曹髦の勢力が増していくばかりでしょう。早急な処分と解決が必要なのです。
まとめ・皇帝討ち死に
■ まとめ・皇帝討ち死に
まとめ・皇帝討ち死に
これまた前代未聞なのですが、宮中から打って出てくる魏の皇帝・曹髦に兵はまったく手が出せません。皇帝に剣を向けるということは反逆罪です。兵の全員が怖気づいています。司馬昭は重臣である賈充に兵を授け、対応させます。賈充は配下の成済に対し「この日のためにお前たちを養ってきたのだ。今日のことは不問に付す」といって成済を用いて曹髦を襲わせます。成済はそのまま曹髦を刺し殺してしまいました。このとき曹髦わずか20歳です。曹髦を裏切って密告した側近の王沈や王業は助かりましたが、密告に係わらなかった王経だけは処刑されています。しかも皇帝殺害の罪で成済も一族もろとも処刑されました。処刑の際にはさすがに成済も賈充らを罵倒していたようです。
葬儀は庶民として扱うとされましたが、司馬孚は郭皇太后に相談したため、王の扱いで葬儀することができるようになりました。
この後、5代目皇帝として迎い入れられたのは曹奐です。やはり歳若の16歳。司馬氏の傀儡となる皇帝ですが、司馬昭は虎視眈々と次のステップである禅譲の機会をうかがっていました。魏の滅亡はもう目前に迫っていたのです。