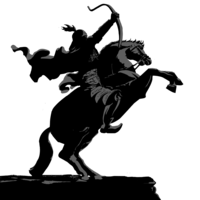トントン拍子に出世して最初の難関【公孫淵】と対決
■ トントン拍子に出世して最初の難関【公孫淵】と対決
トントン拍子に出世して最初の難関【公孫淵】と対決
カン丘倹(カンキュウケン 生年不明―255年)の父は涼州で太守を務めており、官位を得るほど出世していました。カン丘倹は父の跡を継ぐ形で魏に仕えています。後の魏国第2代皇帝となる曹叡(ソウエイ)に仕えていました。曹叡が即位すると、カン丘倹も出世し、皇帝直属部隊を任されるようになっていきます。カン丘倹は荊州・幽州・豫州・揚州と4州の刺史(長官のようなもの)を歴任していきました。
遼東(中国北東)では太守となっていた公孫淵(コウソンエン)が魏に服従する素振りを見せながら、呉と通じていました。呉の皇帝に即位していた孫権(ソンケン 182年―252年)は公孫淵を取り込んで魏に攻め入ろうとし、燕王として公孫淵を迎え入れようとしています。
しかし、公孫淵は孫権を裏切り、呉の使者を殺害して魏に送り、恭順の姿勢を見せて恩賞を受け取っていました。これに怒った孫権は、高句麗(中国北東から朝鮮半島北部を支配)を味方につけて公孫淵を成敗するべく軍を起します。孫権の北上を受けて、魏はカン丘倹に対処を任せます。
カン丘倹は北方の鮮卑(現モンゴル)を動かして遼東を守備し、孫権は配下の反対を受けて戦うことなく軍を退けています。この一連から魏は公孫淵に上洛を命じますが、公孫淵は反旗を翻してカン丘倹と戦います。長雨の影響もあって河川が氾濫し、カン丘倹は軍を撤退しています。
司馬懿の元で勝利
■ 司馬懿の元で勝利
司馬懿の元で勝利
公孫淵はカン丘倹を退けたことを受けて遂に本格的に反乱を起し、自身を燕王と称して、独立します。これに激怒した曹叡が司馬懿(シバイ 179年―251年)を総大将として派遣します。カン丘倹は司馬懿の配下に置かれ遼東に攻め込みました。司馬懿はこの戦いにおいて激戦となるようなものではなく、勝利は必然であるとして臨んでいます。
その通りに陸戦で大勝し、公孫淵を追い詰めていきました。蜀の諸葛亮(ショカツリョウ 181年―234年)と互角に戦ってきた司馬懿にとって、公孫淵は簡単な相手でもあり、その采配を間近で見ていたカン丘倹にも大きな経験となっていきました。カン丘倹はこの遼隧の戦いでさらに出世していきます。
高句麗平定に大貢献!
■ 高句麗平定に大貢献!
高句麗平定に大貢献!
公孫淵が処刑され、遼東の反乱を鎮めると、魏は高句麗に矛先を向けます。これには孫権の調略先が高句麗にも向けられていたことが影響しています。魏は国境を整備していくと、高句麗から略奪を受けており、244年にカン丘倹は軍を率いて高句麗に侵攻しました。
高句麗は2万の大軍で応戦しますが、カン丘倹は巧みな戦術を駆使して連戦連勝を築いていきます。ついには高句麗の首都である丸都城を落としました。事前に東川王(高句麗の王)は逃げ出しており、捕えることは出来ませんでした。カン丘倹は部下に墓地の破壊を禁じ、トンネルを掘って灌漑を実施するなど住民からも歓迎を受けていたといいます。
カン丘倹は捕虜と首都を返還し、東川王に降服を勧めますが、これには拒否を受けており、翌年にはさらに魏軍が大規模な東進を図り、高句麗は壊滅状態に陥りました。
この戦いを受けてカン丘倹の名声はさらに高まり、魏軍においても胡遵(コジュン)・王昶(オウチョウ)・諸葛誕(ショカツタン)・陳泰(チンタイ)といった優秀な将軍たちと揃って、複数の州をまたいで軍制を束ねる都督として存在していました。
対呉の前線にも赴く
■ 対呉の前線にも赴く
対呉の前線にも赴く
252年に孫権が死去すると、カン丘倹は呉討伐の計画を提案し、魏軍は大軍を以って呉の討伐に乗り出します。総大将的な位置づけには諸葛誕が就き、カン丘倹は荊州方面から呉軍を搖動する役目を担いました。しかし、本隊の諸葛誕が呉軍に敗れ、カン丘倹も退却します。
この敗戦で責任を負った諸葛誕と交代する形で、カン丘倹は対呉の前線に赴くこととなりました。翌253年には呉軍の諸葛恪(ショカツカク)が大軍で合肥新城に攻め入ります。合肥新城でカン丘倹は持久戦に持ち込み、城を包囲される中で懸命に防衛しました。2か月も経つ頃、城内にも疫病が浸透し、戦える兵士はわずかとなっていきます。
100日を過ぎる頃、魏から20万もの援軍が訪れ、ようやく呉軍は退却していきました。カン丘倹はこの戦いを受けて、戦死者を弔い遺族に便宜を図っています。
身の危険を感じて魏に反乱を興す
■ 身の危険を感じて魏に反乱を興す
身の危険を感じて魏に反乱を興す
この当時、魏の実権を握っていたのが司馬懿の長男である司馬師(シバシ 208年―255年)です。司馬師は実力者で人望もあった夏侯玄を処刑し、その友人でもあったカン丘倹はいずれ自分の身も危なくなると危惧していきます。
255年にカン丘倹は司馬師に不満を抱いている将軍の文欽(ブンキン)を抱き込み、6万の軍を率いて反乱を起します。カン丘倹は同じ立場である諸葛誕にも挙兵の声をかけますが、諸葛誕はこれに応じず、魏軍として追従しています。魏の総司令官である司馬師は自身が10万の軍を以って出陣し、父の司馬懿並みの用兵術でカン丘倹と文欽を追い詰めていきます。多くの兵が魏に投降し、文欽は呉へ亡命しており、カン丘倹は逃亡中に殺されてしまいました。
この反乱を受けて、カン丘倹の息子であるカン丘デンは殺されますが、妻は魏の建国に貢献していた荀彧(ジュンイク 163年―212年)の血縁でもあり、その当主となっていた荀ギ(ジュンギ)によって嘆願されており、処罰を許されています。弟と孫は呉へ亡命に成功しており、カン丘倹のもう一人の息子であるカン丘宗(カンキュウソウ)は呉に仕え、後に晋が呉を滅ぼした後には、許されて晋に仕えていきました。
まとめ
■ まとめ
まとめ
カン丘倹がいくら兵法に優れていても、魏には数十万の大軍を動かせる力があり、鍾会(ショウカイ 225年―264年)やトウ艾(トウガイ 生年不明―264年)、胡遵、諸葛誕、王基(オウキ 190年―261年)といった優秀な武将が揃っており、とても勝ち目がありませんでした。
それでも魏に対抗したのは、司馬師による権力の専横が要因であり、司馬懿のクーデターが無ければ魏の優秀な将軍として三国平定に貢献していたといえます。
なお、三国志の著者である陳寿は、カン丘倹をずば抜けた才能を持っている人物と評しています。