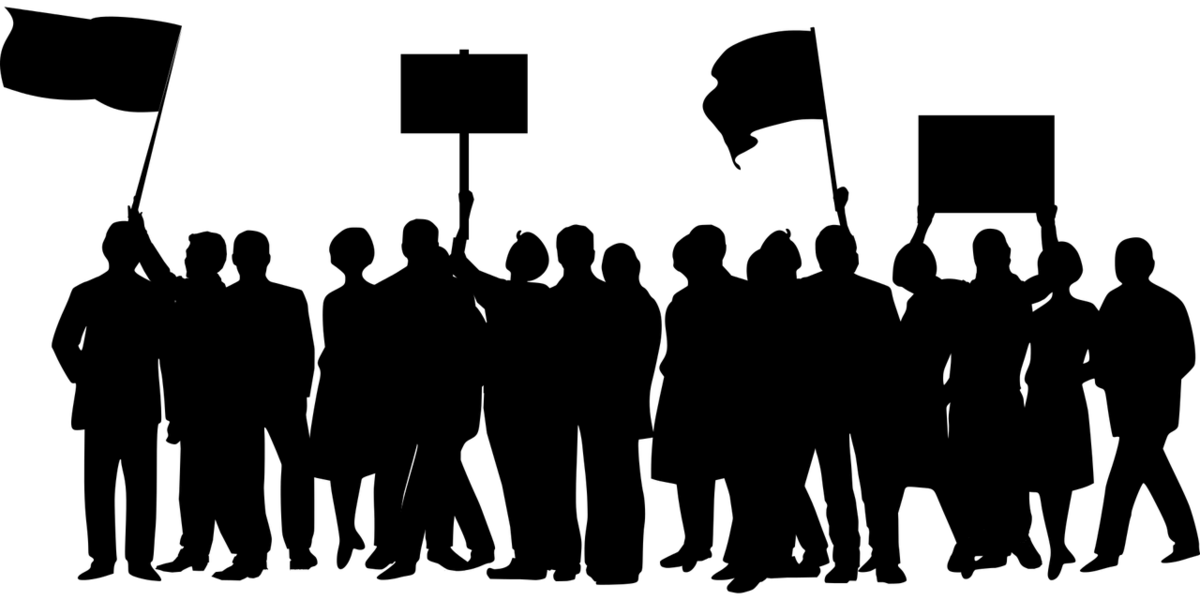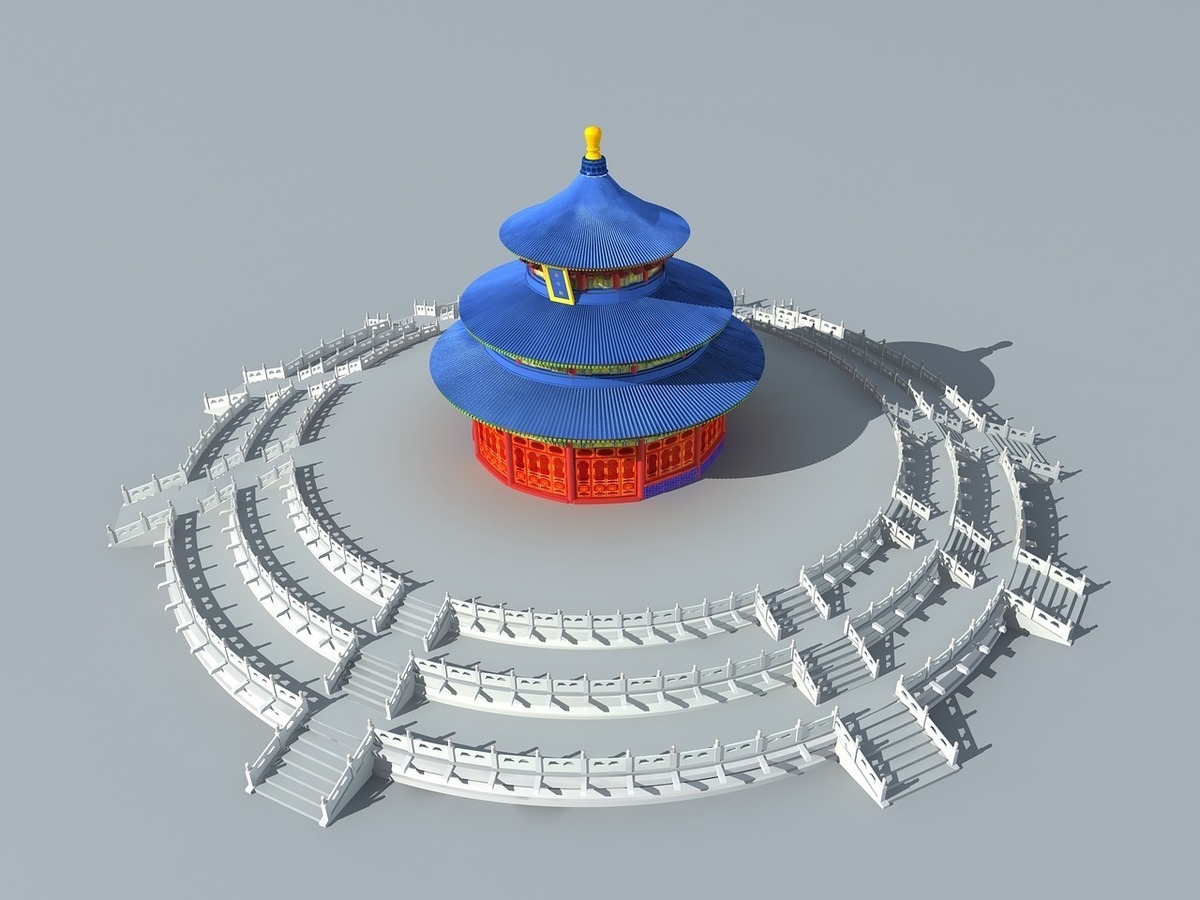黄巾の乱から始まった三国志
■ 黄巾の乱から始まった三国志
黄巾の乱から始まった三国志
さまざまな群雄たちがしのぎを削りあい、100年以上の長きにわたって熾烈な戦いを繰り広げた壮大な歴史物語、三国志。
そんな三国志の始まりとも言われる大きな事件といえば、間違いなく黄巾の乱でしょう。
歴史の教科書にも載っているほど有名なこの乱は、その後の群雄たちが基盤を得て決起するきっかけとなった重要な事件であり、また漢王朝が滅び群雄割拠の時代が訪れる直接的な要因となった事件でもあります。
それでは今回は、そんな黄巾の乱や、それを起こした黄巾党(黄巾賊)とはいったいどんな勢力だったのかを解説したいと思います。
黄巾党とは?
■ 黄巾党とは?
黄巾党とは?
黄巾党とは、後漢末期~三国志初期の時代にかけて中国で大流行していた宗教集団の俗称です。
その正式名称は「太平道」。教祖は張角という人物でした。
太平道が黄巾党と呼ばれているのは、太平道が黄老思想をベースにした道教を信仰しており、その信者たちが結束の証として黄色い頭巾を被っていたということに由来しています。
太平道の他の宗教と一線を画する点は、その圧倒的な規模です。時代背景のおかげもありましたが立ち上げから10余年で数十万人以上の信者を集めるという勢いは、他のどんな宗教勢力にも真似ができないものでした。
同じころの中国には、他にも五斗米道という宗教もあったのですが、規模は桁違い。太平道は河北を中心に、中国全土に瞬く間に勢力を広げていったのです。
太平道の教義は詳しくは伝わっていませんが、もともとは病人に自身の罪を告白させ、「符水」という護符を浸した水を飲ませて病を治療するという霊感治療を行っていた団体だったそうです。
それがここまでの勢力をもつようになったのは、その治療の成功率が圧倒的に高かったことと、また教祖である張角が類まれなカリスマを持っていたからなのだといわれています。
太平道の最大の特徴は、統制された組織体制。
信者が増えてくると張角は信徒を「方」と呼ばれる36個の小組織に分割し、それぞれを「渠帥(きょすい)」と呼ばれるリーダーに統治させました。
この組織編成は軍隊組織の構造に非常に似通っており、このことから張角は、後に黄巾の乱を起こすことを事前に計画していたとも言われています。
なぜ太平道はこんなに流行ったの?
■ なぜ太平道はこんなに流行ったの?
なぜ太平道はこんなに流行ったの?
ところで、いくら太平道が優れた宗教だったとしても、通常であればここまで信者数を増やすことは無かったはずです。
実は太平道が流行したころの中国は、民衆が苦しめられている時代でした。
当時の後漢王朝は長らく続く腐敗体制に悩まされていました。自身の立場を有利にするためだけに政治が行われ、自身の立場を少しでも有利にしようと宦官勢力と外威勢力が激しく政争を続けていました。
民衆は政府からのまともな庇護も受けられず、それどころか重税を課せられたことによる飢えに日々苦しんでいました。
そうした時代にあって、民衆は救いを宗教に求めたのです。
張角にあった病を治す神通力や、カリスマ性のおかげもあって、太平道は一気にその勢力を拡大していくのでした。
ちなみに太平道の勢力は宮中の中にも及んでおり、秘密工作員が宮中でクーデターを計画していたとも言われています。
この工作員は結局事前に計画が露見して処刑されてしまうのですが、現政府に対しての不満がどれほど大きかったかが分かるエピソードではないでしょうか。
黄天まさに立つべし
■ 黄天まさに立つべし
黄天まさに立つべし
中国には古くから「易姓革命」という思想がありました。
易姓革命思想によると、地上を治める王朝は天からその役目を委譲されているのですが、王朝が腐敗し天から見切りを付けられた場合には革命が起こるというもの。
その際には新たに、徳を備えた一族が新王朝を打ちたてる(姓が易わる)とされています。
そのため、王朝に不満がある場合には、腐敗した王朝は倒さなければならないと考えるのは自然な流れでした。
太平道の信者はその大多数が貧しい農民たちで、政府に苦しめられている張本人でした。日々苦しい生活を強いられながらも、一向に変わろうとしない王朝に対して、我慢の限界に達した不満が爆発したのは西暦184年のこと。
太平道の信者たちが、河北一帯を中心に一斉に武力蜂起した事件が、黄巾の乱でした。
黄巾の乱には、王朝打倒を目指したスローガンが掲げられていました。数十万に上った暴徒たちは、各地の町や村、官舎などを次々に襲い、建物の門や壁に書置きを残していっていました。
そのスローガンは「蒼天已死 黄天當立 歳在甲子 天下大吉(蒼天すでに死す 黄天まさに立べし、歳は甲子、天下大吉となる)」というもの。
ここでいう蒼天とは天の意志のこと、黄天は太平道のことです。
つまり意味としては、現在の漢王朝からは既に天の意志が離れているので、今まさに太平道が蜂起して王朝を打ち倒すべし! というもの。また甲子の年、つまり今年中に太平道が天下を手にして世の中を幸福にする。という予言もこめられた言葉です。
このスローガンに感化されて、呼応した信者たちによる蜂起が各地で相次ぐことになったのです。
ところで、当時の中国で一般的な考え方でもあった陰陽五行説では、世界のあらゆるものは五つの属性であらわすことができると考えられていたのですが、実は陰陽五行説において、黄(土)は蒼(木)との属性相性は最悪でした。
もしかしたら張角には、黄巾の乱は初めから分の悪い勝負だということが分かっていたのかもしれませんね。
まとめ
■ まとめ
まとめ
その後の黄巾の乱がどうなったかは皆様もよく知るところ。
武装した各地の群雄たちによってあえなく鎮圧されることになり、またその後の歴史の転機となりました。
歴史は勝者が作るものです。
そのため敗者となった太平道はカルト集団的な見方をされて、のちの歴史においても厳しい目を向けられることになったのです。
とはいえ、現在の王朝に不満を抱き、民衆にとってより良い世の中を作ろうとしていたのは、太平道の信者たちも後の英雄たちも同じことでしょう。
もし黄巾の乱によって太平道が王朝を倒せていたとしたら、一体中国の歴史はどんな形になっていたのでしょうね。そんなIFを想像してみるのも面白いかもしれません。