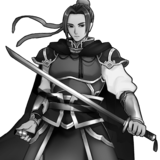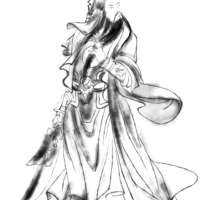一般的な劉備(玄徳)のイメージ
■ 一般的な劉備(玄徳)のイメージ
一般的な劉備(玄徳)のイメージ
あなたはは劉備(玄徳)についてどんなイメージを持っていますか?
一般的には「泣いて天下を獲った」、「謙虚で徳の高い人」、「やさしいおじさん」などプラスイメージが定着しています。
漫画やドラマ、小説では冷酷な曹操や短気な孫権に比べると根っからのいい人、理想の君主像として描かれています。ところが、史実の劉備(玄徳)はそんなに仏のような人物ではないそうです。
幼い頃から既に野望を抱いていた
■ 幼い頃から既に野望を抱いていた
幼い頃から既に野望を抱いていた
劉備(玄徳)がまだ幼い少年だったころ、彼の故郷の?県へ天子による巡行の行列が訪れました。
巡行とは、皇帝が自ら地方の状況や人々の暮らしぶりを確かめるために領地内を巡回することで、秦の始皇帝が始めた国事行事です。さらに「皇帝の威厳を示す」という目的もあったので、この行列には大臣、官僚、医官、僧侶、女官や皇族までもが随行し、莫大な費用と労力を要しました。
それにこの巡行は庶民にとってはありがた迷惑な行事で、皇帝が通る道をふさいではいけない。庶民は路肩に避けて歓迎しなければならないなど、変なルールが確立してしまいました。そしてもし、行列の行く手を遮ろうとすれば処罰の対象となります。また、暗君の場合は路上に倒れている身体が不自由な人を轢き殺すこともあったそうです。
この行列に遭遇した劉備(玄徳)は母親と叔父と一緒に路肩で見物していました。
皇帝が乗る馬車はどこの王侯、貴族よりも豪華な装飾が施されているのでひと目でそれがわかります。まだ幼かった劉備(玄徳)少年はとても危険な発言をしました。
「母ちゃん、オイラもいつかはあの馬車に乗って見せる!!」
劉備(玄徳)少年の大胆発言に周りの大人たちは一斉に振り向き、苦笑いを浮かべる者までいました。驚いた劉備(玄徳)の叔父は慌てて劉備の口をふさぎ、人気のない場所へ連れて行きました。
劉備(玄徳)のこの発した「あの馬車に乗る」は「皇帝になる(漢を乗っ取る)」という意味があります。だから劉備(玄徳)の叔父と母親は慌てていたのです。これより約半世紀後、劉備(玄徳)はこのときの願望を達成するのですが、母親も叔父も既に他界しており、その姿を見せることはできませんでした。
学生時代は劣等生
■ 学生時代は劣等生
学生時代は劣等生
劉備(玄徳)は15歳になると清純派の名士として有名な蘆植の門下生となりました。蘆植は劉備(玄徳)と同じ涿県の出身で、その門下生には公孫瓉もおり、公孫瓉は劉備(玄徳)の兄弟子にあたります。黄巾族討伐の際は、このときの縁を頼って公孫瓉配下の将として加わりますが、それは後の話です。
実は劉備(玄徳)、学問はそれほど得意ではなかったようで講義はあまり真面目に受けていなかったようです。学生としては劣っていたものの、元来の気さくで温厚な性格で人々からの人望が厚く、酒場や賭場でたむろするようなならず者からガリ勉タイプの知識人までが劉備(玄徳)と友達になることを望んだといいます。
劉備(玄徳)は蘆植の門下生の中では苦学生に分類されていたらしく、学費と称して叔父に呑み代をたかっていたり、良く通る声を活かして市場や料理屋の呼び込みバイトなどをして小銭を稼いだ経験もあるそうです。
監察官を鞭打ちする
■ 監察官を鞭打ちする
監察官を鞭打ちする
劉備(玄徳)が義勇軍とともに黄巾軍と戦ってようやく得たものは安喜県の県尉(警察署長)でした。しかもこの仕事は名ばかりで監察官に賄賂を贈らないと就業を維持することができませんでした。
劉備(玄徳)が就任してしばらくすると監察官が監査という名目で賄賂徴収に来ました。演義では、賄賂を要求してくるこの男を張飛が怒って馬を繋ぐ柱に縛り付け、鞭でボコボコに殴りつけるのですが、史実ではこの乱暴を働いたのは劉備(玄徳)で、関羽と張飛はこれを制止しようとしていたとされています。
劉備(玄徳)はそれだけでなく、ぐったりした監察官の首に巾着に入れた官印をぶら下げ、額に辞職願を貼りつけて逃走したそうです。
家族を見捨てること3度
■ 家族を見捨てること3度
家族を見捨てること3度
たいていの父親は、自分の妻や子供、いわゆる家族のために粉骨砕身働きます。家臣や仲間を家族のように大切に扱う劉備(玄徳)ですが、自分の家族はあまり大切にしていない言動が目立ちます。実際劉備(玄徳)は3度も家族を置き去りにして、単身で逃走しています。
1度目 呂布に徐州を簒奪されたとき
■ 1度目 呂布に徐州を簒奪されたとき
1度目 呂布に徐州を簒奪されたとき
劉備(玄徳)が家族を置いて逃げることになった1度目の事件は呂布による徐州簒奪です。陶謙より徐州牧を引き継いだ劉備(玄徳)は、いてつく島もなかった呂布が居候することを受け入れ、留守の間に奪われるという惨劇に見舞われます。このとき、劉備(玄徳)の正妻と長男も人質となってしまいます。追い返された劉備(玄徳)は家族を置いたまま小沛に逃げ落ちます。
これは不可抗力なので仕方がないのですが、もう少し真面目に戦うべきではないかな?と個人的に思いました。小沛でひと段落した劉備(玄徳)は呂布に和睦を申し入れて代わりに妻と長男を返してもらいました。
2度目 呂布の反撃
■ 2度目 呂布の反撃
2度目 呂布の反撃
劉備(玄徳)は徐州を取り戻そうと攻撃しますが、呂布の反撃にあいます。小沛に逃げ込んでも猛追撃を受け、劉備(玄徳)は敗走するのですが、家族は置き去りにしたまま。妻と長男はまた呂布の人質にされました。人質になった劉備(玄徳)の妻と長男はこれ以降登場しないので、この後処刑されたか自害していたと思われます。
3度目 長坂の戦い
■ 3度目 長坂の戦い
3度目 長坂の戦い
長坂の戦いの際、劉備(玄徳)だけでなく随行していた避難民たちも曹操の猛追撃を受けて家族と散り散りに逃走しました。劉備も自分が逃げるのに必死で、二人の夫人と阿斗(後の劉禅)とはぐれてしまいました。しかし、運よく趙雲が夫人ひとりと阿斗を救出することに成功しました。
ホラ吹きの才能は天下一品
■ ホラ吹きの才能は天下一品
ホラ吹きの才能は天下一品
劉備(玄徳)は若かりしころ、ホラ吹き上手(嘘をつくのが上手い)と言われていました。その能力はむしろ売りをしていたころに磨かれたそうです。とにかく嘘をついてでもなるべく好条件で雇ってもらったり、お客さんが買いたくなるようなキャッチコピーで宣伝しなければならないので、ホラ吹き上手というよりセールスが上手いといった方が妥当だと思います。
劉備(玄徳)が売り物としていたのはむしろやわらじですが、一定の需要はあるもののバカ売れするような商品ではありませんでした。涿県の市場では誰でも出店することができるのですが、売り物も似たり寄ったりで呼び込みがある程度うまくいかなければ、商品の売れ残りが出てしまいます。劉備(玄徳)は精肉や魚を売っているような屋台の主人と仲良くなって自分の商品が売り切れになったり、需要がなさそうなときは率先して手伝っていたそうです。
劉備(玄徳)のキャッチセールス
■ 劉備(玄徳)のキャッチセールス
劉備(玄徳)のキャッチセールス
劉備(玄徳)の隣で肉を売る屋台の主人は口下手な男で、正直売れない肉屋でした。それを見かねた劉備(玄徳)が、
「オヤジ!!あんまり調子よくなさそうだね。オレが呼び込み手伝うからオレと母ちゃんが食える分の肉を分けとくれよ」と交渉しました。
主人がこれに承諾すると、いよいよ劉備(玄徳)はよく通る声でホラ吹きを発揮します。
劉備 「さーさー、おいしい肉はいらんかね?みんなが欲しい肉はここにあるよ!、そこのご婦人
あいや待たれい!」
婦人 「なにさ、あたし忙しいんだよ」
劉備 「ご婦人のとこは坊ちゃんがいるかい?」
婦人 「うちは息子が3人いるよ」
劉備 「ご婦人、やっぱ親なら坊ちゃんに大きくなって欲しいと思わんか?」
婦人 「そうだね。やっぱ男だから丈夫な子には育ってほしいと思うけど…」
劉備 「じゃあ、ご婦人ここの肉をおススメするよ~!オレはここの肉を食って大きくなったんだ
(もちろん嘘)」
婦人 「たしかに、あんた身体が大きいね!!」
劉備 「おうよ!!ここの肉を食えば…ホレこの通り。オレみたいな丈夫な男に育っちゃうよ~、
さあさあ買った買った!!」
婦人 「そうね、じゃあ1斤買っていこうかしら…」
劉備 「ありがとう!!でもご婦人それじゃあちょっと足りないんじゃないかい?あんたのとこ男
3人いるんだろ?思い切って1人1斤、3人分で3斤買って食わせてやろうぜ」
婦人 「そうね…たしかに1斤じゃすぐになくなるし…あんたのいう通りにするよ」
こういう調子で女性をターゲットにした呼び込みや自分のでかい図体を活かしたキャッチセールスをしていたらしいです。劉備(玄徳)が店の手伝いをすると必ず完売するという具合でした。それだけ交渉したり、人の気分がよくなることを口にするのが得意だったのではないかと思います。
一般的な劉備像は羅貫中の策に溺れている
■ 一般的な劉備像は羅貫中の策に溺れている
一般的な劉備像は羅貫中の策に溺れている
いかがでしたでしょうか?
きっと劉備(玄徳)に対するイメージに変化があったと思います。三国志演義を著作した羅貫中は、蜀漢をよく見せるために蜀にとって悪いことは書かなかったり、張飛に罪をなすりつけたり、孫呉の手柄をさも諸葛亮がやったというように挿げ替えています。劉備(玄徳)とて人間なので、長所もあれば短所もあります。
劉備(玄徳)のことを仏様のようなリーダーだという観念があるのなら、それは羅貫中の策に溺れているのです。