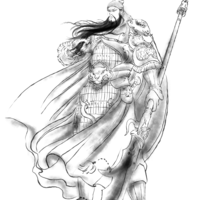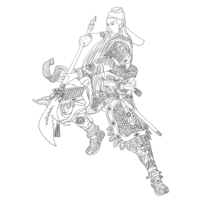帝を勝手に変えようとする董卓
■ 帝を勝手に変えようとする董卓
帝を勝手に変えようとする董卓
やりたい放題の董卓はまず帝を変えるというかなり無茶なことをやってのけました。「今の帝は使えないから弟の陳留王(ちんりゅうおう)を帝にしよう!」と言って本当に実行してしまうのです。もちろん反対者はいますがことごとく反対意見を潰します。
最初は丁原(ていげん)が反対しましたが殺してしまい、次に袁紹(えんしょう)が反対した時には一触即発状態となりました。しかし袁紹に董卓を止める手立てはなく、本当に帝を後退させてしまうことに成功させてしまいました。
そして自分に賛成派の物だけを中央に置いてさらに横暴に出てしまうのです。肝心の帝はというと発言力は全くなく案の定董卓の言いなりになってしまうのです。
これにより董卓の横暴は加速し、三国志一の悪者として名を轟かすのでした。帝を廃止してしまうシーンが強引すぎて思わず「え~っ?」と言ってしまいます。
李儒(りじゅ)の言うことを素直に聞く董卓
■ 李儒(りじゅ)の言うことを素直に聞く董卓
李儒(りじゅ)の言うことを素直に聞く董卓
天上天下唯我独尊と言った董卓ですが、なぜか李儒の言うことは素直に聞きます。中郎将盧植(ろしょく)が「あまりに我を通そうとすると帝の位を簒奪しようと思っていると思われます」と言ったのに対しブチ切れて、いきなり「斬ってしまえ!」というのです。
そんな取り乱した董卓に対して李儒は「盧植は学者なので斬ってしまったら評判が下がってしまいます」と伝えます。すると、心を入れ替えたのか「では追っ払え!」と言います。「殺せ!」と言った瞬間に李儒の一言で改心するのは董卓にしてはかなり珍しく「えっ李儒の言うことなら簡単に聞いちゃうの?」という感じで驚きでした!
周毖(しゅうひ)の言うことを素直に聞く董卓
■ 周毖(しゅうひ)の言うことを素直に聞く董卓
周毖(しゅうひ)の言うことを素直に聞く董卓
帝を廃止して陳留王を新たな帝にしたというエピソードは上記で述べましたが、その際に一回目は丁原に、二回目は袁紹に反対されています。丁原に対しては呂布を見事寝返らせて殺してしまいました。
袁紹の時も「殺してしまえ!」と言って軍を出そうとしたのですが、周毖に「袁紹に対して軍を出したらお互い被害が大きすぎる」と諭されました。すると董卓は「そうかなぁ」と言って結局軍を出すことを止めました。
今までだったら「うるさい!反対する奴は斬るぞ!」とすごむところでしたが「そうかなぁ」と弱弱しく言う董卓に対して「え~!」と言わざるを得ませんでした!いつも鬼畜で横柄な董卓ですがごく稀に部下の言うことを簡単に聞き入れるシーンがあるので「こいつかわいいやつかも」なんて思われてしまうこともあるのでしょう……
策が見破られ強行突破しようとする李儒
■ 策が見破られ強行突破しようとする李儒
策が見破られ強行突破しようとする李儒
これは董卓がというよりは、董卓陣営がという話です。帝だった弘農王(こうのうおう)がその座を陳留王に取られた後の話です。弘農王と何太后(かたいごう)を幽閉していたわけですが、後々反対勢力になったら困るので李儒に「殺してしまえ」と命じます。
その際何太后に対して酒をふるまったのですが、すぐに毒だと見破られてしまいます。「毒じゃないならお前が飲んでみろ」と言われ李儒は何も言えなくなり縄と短刀を渡し「いずれか好きな死に方で死ね」と言うのです。それに対し何太后が罵ったので李儒は高楼の蘭から投げ落として殺してしまいました。そして何食わぬ顔で董卓に「命令通りにしてきました」と言って首を差し出すのです。とは言え、毒殺→自殺ができなかったから高いところから落とすというかなり強引な手に走ったのに「命令通り」はないだろ!と突っ込みどころ満載の李儒に驚きです。
晴れた日に祭りをする男女にブチ切れる董卓
■ 晴れた日に祭りをする男女にブチ切れる董卓
晴れた日に祭りをする男女にブチ切れる董卓
ある祭りの日に農民の男女が晴着を着て帰っているのを董卓が目の当りにしてしまいました。「農民のくせにこんな晴れた日に着飾って働かないなんてどういうことか!」といきなり怒り、捕まえて手足に縄を縛り付けて二頭の牛に縛り付けその二頭の牛を真逆に歩かせ引き裂いてしまいました。
その際に血で梅園を染めたわけですが「花見よりもよほど面白かった!」と言って董卓は満足してしまいます。
あまりに鬼畜ぶりな董卓に「え~?」を通り越して「おいおいおい」という言葉が出てきてしまいます。反董卓連合ができるのもうなずけるような人物エピソードですよね!
かなり鈍感な董卓
■ かなり鈍感な董卓
かなり鈍感な董卓
董卓は敵が多い為結構神経をとがらしていることが多いのですが、呂布を手にしてからというもの警戒心が若干薄れてしまったのではないかと思います。それは自室で寝ていた時のことです。曹操が王允からもらった件で董卓を殺そうとするのですが呂布がいるためどうしても実行に移すことができませんでした。
呂布が席をはずし、董卓が寝ていると思った曹操はチャンスとばかりに剣を抜きました。しかし鏡に映り曹操は「なんだそれは?」と言われてしまいます。
とっさに「この剣を董卓様に献上しようと思いまして、拭いていたところです」と三国志の帝王とは思えないなんとも情けないエピソードです。しかしこの話はここで終わりではありません。董卓は「そうかそうか」と言ってこの剣をもらうのですが、呂布に対して「今日の曹操おかしくなかったか?」と尋ねるのです。呂布は曹操が董卓のことを殺そうとしていたのが分かったため「そりゃ、曹操は殺そうとしていましたからね」と言って初めて董卓は命を狙われていたことに気付くのです。
この件曹操、董卓共に「嘘でしょ!」と言いたくなるような間抜けな話で、三国志の中でも最も間抜けなエピソードの一つと言っても過言ではないと思います。ちなみにここで逃げ延びた曹操は董卓に恨みのあるものを募って反董卓連合を結成することとなります。
まとめ
■ まとめ
まとめ
悪名の限りを尽くした董卓から出てくる話と言えばやはり人間性を疑うような彼の悪事ばかりが目立ってしまいます。しかしごく稀に「部下の進言を聞くなんて董卓らしくない」と思ってしまうこともあるのです。
そういった意味で全く行動が読めない董卓は目が離せない人物NO.1かもしれません。日本で言うと織田信長のような感じでもありますが、もちろん信長より卑劣です。それでもカリスマ性があるのかただ単に恐怖心があるのか董卓についていく家臣も少なくありません。
三国志を読む上で董卓は「え~!」と思わせる宝庫と言える人物です。つつけばキリがありませんが、少しでも董卓のことについて分かっていただけたら幸いです!