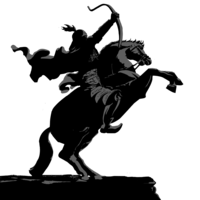魏の五大将軍
■ 魏の五大将軍
魏の五大将軍
三国志演義の主役である「蜀」には「五虎大将軍」と呼ばれる五人の勇将がいます。筆頭の「関羽」、その義弟「張飛」、錦馬超こと「馬超」、老黄忠こと「黄忠」そして古参の「趙雲」のことです。現代でもとても人気のある武将たちです。
それに対抗するように「魏」にも五人の名将がいるのです。後世になって「五大将軍」と呼ばれるようになりました。正史では優れた功績を残した武将ということで、この五人がまとめられた伝が作られています。
筆頭の「張遼」、「楽進」、「于禁」、「張郃」そして「徐晃」を指します。楽進以外の四人は他勢力の武将だった者たちです。その中でも今回は中国の名将「百将」にも選ばれている徐晃についてご紹介いたしましょう。
白波賊頭目・楊奉の配下
■ 白波賊頭目・楊奉の配下
白波賊頭目・楊奉の配下
徐晃、字は公明。生まれは司隷河東郡です。どのような家に生まれたのかはまったく不明になっています。この河東郡は黄河を挟んで都・洛陽の北にあるのですが、賊徒の群れが巣を作っており、治安の不安定なところです。白波賊と呼ばれています。かつては黄巾の乱に与したこともありました。リーダー格に楊奉、韓暹、李楽、胡才などがいます。その中でも楊奉は武勇に優れ、あの曹操をして精強な一団と言わせしめたほどでした。
徐晃はこの楊奉に仕えています。どのような経緯で仕えるようになったかはわかりませんが、徐晃の知勇兼備の才を見て楊奉が気にいったのではないでしょうか。事実、徐晃は楊奉の相談役のような役割も担っていました。
要するに徐晃は賊徒の一員だったわけです。
大司馬・李傕の配下
■ 大司馬・李傕の配下
大司馬・李傕の配下
白波賊の頭首らの中で、楊奉だけが兵を率いて当時の最高権力者である李傕に仕えます。李傕は董卓の部下だった男で、董卓の死後、新都・長安を占拠し、後漢皇帝の身柄を押さえて傀儡政権を誕生させています。徐晃はこのとき、李傕の部下のそのまた部下だったわけです。李傕は邪教に傾倒しており、巫女の占いを信用していました。
長安は地獄図のように荒廃していきます。楊奉は李傕の独裁政権に不信感を抱き、暗殺を計画しますが失敗し独立。ここで徐晃は後漢皇帝を長安から脱出させ、洛陽に向かうことを進言します。楊奉は徐晃の案を受け入れて後漢皇帝を保護し、これを守護しながら長安から洛陽を目指しました。李傕の追撃は凄まじく、楊奉は昔の仲間である白波賊の頭首らに援軍を求めます。こうして楊奉らは何とか洛陽までたどり着きました。
大将軍・曹操の配下
■ 大将軍・曹操の配下
大将軍・曹操の配下
後漢皇帝が無事に洛陽にたどり着けたのには兗州牧である曹操の協力もありました。洛陽に到着した楊奉や韓暹らははしゃいでいましたが、やがて共に後漢皇帝を守護してきた董承らと政争劇をはじめます。そしてその隙に曹操に後漢皇帝を奪われるのです。曹操は許に後漢皇帝を迎え、ここを都としました。曹操は大将軍に任じられます。楊奉は戦で曹操に敗北し、落ち延びていきます。徐晃はそれ以前に楊奉に曹操に帰順するように勧めていましたが、楊奉はその提案をはねのけています。敗北した楊奉を見捨て、徐晃は曹操に降りました。徐晃はこのとき卑将軍に任じられています。楊奉は袁術のもとに逃げ込みました。曹操は大勢力である袁紹の立場を気にして大将軍の座を譲り、司空、車騎将軍となっています。
徐晃はついに己の命をかけて仕えるべき主君に巡り合ったのです。
連戦連勝の徐晃の活躍
■ 連戦連勝の徐晃の活躍
連戦連勝の徐晃の活躍
この後の徐晃の戦場での活躍は目を見張るものがあります。
最強を誇る呂布軍と戦い武功をあげ、さらに劉備軍を退け、袁紹軍との戦いでは猛将の顔良・文醜を破りました。西涼の馬超との戦いでも敵将・梁興を討ちました。漢中の張魯を攻めた時にも異民族である氐族を打ち破っています。
徐晃の戦上手は、斥候の起用の巧みさにありました。情報収集の重要性を常に意識していたようです。情報を分析し、不利だと察すると退路の確保にぬかりはなく、また好機だと知るとどのような時間であろうと容赦なく攻めました。
徐晃はこれだけの功績をあっても驕ることなく、名君・曹操に出会えたことを感謝し続けていたといいます。徐晃の武勇と謙虚さは、あの関羽から評価されています。やや他人を見下す癖のあった関羽ですが、魏の中では張遼と徐晃のことは認めていました。親しく交わっていたともいわれています。
長駆直入の故事となる
■ 長駆直入の故事となる
長駆直入の故事となる
219年、魏の領地に関羽が侵略してきました。荊州北部の襄陽、樊城が攻められます。守備側の総大将は曹仁です。援軍に出た五大将軍の于禁は関羽に敗れ捕虜となります。猛将の龐徳も同様に援軍に出ましたが関羽に討ち取られました。
曹操は危機を感じ遷都すら考えたといいます。この時に関羽の背後を突いたのが呉の呂蒙です。さらに曹操が援軍として宛から送り込んだ徐晃が真正面から攻めて関羽軍を破ります。
曹操は徐晃の戦いぶりを見て「これほど長い距離を進軍し敵の包囲網を破った将は初めてだ」と賞賛しました。これより徐晃のこの戦ぶりを「長駆直入」と呼び、後世まで語り継がれることになります。
蜀びいきの「三国志演義」でもこの戦で徐晃が関羽を一騎打ちで八十合打ち合って退けたと記載しています。(ただし関羽は負傷していた)
まとめ・周亜夫の風格
■ まとめ・周亜夫の風格
まとめ・周亜夫の風格
宿敵関羽を撃破し戦勝に浮かれる曹操の陣営でしたが、徐晃の陣営だけは整然として持ち場を離れることはなかったといいます。徐晃の統率ぶりは兵卒の末端まで行き渡っていたのです。そんな様子を見た曹操はさらに感心し、「徐晃には周亜夫の風格がある」と称えました。周亜夫とは前漢の名将で、陣営にあっては訪れた皇帝に対しても陣中の作法を強要し、皇帝より真の将軍であると称された人物です。
こうして徐晃は、曹操が没した後は文帝(曹丕)、明帝(曹叡)に仕え、右将軍まで出世しました。227年に病没しています。
ちなみに三国志演義では反乱を起こした新城郡の孟達を攻めたときに、孟達が放った矢で額を貫かれて戦死していますが、これは関羽を倒した徐晃をおとしめるフィクションです。
いささか地味なイメージもある徐晃ですが、よくよく知ると驚くべき活躍をしています。
まさに徐晃は兵の統率力、戦場での駆け引きにおいて三国志最強レベルを誇る武将なのです。