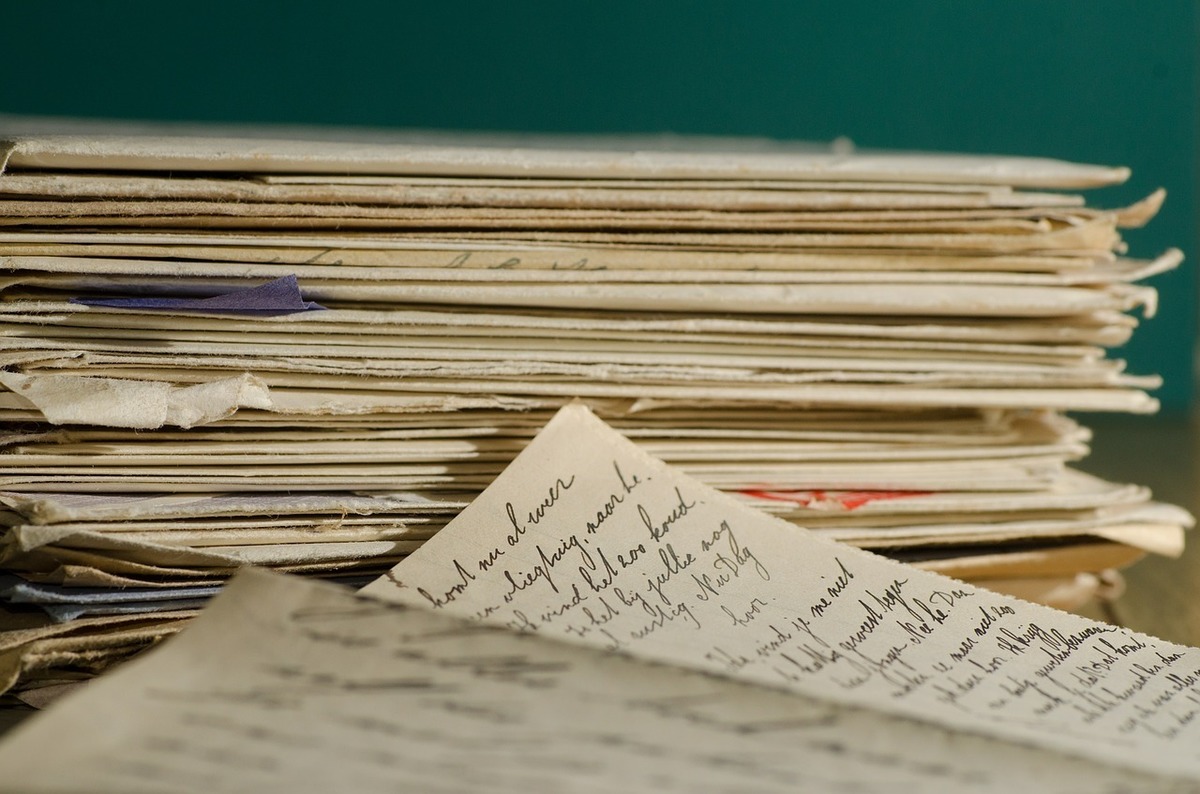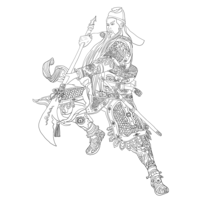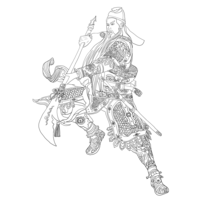正史と演義の違い
■ 正史と演義の違い
正史と演義の違い
三国志には歴史書として書かれた正史三国志と、後の世に大衆受けを重視して創作された三国志演義の二種類がある、という話は以前したかと思います。
もちろん同じ「三国志」という名前がついていることからも分かるように、正史をベースにして演義は作られているのですが、とはいえ、実際にはこの二つはまったくの別物といっても良いほどに、見比べてみると、実はビックリするような違いがいくつもあるのです。
というわけで今回は、日本での一般的な知名度が高いとされる演義のエピソードの中から、正史との違いを取り上げてご紹介したいと思います。
孫堅は伝国の玉璽を得ていなかった?
■ 孫堅は伝国の玉璽を得ていなかった?
孫堅は伝国の玉璽を得ていなかった?
三国志初期の名場面の一つといえば、呉の礎を築き上げた孫堅が、伝国の玉璽を手に入れるエピソードではないでしょうか。
反董卓連合として出陣した孫堅は、董卓が撤退し焼け野原となった洛陽の古井戸から見つけ出したというもので、「天は私に天下をとれと言っているのだ!」と孫堅が決意を固めるという印象的なシーンですよね。また孫堅亡き後は、息子の孫策を通じて袁術へと渡り、孫策の覇業を大いに助けたといわれています。
ところが実は、陳寿が記した正史三国志にはこうした孫堅が玉璽を得たというエピソードは一切出てきません。
それではこのエピソードは全くの創作なのかというと、そうではありません。
裴松之が正史三国志に付けた注釈には、「呉書」と「山陽公載記」という史料から引用して、孫堅が井戸の中から玉璽を見つけ出したというエピソードと、玉璽を孫堅が手に入れたことを知った袁術が孫堅の妻を人質にして玉璽を奪い取った、というエピソードが記載されています。
三国志演義ではこのエピソードを元にして、後の孫策の飛躍につながるようによりドラマチックな展開を創作したのです。
ちなみに、裴松之は上記のように玉璽のエピソードを載せつつも、一方の「孫堅伝」では「もし孫堅が玉璽を手に入れていたとして、忠義の士である孫堅がそれを秘匿して自身の物にしようとするだろうか」とも懐疑的な立場を記しています。
結局、実際のところがどうだったのかは謎のままなのです。
十万本の矢は孫権の手柄だった?
■ 十万本の矢は孫権の手柄だった?
十万本の矢は孫権の手柄だった?
演義での創作エピソードがダントツで多い武将といえば、間違いなく諸葛亮でしょう。
諸葛亮の神算鬼謀を尽くした計略たちは、実際のところそのほとんどが創作されたエピソードです。
さて、そんな諸葛亮の序盤の見せ場である赤壁の戦いでの活躍は、周瑜との対比によって、より諸葛亮の神がかった智謀が強調される名場面でもあります。
赤壁開戦直前のある日、軍議の席で諸葛亮は周瑜に命じられます。
「10日以内に10万本の矢を用意してもらいたいのだができるだろうか?」
これは現実的には不可能ともいえるレベルの命令で、諸葛亮に脅威を抱きつつあった周瑜は無理難題を吹っかけて、それを口実に諸葛亮を罰してしまおうと考えたのです。
これに対して諸葛亮は「3日でやってみせましょう」と答え、さらにもし達成できなかったらどんな罰でも受けます、という署名までしてしまいました。
この後の展開は皆様ご存知の通り。
藁束を積んだ船で漕ぎ出した諸葛亮は、わざと曹操軍の陣営付近まで近づき、船に向かって矢を射させることで見事10万本の矢を用意してみせたのです。
諸葛亮の名場面のひとつである「藁の船で矢を借りる」のエピソードですが、実際のところこれは創作。実は元となったエピソードは諸葛亮ではなく、孫権の功績なのです。
正史にあるエピソードはいかの通り。
赤壁の戦い直後、儒須で孫権と曹操が対峙していた際のこと。
船に乗って偵察に出た孫権は、曹操軍から弓の雨を射掛けられてしまいます。すると、あまりの激しさに、その矢の重みによって船が傾き、あわや転覆という事態になってしまいました。
そこで孫権は即座に船を反転させ、逆側で同じように矢を受けることでバランスを取り、安定したところで引き上げていったのです。
三国志演義では、これを元にして、諸葛亮の計略ということにしたのでしょう。
張飛は酒飲みじゃなかった?
■ 張飛は酒飲みじゃなかった?
張飛は酒飲みじゃなかった?
三国志の中でも人気の高い人物である張飛。
豪快で直情的、分かりやすく腕っ節の強い豪傑ということで、非常にキャラクターが立った人物だと言えるでしょう。
そんな張飛は酒癖の悪さがイメージとして強いのではないでしょうか。
劉備と呂布が同盟関係にあった時代には、徐州城の留守を任された際に、禁止されていた酒を飲んで部下に乱暴をしたことによって裏切りを招き、結果的に徐州を呂布に奪われることになります。
また、張飛の死因も、関羽の仇討ちで出陣する直前に、酒に酔いつぶれていたところをかねてから恨みを買っていた部下の范彊と張達に暗殺されてしまったということです。
ところが、こうした酒癖に関するエピソードは、実は正史には一切登場してこないのです。
ちょっとお馬鹿で単純だけど豪快で憎めない、という張飛のキャラクターを強調するために、演義において酒癖が悪いというエピソードが追加されたのでしょう。
とはいえ「張飛伝」には「張飛は身分の高いものには敬ったが、身分の低いものには蔑んだ言動をすることが多い」と書かれており、劉備からは「お前は部下に厳罰を与えすぎるから、そんなやり方ではいつか災いを招くぞ」と注意をうけたこともあります。
やはり張飛はもともと人の恨みを買いやすい人物であり、そうした部下からの離反のきっかけとして酒癖の悪さや酔いつぶれる、というエピソードが使いやすかった、という理由もあるのかもしれませんね。
まとめ
■ まとめ
まとめ
そんなわけで今回は、正史と演義でイメージがまるで異なるエピソードをいくつかご紹介しました。
よく知られている三国志演義のイメージから考えると、意外に思うものがあったのではないかと思います。
このように演義には、正史とは大きく異なる部分がたくさんあるのです。
とはいえわたしは、決して正史が正しくて、演義が間違っているなどということを言うつもりはありません。
正史も演義も、どちらも歴史に残る素晴らしい物語であることには違いありませんし、正史にあるエピソードを上手く改変し物語りに落とし込んだ演義の完成度は、他のどんな本にも勝る部分でもあります。
正史と演義の違いは、このほかにも数え切れないくらいありますので、その他のエピソードに関しても機会がありましたらまた紹介したいと思います。