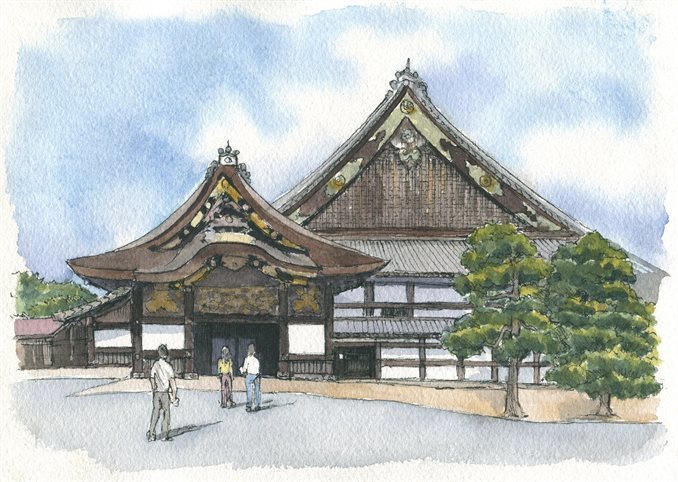卑弥呼の存在は三国志のおかげ?
■ 卑弥呼の存在は三国志のおかげ?
卑弥呼の存在は三国志のおかげ?
日本で初めて「王」として認知されているのが卑弥呼ですが、そもそも卑弥呼という存在そのものが実は三国時代の魏の文献のみにしか残されていないものです。「魏志倭人伝」がそれです。「魏」が記した「倭」の話。つまりは日本の話です。
そもそも、この時代は日本にはまだまだ書物という文化がなかったのか記録されていないのかは定かではありませんが、卑弥呼に関しては魏氏和人店がいわば唯一の手掛かり。
もしもですが、魏志倭人伝がなければ日本の歴史は少なからず変わっていたでしょう。学校の教科書でも縄文時代や石器時代を経て、一番初めに名前が出てくるのが卑弥呼ですが、もしも魏が卑弥呼のことを何も記録していなければ卑弥呼という存在がいたのかさえ分からなかったのです。
そもそも大和朝廷がどこにあるのかという、歴史学の長年の論争も魏志倭人伝による、魏から倭までどのように足を運んだのかという記述が重要視されている程。この事実だけでも、三国志と日本の関係が分かるのではないでしょうか。
徳川家康が天下統一出来たのは三国志のおかげ?
■ 徳川家康が天下統一出来たのは三国志のおかげ?
徳川家康が天下統一出来たのは三国志のおかげ?
戦国時代の最後の勝利者でもある徳川家康もまた、三国志の影響を大きく受けていたのは歴史マニアであればご存知なのではないでしょうか?
徳川家康と言えば関ケ原の合戦にて天下を掌握し、大坂の陣で豊臣家を滅ぼして文字通り天下統一を果たし、戦国という時代そのものを終わらせました。ですがそれはいわば晩年。関ヶ原の合戦の時点で徳川家康は既に60歳だったのです。
若い頃は織田信長と共に様々な戦いを共にし、時には苦渋にまみれたこともあるのですが、徳川家康が「完膚なきまでに負けた」と言える戦が三方ヶ原の戦いです。
この戦いは甲斐の虎・武田信玄が上洛するための通り道であった徳川家康と戦うことになるのですが、この戦は1572年。徳川家康も30代前半とまだまだ血気盛んな時期でした。
武田信玄の巧みな挑発に引っ掛かってしまった徳川家康は武田信玄に大敗北。必死の形相で居城である浜松城まで逃げ帰ったのですが、浜松城まで迫った武田信玄に用いた計略。
それは三国志ファンにはお馴染みの空城計だったのです。既に多くの兵士を失っていた徳川家康は籠城しても戦うだけの兵力は残っていませんでした。そこでイチかバチかで武田信玄相手に空城計。
相手が猪突猛進な武将であればこの作戦は失敗に終わっていたでしょう。ですが相手は武田信玄。武田信玄は思慮深い武将でもあったので徳川家康の空城計に対して「何かある」と察知して撤退したのです。その後武田信玄は病没。後に徳川家康が天下を握ったことを考えると、諸葛亮孔明の空城計は日本の歴史に大きな影響を与えたと言っても決して過言ではないでしょう。
「忠臣」という概念を生んだのも三国志?
■ 「忠臣」という概念を生んだのも三国志?
「忠臣」という概念を生んだのも三国志?
三国志の中でもトップクラスの人気を集める関羽。
関羽の人気は「曹操になびかなかった」「最後説得されても死を選んだ」といったように、「中心は二君に仕えず」という言葉を実践したからにほかなりませんが、このような考え方は鎌倉時代以降、日本にも伝わるようになっていたのです。
戦の世の中になると裏切りが当たり前になりますが、関羽のように主君は劉備だけと決め、最後まで曲げない。
これこそ「忠臣」として、日本の多くの武将に影響を与えているのです。
新田義貞など、鎌倉時代の武将でさえ関羽を意識していたのは、忠臣でありたいとの願いがあったからなのでしょう。つまり関羽は「忠臣像」を作ったと言っても過言ではないのです。
江戸時代の町人文化と三国志が?
■ 江戸時代の町人文化と三国志が?
江戸時代の町人文化と三国志が?
三国志が我が国に初めてもたらされた正確な時期は分かっていません。ですが平安時代には既に三国志の存在が記述されていますので、高貴な身分の人間は三国志に触れる機会があったのでしょう。
一方、一般市民に親しまれるようになるのは江戸時代からです。江戸時代に入ると三国志が広く普及していき、多くの人が三国志を楽しむようになったのです。
例えば歌舞伎。歌舞伎は江戸時代生まれの文化で、今日では無形文化財にまで登録されているほど貴重なものですが、江戸時代の歌舞伎の演目に三国志が確認されているのです。
歌舞伎がここまで長く続いているのは伝統もありますが、人気も関係しています。近年でこそ伝統ですが、まだまだ登場したての頃、当時の庶民にとっては未知数のものだったでしょう。
ですが三国志を上演するなど、地道に人気を高め、広く支持されるようになったからこそ高い人気を集めるようになり、今日まで続いている…と言っても大げさではないのです。
もしもですが、三国志がなければ歌舞伎もここまで人気を集めることなく、時代の流れの中で消えてしまっていたかもしれないことを考えると、三国志は日本文化にも影響を与えている…と考えても大げさではありません。
幕末維新も三国志のおかげ?
■ 幕末維新も三国志のおかげ?
幕末維新も三国志のおかげ?
前途したように戦国時代を終わらせたのは紛れもなく徳川家康。その後、260年に及ぶ「徳川時代」となりますが、幕末、様々な思惑の中で江戸幕府は新政府に屈服することになります。
その際、倒幕は様々な形で機運が高まるのですが、水戸学が大きな影響を与えたとも言われています。
水戸藩と言えば水戸黄門でも有名で徳川御三家の一つなのですが、思想的には幕府という形ではなく、新しい形を模索していたのですが、徳川家康が亡くなった際、彼の愛書が居城であって駿府(今の静岡)から水戸藩と尾張藩に移されたのですが、その中には三国志も含まれていると近年発表されたのです。
徳川家康を書をたしなんでいましたし、先の空城計も知っていたからこそ出来たのでしょう。
つまり、手元に三国志の文献があったのです。
そして亡くなった際にはしっかりと勉強してもらいたいとの思いから、自分の子供たちに託したのですが、水戸藩から徳川ではなく、新しい世の中…といった考え方が生まれたのは皮肉なものとはいえ、いわゆる「水戸学」と呼ばれている新しい時代の考え方には三国志の影響もあるかもしれません。
水戸に運ばれたということは、水戸の人間は三国志を読んでいるのです。そこで様々なことを考えても決して不思議ではありません。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志は娯楽作品である一方、日本の歴史にも様々な形で寄与していますので、もしも三国志がなかったら日本の歴史もまた、微妙に違うものになっていたかもしれませんね。