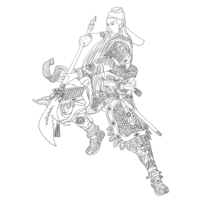貯めこんだ食料、30年分
■ 貯めこんだ食料、30年分
貯めこんだ食料、30年分
朝廷の独裁者として、思うがままに振舞っていた董卓ですが、こういう人にかぎって恐怖におびえているものなのかもしれません。彼は新首都・長安の東に、頑丈な砦(とりで)を作り、自らの拠点としました。朝廷の最高権力者にもかかわらず「首都にいては危ない」というのですから、身の危険を感じていたのでしょう。砦を造ってそこに引きこもったのです(最後はそれでも、殺されてしまうのですが)。
砦は高さが7丈(約21メートル)もあり、董卓はここに30年分の食料をため込んだといいます。これだけの私腹をこやすのに、人民からどれだけしぼり取ったのでしょうね……。この鉄壁の防御と莫大な物資をほこる砦で、董卓はこう言ったそうです。
「もし事が上手く運べば、広く天下を平定いたそう。だが成功しなくとも、この地を守っていれば老後も安泰だ」
独裁者の董卓にしては、なんだか弱気な発言にも思えますが……軍人として多くの武勲を立てた彼は、本来頭のいい人物です。自分の強引な政治では、必ずしも天下を従わせられないことを、心のどこかで理解していたのでしょう。
勇者あらわる! 董卓暗殺計画!
■ 勇者あらわる! 董卓暗殺計画!
勇者あらわる! 董卓暗殺計画!
独裁者が強引かつ乱暴な政治をしていれば、暗殺の危機が訪れてもおかしくありません。
そんな董卓を討ち果たそうと、伍孚(ごふ)という男が立ち上がりました。
伍孚は大将軍・何進(かしん)に引き立てられた男で、何進死後に始まった董卓の暴政に非常な怒りを覚えていました。あるとき伍孚は、董卓に従うふりをして面会に行きました。服の下にヨロイを身につけ、刀を隠し持っての訪問―――まさに独裁者と刺し違える覚悟です。
伍孚は董卓のスキを伺って、刀を出して刺し殺そうとします。ただの独裁者であれば、ここで討たれていたでしょうが、董卓もさるもの。すばやく攻撃をよけて、暗殺の危機をかわしたのです。若いころから武勇に秀でていた、董卓ならではのエピソードでしょう。
かくして董卓打倒に失敗した勇者・伍孚は、あわれにも処刑されたのです。
さらには三国志のキーパーソンとなる知恵者も、董卓暗殺を試みます。
その男こそ、後に曹操の参謀として歴史に名を残す荀攸(じゅんゆう)でした。彼もまた大将軍・何進に引き立てられたものの、それに続く董卓の独裁政権に強い反感を持ち、暗殺計画に加わったのです。しかしこの計画もまた未遂に終わり、荀攸は投獄されました。本来ならばこのまま死刑になってしまうところですが、執行される前に董卓が討ち果たされたため、荀攸は運よく助かったのです。
伍孚も荀攸も、董卓の政治に反対していたことはもちろん、「大将軍・何進に起用された人材」という点で一致しています。死んでもなお何進の存在感は大きく、何進グループが董卓に反発し続けたことがよく分かります(反董卓連合の盟主・袁紹からして、何進の一派でした)。
こう考えると、董卓が強引にでも少帝を廃立・殺害したことも、理由が無いことではなかったのですね。何進の甥である少帝(および少帝の母である何太后)を生かしておいては、こうした何進グループの残党が力をたもち、董卓のさらなる難敵になっていたでしょうから……。
さらなる暗殺計画 王允の策謀
■ さらなる暗殺計画 王允の策謀
さらなる暗殺計画 王允の策謀
このように、武人としても優れた戦闘力を持ち、鉄壁の砦に立てこもる董卓。
もはやつけ入るスキはないのか……と思いきや、こんな彼にも落とし穴があったのですね。
都ではさらなる董卓暗殺計画が、ひそかに進行していました。その首謀者は、他ならぬ董卓が政治をまかせていた王允(おういん)という男でした。
董卓に政務をまかされた王允とは、何者か?
彼は若くして正義漢として名を上げた政治家で、不正をゆるさぬ剛直の士でした。武芸の訓練もおこたらぬ人で、黄巾の乱(こうきんのらん)の鎮圧でも活躍し、董卓と因縁のある名将・皇甫嵩とともに多くの敵軍を降伏させたといいます。
このとき王允は、ある重要な手紙を見つけます。それはなんと、宦官の実力者である張譲(ちょうじょう)が、黄巾軍と内通(注)していた証拠だったのです。王允はこの裏切りを摘発しますが、返って張譲の恨みを買い、長らく投獄されてしまうこととなりました(宦官が幅を利かせていた時代、彼らに逆らうことは命がけでした)。
(注)内通(ないつう)……味方のふりをして、こっそり敵側に通じること。
その後、大将軍・何進にまねかれて政界に復帰しますが、その何進も宦官に討たれてしまいます。代わって権力者となった董卓にも王允は用いられ、三公のひとつである司徒(しと/注)の位につけられます。前にも述べましたが、董卓は自分の政権基盤を強化するため、「名士」(社会的名声の高い知識人)を積極的に起用したのです。
王允は董卓政権下で、大変重用されました。反董卓連合軍の攻撃にそなえ、董卓は長安に都をうつし、自らは洛陽に残ります。このとき董卓不在の長安の政務を任されたのが、王允だったのです。
(注)司徒(しと)……政府でもっとも高い位のひとつ。三公とは最高位にあたる3つの官職のこと。
王允は「あの男」に声をかけた
■ 王允は「あの男」に声をかけた
王允は「あの男」に声をかけた
こうして董卓に従い、その政権運営を担当していた王允ですが……なんだかおかしいですよね?
だってこの人、本来は「不正をゆるさぬ剛直の士」として知られた男です。さらには何進に引き立てられた政治家でもあり、そうやすやすと董卓に従うタイプの人間ではないはずなのです(何進グループの有力者の多くが、董卓に反発したことはお話しして来たとおりです)。
そう。王允は表向きは董卓に従ったものの、心服していたわけではなかったのです。董卓の暴政に絶望した彼は、ひそかに董卓の排除を決意し、暗殺計画をねりはじめたのです。
とはいえ、董卓は権力者であるうえに、武勇にもすぐれているため、暗殺は簡単なことではありません。そこで王允は、戦いに強く、なおかつ董卓の近くにいる男に協力を求めました。こうして暗殺計画実行犯として白羽の矢が立ったのが、董卓軍の猛将・呂布だったのです。
とはいえ、呂布とくれば董卓と「親子の誓い」まで交わした、側近中の側近。そんな人物にどうやって裏切りを決意させ、暗殺計画に引きずり込むのか? 王允にいかなる秘策があるのか? 次回は、董卓の悲惨な末路をご紹介します。