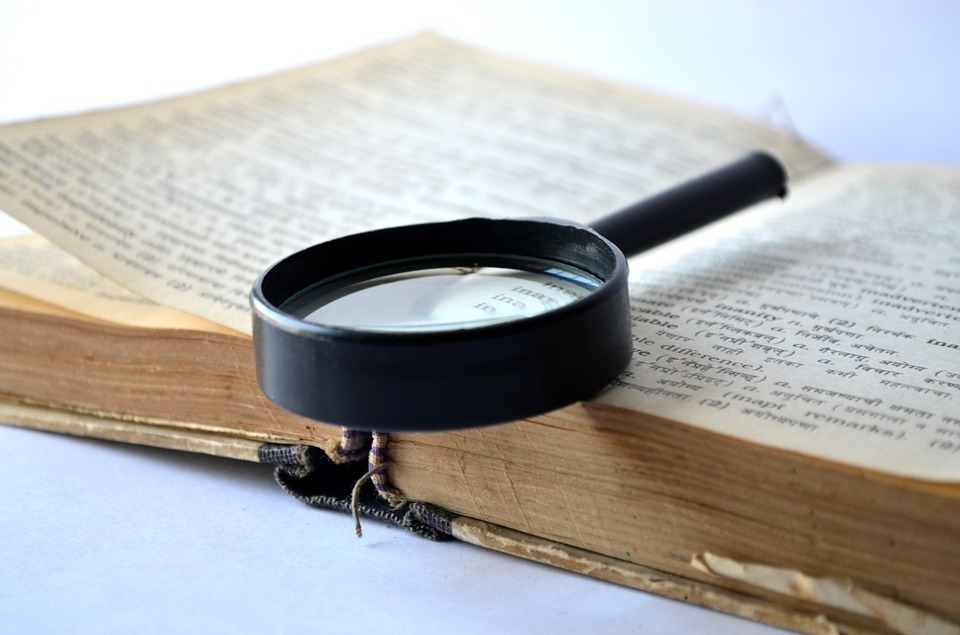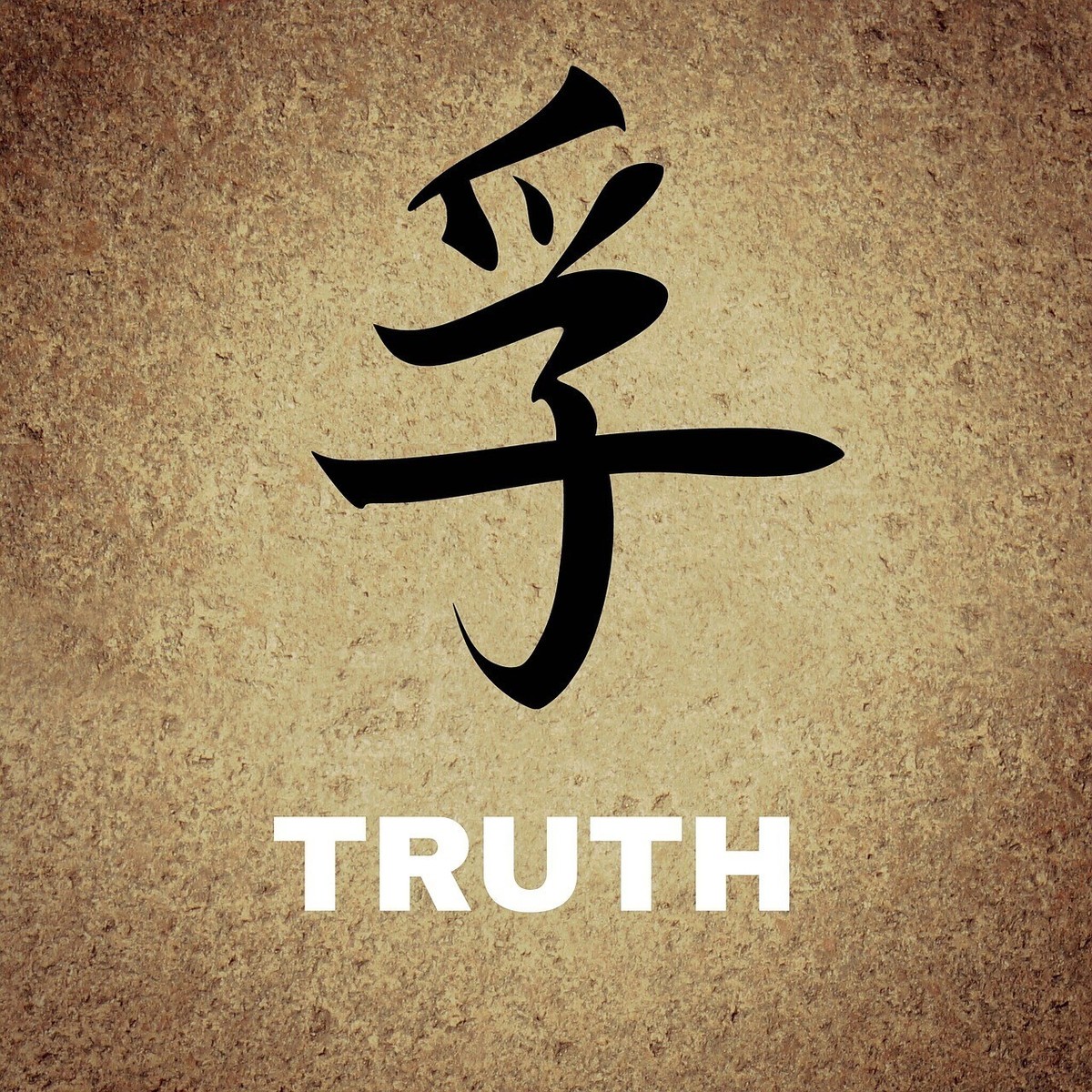玉璽
■ 玉璽
玉璽
「玉璽」とは、中国の歴代王朝や、その皇帝に代々受け継がれてきた皇帝の用いる玉製の印璽のことで、正式には「伝国璽」と呼ばれています。帝権の象徴と考えられています。
三国志に登場する玉璽(伝国璽)は、秦の始皇帝が作らせた物で、漢王朝滅亡後、魏、晋や隋、唐といった王朝まで引き継がれました。
大きさは四寸四方、つまみには五匹の龍が彫られています。印面には「受命於天、既寿永昌」と刻まれています。「命を天に受けたれば、すでに寿にして永く昌(さか)えん」という意味です。
ちなみに前漢から帝位を簒奪した王莽は、この玉璽を得る際に投げつけられてつまみの龍の部分が欠けたという言い伝えがあります。
明の時代には、「三国志玉璽伝」という、玉璽の流伝を柱にした三国志の物語も創作されています。
孫堅が玉璽を発見する
■ 孫堅が玉璽を発見する
孫堅が玉璽を発見する
この玉璽に注目が集まるのは、董卓が洛陽から長安に強制遷都を行った際のことになります。董卓は洛陽を焼き払い、皇帝を擁したまま西の長安に移ります。反董卓連合軍が迫っていたからです。
洛陽に入った孫堅は、漢王朝の宗廟をはき清め、いけにえを捧げて祭りました。翌日の明け方に、井戸から五色の気がたちのぼったので、兵士たちは水を汲もうとせず、孫堅は井戸の中を探らせました。すると玉璽が見つかったのです。
印面には八字が刻まれており、上部の紐をかける所には五匹の龍が組み合わされ、上の一匹は角が欠けていました。まさに正真正銘の玉璽です。
三国志正史「呉書」の記録によると、この玉璽は、宦官の張譲らが皇帝を擁して出奔した際に、側近たちがバラバラになってしまい、玉璽の保管係が井戸に投げ込んだそうです。
董卓が洛陽を占拠したのは、その後のことになります。
つまり朝廷を牛耳った董卓は、玉璽を見ることなく、その所在もわからぬまま遷都したことになるのです。董卓のことですから、あまり関心も抱かなかったのかもしれません。
しかし董卓に擁立された献帝は、玉璽なしで皇帝に即位したことになります。これは問題ですね。
玉璽はいくつあったのか
■ 玉璽はいくつあったのか
玉璽はいくつあったのか
玉璽には何種類かあったようです。「天子の六璽」というものがあり、用途に応じて封印に用いたもので、刻まれている文字も異なりました。「皇帝之璽」「皇帝行璽」「皇帝信璽」「天子之璽」「天子行璽」「天子信璽」と刻まれている六璽です。
伝国璽はこれに含まれないので、玉璽は七つあったことになります。この話を信用するとなると、伝国璽には「受命於天、既寿且康」と刻まれており、孫堅が発見した玉璽とは二字異なります。
ちなみに呉が晋に降伏した際に、皇帝である孫皓が晋に差し出した玉璽は、六璽であり、ここには伝国璽はなかったようです。そのため、孫堅が伝国璽を発見したという記述は誤りではないかという説もあります。
呉書は建国の正統性を説くために、孫堅が玉璽を発見したと記していますが、三国志正史の注釈を行った裴松之は、忠烈の名が高かった孫堅が伝国璽を発見しながら隠し持っていたというのはおかしいと異を唱えています。
果たして孫権が手に入れた玉璽は、「天子の六璽」だったのか、始皇帝から伝わる「伝国璽」のどちらだったのでしょうか。
三国志演義の孫堅
■ 三国志演義の孫堅
三国志演義の孫堅
三国志演義でも洛陽に入った孫堅が玉璽を発見したことに触れています。そこで孫堅は野心を抱き、それを故郷に持ち帰ろうとするのです。これを反董卓連合の盟主である袁紹が気づき、孫堅から玉璽を奪い取ろうとして劉表の軍勢を差し向けます。
この時の恨みを孫堅は忘れず、袁術の要請を受けて、孫堅は劉表を攻めます。呉から出陣した孫堅は、樊城の黄祖を破り、さらに蔡瑁を破って襄陽を囲いました。劉表配下の蒯良は襄陽近くの峴山に兵を潜ませ、孫堅をおびき出して射殺しました。
その後、孫堅軍は袁術の勢力下に入り、孫堅の息子である孫策はしばらくして、袁術から兵を借りて江東を攻める際に、玉璽を引き換えにするのです。
玉璽を得た袁術は皇帝に即位しますが、諸侯の反発にあって、すぐに滅亡してしまいます。
三国志演義では孫堅も袁術も僭国を志した不忠の象徴なのです。
玉璽の行方
■ 玉璽の行方
玉璽の行方
孫堅が手にした玉璽の行方については諸説あります。
楽資の「山陽公載記」によれば、皇帝になる野心のあった袁術が、孫堅の妻を人質にして、玉璽を奪い取ったとあります。
このまま孫皓の代まで引き継がれたという説もありますし、袁術に渡った玉璽は滅亡後に徐璙によって漢王朝に返却されたという説もあります。さらには劉備(玄徳)が皇帝に即位する際に、漢水の川底から玉璽が見つかったという説もあるぐらいです。
自分たちの王朝の正統性を主張するためには、玉璽の存在は必要不可欠なものだったことは確かなようです。かなり偽物の玉璽も出回っていたと考えられます。ほとんどの人間が本物の玉璽を見たことがなく、またそれを証明することはできなかったことでしょう。皇帝が複数いたように、本物の玉璽であるとされたものも複数あったのではないでしょうか。
ちなみに曹丕が献帝より禅譲を受ける際に、皇后である曹丕の妹・曹節が、使者に玉璽を投げつけたという記録もありますので、漢王朝から魏王朝に引き継がれた玉璽も間違いなくあったことになります。
まとめ・孫堅は本物の玉璽を手にしていたのか
■ まとめ・孫堅は本物の玉璽を手にしていたのか
まとめ・孫堅は本物の玉璽を手にしていたのか
三国志正史でも三国志演義でも、孫堅が玉璽を手に入れたことは記されていますので、おそらく入手したことは確かでしょう。
ただし、目的は定かではありません。皇帝となる野心を孫堅ほどの忠義の士が持っていたとは、考えにくいので、董卓を倒し、皇帝をそこから開放した後に返却するつもりだったのかもしれません。
この場合は、他の皇帝を擁立する予定だった袁紹に渡すことは危険だと判断したはずです。袁紹に対抗していた袁術に玉璽を託していたことも考えられます。そのため、袁術は孫堅の死後、孫策を重用したのかもしれません。孫策が息子だったらと良かったと、高い評価をしています。(その割になかなか太守に任命せず、約束を反故していますが)
袁術の死後は、袁術の遺族は孫策に保護され、袁術の娘は孫権の後宮に入って存在感を示していますので、玉璽を介して袁術と孫氏の繋がりは強化されたのかもしれませんね。