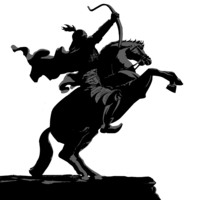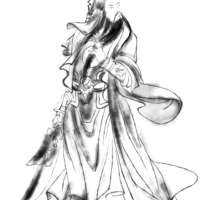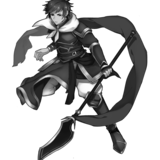五虎大将軍(ごこだいしょうぐん)とは
■ 五虎大将軍(ごこだいしょうぐん)とは
五虎大将軍(ごこだいしょうぐん)とは
五虎大将軍とは、劉備(玄徳)が諸葛亮(しょかつりょう)の進言により、信頼と過去の実績をもとに武将五名に授けた称号になります。また、五虎大将軍は蜀の軍事における中心的な役割を果たしました。
劉備(玄徳)より五虎大将軍に選ばれた5名は、関羽(かんう)・張飛(ちょうひ)・馬超(ばちょう)・黄忠(こうちゅう)・趙雲(ちょううん)と蜀の中でも猛将ぞろいです。
五虎大将軍をまとめる筆頭には、劉備(玄徳)と義兄弟であり信頼と実績のある関羽が任命されました。
五虎大将軍は「五虎大将(ごこたいしょう)」「五虎将軍(ごこしょうぐん)」「五虎将(ごこしょう)」などと略される場合もあります。
ところが、五虎大将軍は後に三国志演技で物語を面白くする為に作られた創作であり、実際には存在しなかった役職のようです。
五虎大将軍の元になったのが、「蜀書第6巻 関張馬黄趙伝」と言われています。
「蜀書第6巻 関張馬黄趙伝」を参考に関羽・張飛・馬超・黄忠・趙雲の5人を五虎大将軍としました。
実際には関羽が前将軍、張飛が右将軍、馬超が左将軍、黄忠が後将軍、趙雲は他の4人よりも低い役職だったようです。
趙雲が他の4人と同じ位になったのは関羽・張飛・馬超・黄忠がいなくなった後の、超雲が晩年の頃のようです。
五虎大将軍メンバー
■ 五虎大将軍メンバー
五虎大将軍メンバー
関羽(かんう)
■ 関羽(かんう)
関羽(かんう)
関羽、字は雲長(うんちょう)。司隷河東郡解県(現在の山西省運城市塩湖区解州鎮常平村)出身と言われています。
五虎大将軍(関羽、張飛、黄忠、馬超、趙雲)の筆頭です。
劉備(玄徳)、張飛と桃園の誓いを結び義兄弟であり、黄巾討伐より行動を共にし蜀の建国に尽力した人物です。
反董卓連合軍に参加していた時は董卓軍の猛将華雄(かゆう)を倒す。曹操に敗れ、劉と別れ離れになり曹操の捕虜となった際は、曹操軍として官渡の戦い(かんとのたたかい)に参戦、袁紹(えんしょう)軍の猛将顔良(がんりょう)を倒すなどしています。
関羽は見事な鬚髯(鬚=あごひげ、髯=ほほひげ)をたくわえていたため「美髯公(びぜんこう)」とも呼ばれます。
敵方でありながら張遼(ちょうりょう)、徐晃(じょこう)とは親交があるなど敵味方問わず人を惹きつける人間的魅力もあります。
実は、中国では「商売の神様」として祭られています。日本では横浜の関帝廟(かんていびょう)が有名です。
張飛(ちょうひ)
■ 張飛(ちょうひ)
張飛(ちょうひ)
張飛、字は益徳(えきとく)、三国志演義では翼德(よくとく)。幽州涿郡(現在の河北省涿州市)の出身と言われています。
五虎大将軍(関羽、張飛、黄忠、馬超、趙雲)の一人です。
劉備(玄徳)、張飛と桃園の誓いを結び義兄弟であり、黄巾討伐より行動を共にし蜀の建国に尽力した人物です。
曹操軍から追撃を受けた際、長坂橋で曹操軍を単騎による大喝一声して足止させたことにより、劉備(玄徳)軍が撤退できたエピソードは有名です。
短気で思ったらすぐ行動するタイプ。また、大酒呑みであり、それが災いして失敗することもありました。呂布に匹敵する武力の持ち主です。
馬超(ばちょう)
■ 馬超(ばちょう)
馬超(ばちょう)
馬超、字は孟起(もうき)。司隷扶風郡茂陵県(陝西省興平市)の出身と言われています。
五虎大将軍(関羽、張飛、黄忠、馬超、趙雲)の一人です。
馬超は剛力の持ち主で若い頃から武勇に優れていました。その雄姿から「錦馬超」(きんばちょう)として称えられています。
馬超は、後漢の名将馬援(ばえん)の子孫と称する一族の出身です。父は馬騰(ばとう)になります。
父親の馬騰は曹操と対立していており、曹操暗殺計画に加担していたことが曹操にばれて一族のほとんどを曹操に謀殺されてしまいます。唯一生き残った馬超と従弟の馬岱(ばたい)は共に、復讐の為に兵を起こしました。
潼関の戦にて馬超は圧倒てきな強さで曹操軍を蹴散らしていきます。その中で行われた、許褚(きょちょ)との一騎討ちは有名です。
優勢に進めてきた馬超軍ですが、賈詡(かく)の離間の計(りんかんのけい)により、韓遂(かんすい)の裏切りにより、形勢が逆転し馬超は敗走していきます。その後、張魯の元に身をよせ、そして劉備(玄徳)の配下となります。
黄忠(こうちゅう)
■ 黄忠(こうちゅう)
黄忠(こうちゅう)
黄忠、字は漢升(かんしょう)。荊州南陽郡(現在の河南省南陽市)の出身と言われています。
五虎大将軍(関羽、張飛、黄忠、馬超、趙雲)の一人です。
黄忠は60歳を過ぎた老将でありながら、弓の名手で敵将を一騎討ちで討ち取るなど、老いても勇猛果敢な活躍をしました。
例えとして、中国では老いてますます盛んな人を老黄忠(ろうこうちゅ)と呼ぶそうです。
もともと黄忠は韓玄(かんげん)の配下でした。関羽率いる劉備(玄徳)軍が長沙(ちょうさ)に攻めてきた際に、関羽と一騎討ちをしており互角の戦いを繰り広げました。韓玄に劉備(玄徳)軍と内通しているのではと疑われ、捕えられてしまい処刑されそうになった際、同じく韓玄の配下の魏延(ぎえん)が反乱を起こし韓玄の死亡により、劉備(玄徳)の配下となりました。
劉備(玄徳)の配下になってからは、漢中攻略時に、張郃(ちょうこう)・夏侯尚(かこうしょう)を撃破したり、定軍山の戦いで夏侯淵(かこうえん)を討ち取るなど活躍しました。
趙雲(ちょううん)
■ 趙雲(ちょううん)
趙雲(ちょううん)
超雲、字は子龍(しりゅう)。冀州常山郡真定県(現在の河北省石家荘市正定県)の出身と言われています。
五虎大将軍(関羽、張飛、黄忠、馬超、趙雲)の一人です。
もともと公孫瓚(こうそんさん)の配下でした。公孫賛が青州(せいしゅう)の袁紹と戦いで、田楷(でんかい)の援軍として派遣された劉備(玄徳)の騎兵隊長となったことが劉備(玄徳)との出会いです。その後、趙雲は兄の喪のために故郷に帰ることとなり公孫賛の元を離れます。
そして趙雲は、袁紹の元に居た劉備(玄徳)と会い劉備の配下となった。
長坂の戦いでは、阿斗(後の劉禅(りゅうぜん))と甘皇后を救出しに曹操軍の大群に単騎で乗り込み救出するエピソードが有名です。
劉備(玄徳)、関羽、張飛亡き後、諸葛亮と共に魏軍(北伐)討伐などをおこないました。タレント不足な蜀の中で諸葛亮と共に劉禅(りゅうぜん)を支えた人物です。