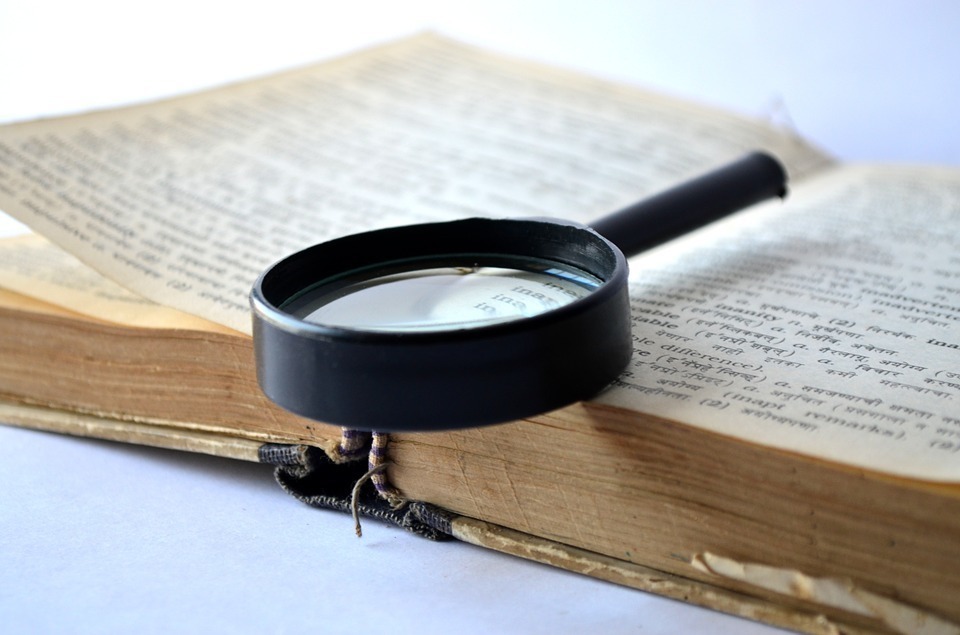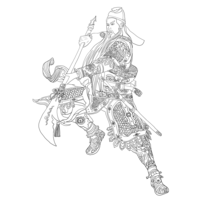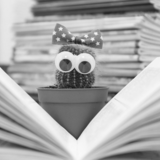三国時代の武器について
■ 三国時代の武器について
三国時代の武器について
戦で勝利をもたらすうえで重要となってくるのが武器です。三国時代では様々な武器が用いられました。ここでは三国時代でよく用いられた五つの武器について紹介したいと思います。
矛「ぼう」
■ 矛「ぼう」
矛「ぼう」
矛は長い柄に両刃の穂先を付けた武器です。日本の薙刀と似た感じですが。薙刀は斬る、払うといった動作を目的に作られているのに対して、矛は斬る、突き刺すことがメインとした武器です。馬に乗っている際によく用いられました。一対一で戦う際も剣に比べて遠くから攻撃できるため非常に愛用されていた武器の一つです。
戟「げき」
■ 戟「げき」
戟「げき」
矛の横に相手をひっかけて倒すための刃がついています。遠い間合いからでも攻撃ができ、矛よりも攻撃の幅が広がるので、三国時代に最も使われていたのではないかといわれている武器です。
刀「とう」
■ 刀「とう」
刀「とう」
いわゆる「かたな」のことで、接近戦で使われる武器です。接近戦で主に使われます。剣との違いは、剣は刃が両側についているのに対して刀は刃が片方にしかついていないところです。
弓「きゅう」
■ 弓「きゅう」
弓「きゅう」
いわゆる「ゆみ矢」です。騎兵用の弓と歩兵用の弓は違い、騎兵用の弓の全長は70~90センチであるのに対し、歩兵用の弓は倍ほどあり170センチに達していたといわれています。
弩「ど」
■ 弩「ど」
弩「ど」
弓より複雑な作りでクロスボウといったほうがピンとくるでしょうか。引き金を引いて矢を連発して放つことができる極めて殺傷能力が高い武器です。この時代にすでに足で弓を踏んで両手で弦をセットするものがありました。
三国時代の一騎打ちについて
■ 三国時代の一騎打ちについて
三国時代の一騎打ちについて
三国時代では一騎打ちが多数存在しています。それにより、呂布(奉先)や関羽(雲長)がいかに一騎打ちに強いか物語られています。ところが実際は、あまり一騎打ちは行われていなかったというのが一般的な説です。
大将が一騎打ちをして負けたら戦争が終わりというのはなかなか考えづらく、偉いのであれば後方で全軍の指揮にあたるというほうが考えられやすいですよね。
しかし一騎打ちがあちらこちらで行われていたとされているのは「その方が見ごたえがある」からでしょう。
もちろん一騎打ちがなされた記述もあります。特に有名な一騎打ちは呉の皇帝となった孫権(仲謀)の兄である孫策(伯符)と太史慈(子義)の戦いです。孫策(伯符)は軍の総大将だったため言ってみたら敗れたら国が亡ぶといっても過言でもない状況でした。そんな状況で一騎打ちをしたのでこの対戦はもはや伝説となっています。
三国時代の兵士の数について
■ 三国時代の兵士の数について
三国時代の兵士の数について
三国志ではいくつもの戦争がありました。ところが数十万規模兵を動かすほどの大戦となるとそうはありませんでした。とはいえそのような大戦では数が盛られているケースが多々あります。
その中でも一番誤差があったのが赤壁の戦いと言われています。赤壁の戦いでは魏の総大将曹操(孟徳)が「80万の軍勢を率いて攻め込む」というシーンがありますが、実際は20~50万程度の軍勢だったのではないかという説が有力視されています。20万も50万もとんでもない差で誤差とは言えないほどですよね。
もはや正確な数値はどうでもよく、いかに伝説化するために数を盛るというほうが重要みたいです。
実際、三国志を楽しむうえあえて正確な数値を求めない方がいいと思います。「史実は違うんでしょ」と冷めた目で見るよりも「こんな少人数で大軍を制したのか!すごい!」と単純に物語を楽しんだほうが面白くなります。
最初は物語をうのみにし、三国志にはまったら「これは違うのではないか」「本当はどうだったんだろう」ということに着目してみるのがお勧めです。
三国時代の王が囲う宮女と近くにいる宦官について
■ 三国時代の王が囲う宮女と近くにいる宦官について
三国時代の王が囲う宮女と近くにいる宦官について
三国時代の王の子作りはスケールが違います。三国時代を終わらせた皇帝司馬炎(安世)には5000人の宮女を囲っていたといわれています。さらにそれだけでなく呉を亡ぼした際、呉国のラストエンペラー・孫晧(元宗)の囲っていた宮女5000人まで自分の救助にしてしまいました。10000人の宮女を抱えてもはや何がしたいのかという感じです。
さらにその宮女が自分以外の子供を作らないように宮廷の奥で働く男は宦官と言って去勢(男性の生殖器を切除)しなければいけないほどでした。しかしこの宦官は身分が低いものではなく、皇帝の側近ともいえるほど近しい者までいました。
司馬炎(安世)ほど宮女を囲っていた皇帝は存在しませんが、この時代の皇帝になったらそれほどの暮らしができるということです。こんな世の中であるのであれば「出世したい!」と思う男性は多いことが想像できますね。
三国志と三国志演義の違いについて
■ 三国志と三国志演義の違いについて
三国志と三国志演義の違いについて
三国志を知りたいと思った人が必ずと言っていいほど直面する問題は「三国志」と「三国志演義」の違いです。三国志は正史で三国志演義は小説です。そのため三国志演義ではあ派手な演出が施されています。三国志演義は「七実三虚」=7割が真実で3割が虚構と言われているくらいで蜀=劉備軍を正当王朝、魏=曹操軍を適役としています。
三国志演義ができたのは14世紀初頭くらいなのでその時代の感性や願望も混ざっている読み物としてとらえたらいいと思います。
日本でよく読まれる三国志の本について
■ 日本でよく読まれる三国志の本について
日本でよく読まれる三国志の本について
日本でよく読まれる三国志の本を挙げると吉川英治の三国志、北方謙三の三国志、横山光輝の三国志が代表的でしょう。それぞれに特徴があるので簡単に紹介します。
まず吉川英治の三国志ですが、これはまさに日本版三国志の生みの親といってもいい存在です。三国志演義を元に作られた新聞小説ですがさらに劉備の恋物語を仕立てるといった独自のストーリーも加えています。
北方謙三の三国志は正史「三国志」に基づいて構成されているため吉川英治の三国志より史実に忠実です。しかしもちろん独自の目線からの描写もあり、三国時代の真の英雄は曹操(孟徳)という考えが随所にちりばめられています。
横山光輝の三国志はマンガです。そのため彼の三国志の絵をCMやラインスタンプなどで一度は目にしたことがある人も多いことでしょう。この作品は吉川英治の三国志を元に独自の解釈を織り交ぜています。全60巻という大作ですが、三国志を読もうという人にとって入りやすいのではないかと思います。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志や三国時代にまつわることについて記載しましたがいかがだったでしょうか。「え?そうなんだ」とか、もっと三国志について知りたいと思っていただけたら幸いです。
正史だとしても歴史なのできちんと伝わっていなかったり解釈の違いによってずれが生じることがあります。しかし「こうなのではないか」「自分はこう捉えた」といった独自の視点で三国志を楽しむことがより深い知識を生むことだと思うのでまずは自由に知識を取り入れてそこから取捨選択していくという形でいいと思います。