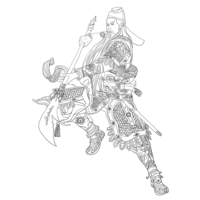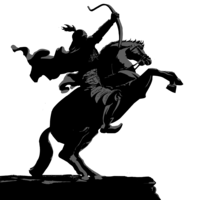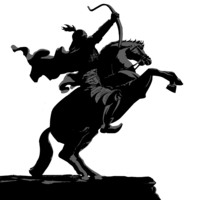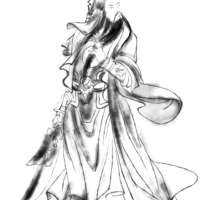魏を滅ぼす最大のチャンス
■ 魏を滅ぼす最大のチャンス
魏を滅ぼす最大のチャンス
218年、劉備(玄徳)は漢中から兵を出し西から魏へ攻め込みました。一方関羽(雲長)もその動きに呼応する形で本拠地である光陵の守備を麋芳(子方)に任せ南から魏へ攻め込みました。この頃劉備(玄徳)率いる蜀の戦力がもっとも整っている頃で、魏であっても、容易に退けることが出来ませんでした。
長江を超え北上してきた関羽軍が樊城を包囲。荊州北部では蜀につき曹操(孟徳)率いる魏に反旗を翻す豪族も増えました。さらには援軍として送られてきた于禁(文則)はあっさり降伏してしまったのです。それにより守将の曹仁(子考)もいよいよ落城を覚悟しなければいけないという所まで追いつめられていました。そしてこの樊城が落とされたら赤壁の戦いでの敗戦後、呉に攻め立てられたとき同様に最大のピンチを迎えます。
司馬懿(仲達)の功績が光った
■ 司馬懿(仲達)の功績が光った
司馬懿(仲達)の功績が光った
樊城が落ちれば許都もいよいよ危なくなると思った曹操(孟徳)は関羽(雲長)の攻撃を恐れて首都を北方へ移すべきかという検討すらしていたのです。それほどまでに魏は追いつめられていました。
しかしここで立ちはだかったのが後に孔明のライバルとなる司馬懿(仲達)。彼は「蜀が荊州に居座っていることに不満を持っている孫権(仲謀)の心理に付け込んだのです。孫権(仲謀)に対し江南の支配権を与え、関羽(雲長)を後方から襲わせるという策を授けました。
呉は呂蒙(子明)の部隊が江陵の留守を任されていた麋芳(子方)を攻め立て降伏させました。南方からの物資補給地点を占領された関羽軍はすぐに兵糧不足に陥るという危険にさらされてしまったのです。
魏と呉に攻め込まれた関羽(雲長)
■ 魏と呉に攻め込まれた関羽(雲長)
魏と呉に攻め込まれた関羽(雲長)
もうすぐで樊城を落とすことが出来るという関羽(雲長)だったが一気にピンチに追いやられました。関羽(雲長)に残された道は樊城を一気に落とすか、すぐに退散するという手しかありません。
しかし魏軍の徐晃(公明)が関羽(雲長)の退路を断つ動きに出たため関羽(雲長)は焦り、樊城の包囲を解きました。
落とされる寸前まで陥った樊城を守り抜くことが出来ただけで司馬懿(仲達)からしてみたら最低限の働きはできたと言えたでしょう。しかし、事はもっとうまくいきました。
魏軍は援軍の到着により関羽(雲長)を追撃、呉軍も関羽(雲長)の拠点を次々と攻略していったのです。関羽(雲長)の軍は度重なる急襲により戦意を喪失し、脱走兵まで出る有様でした。南の当陽を目指したが呉の大軍が待ち構えていたため進路を西に変え麦城に籠ったのです。
陸遜にしてやられた
■ 陸遜にしてやられた
陸遜にしてやられた
こう見ると関羽(雲長)は司馬懿(仲達)にしてやられたという感がありますが、そもそもこの樊城の戦いでの影の支配者は陸遜(伯言)です。元々陸口の守備をしていた呂蒙(子明)に病気と称し陸口の守備を陸遜(伯言)に譲りました。関羽(雲長)は陸口に赴任した陸遜(伯言)からの挨拶状を見て「こいつは江陵を攻めてこない」と侮ったのです。それゆえ樊城攻略に人員を割いた次第です。それからは上記に挙げたように補給路、退路を断たれる始末となったのです。
よく「関羽(雲長)は呂蒙にやられた」と言われることがあります。しかし、そこには陸遜(伯言)の計略が大いに関わっていて、さらには司馬懿(仲達)の陰謀もあったのです。
ちなみにですが、この呂蒙(子明)は病死したわけだが関羽(雲長)が呪い殺したという逸話も多く残っています。
実は味方からも裏切られていた
■ 実は味方からも裏切られていた
実は味方からも裏切られていた
さて、麦城に籠った関羽(雲長)ですが、孟達(子敬)と劉封に援軍を要請していました。しかし、孟達(子敬)は「焼け石に水だ」と言って援軍を断りました。劉封は自身が劉備(玄徳)の養子になる際に関羽(雲長)が養子になることを反対したということを恨んでいて援軍を出しませんでした。
麦城の兵糧がつきかけたので関羽(雲長)は養子の関平らと共に脱出を図ったが、呉軍の伏兵に生餌獲りにされ、斬首されてしまったのです。
関羽(雲長)を斬首したことで劉備(玄徳)の怒りの矛先が向くのを恐れた孫権(仲謀)は関羽(雲長)の首を曹操(孟徳)に送りました。しかしここでも司馬懿(仲達)はこの企みを見抜き、関羽(雲長)を丁重に葬るようにさせました。
当然のことながら劉封は関羽(雲長)を救援しなかった罪により劉備(玄徳)の手により処刑された。
「兄弟は手足のごとし、妻子は衣服のごとし」というほど兄弟という存在を重く見ていた劉備(玄徳)にとって子供より関羽(雲長)の存在の方が大きかったというのは言うまでもありませんね。
関羽(雲長)が亡くなった結果
■ 関羽(雲長)が亡くなった結果
関羽(雲長)が亡くなった結果
関羽(雲長)の死は一将軍が亡くなったというのとは訳が違います。関羽(雲長)が討たれたことにより劉備(玄徳)の頭の中は天下統一より弔い合戦ということでいっぱいでした。そのため諸葛(孔明)では制御できるわけもなく、ここで蜀の野望はついえたと言っても過言ではありません。
全力で来る劉備軍に対し孫権軍も無傷で済むわけもなく、多大な被害を被ったのです。ちなみにこの戦いが起こるちょっと前に張飛(翼徳)は部下に無茶ぶりをしたため刺殺されてしまったのです。
最初から最後まで司馬懿(仲達)の目論見通り進んだ訳だが、ここまであっさり作戦通りに事が運んだので司馬懿(仲達)にとっても驚いたことでしょう。
義を重んじて人望が厚かった劉備(玄徳)ではあるが、怒りの感情に任せて全軍を呉に向けるという浅はかな作戦を立てるのは王としての器が欠けるとも捉えられます。しかし私はこのように「全てを投げ打ってでも感情を爆発させなければいけないことがある」という姿勢に民は惹かれていったのではないかとも思います。
まとめ
■ まとめ
まとめ
いかがだったでしょうか?司馬懿(仲達)の計略、陸遜(伯言)の策、関羽(雲長)による樊城包囲、呂蒙(子明)による江陵攻略、そして劉備(玄徳)による弔い合戦。これらすべては一つの直線となり、三国志に与える影響が計り知れないのがよく分かります。
赤壁の戦いのような派手さはないけれど三国が絡み合った見ごたえのある対戦と言ってもいいでしょう。この戦いにおいてはその後のストーリーにも影響を及ぼすことが多く、三国志を学ぶ上で是非とも頭に入れておいてほしい場面です。
どの武将、どの国が好きかで見方は大きく変わってくるかもしれませんが、魏、呉、蜀それぞれから視点を変えてみるととても深い戦いになってくると思います。