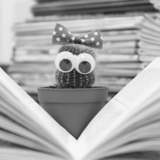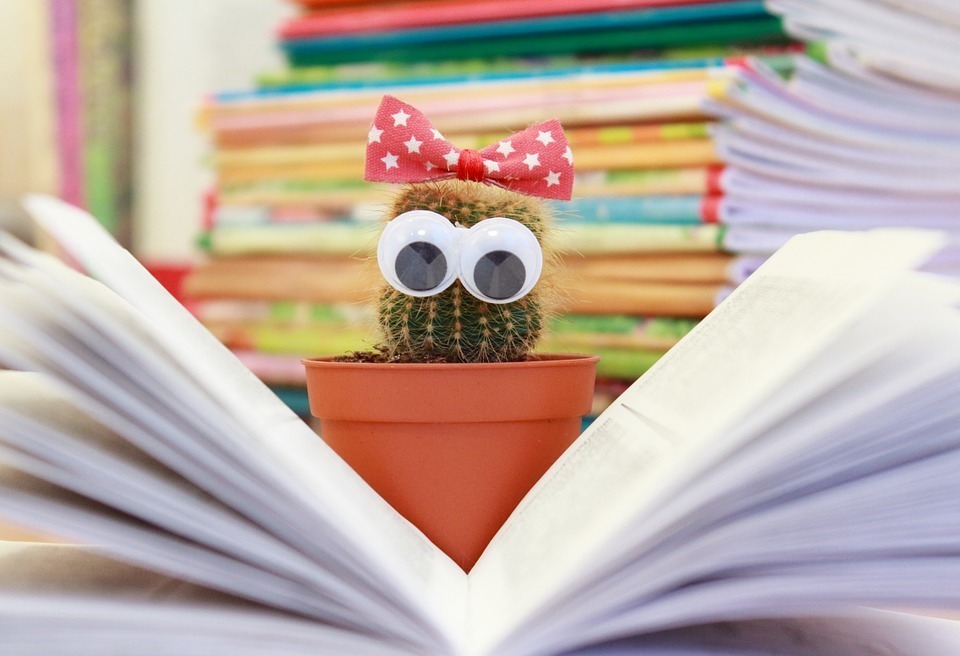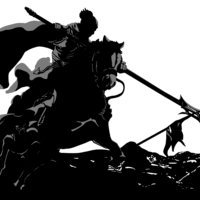秦は曹操軍
■ 秦は曹操軍
秦は曹操軍
キングダムで秦と言ったら王が優れている、有能な武将が次々と誕生している、国土が豊という良い点が揃っています。しかし物語の前半では呂不韋が中で国を乱しているため足を引っ張られる要素が多々ありました。これを三国志に置き換えると曹操軍に似ていると思います。
曹操(猛徳)は悪い噂が立つことも多いですが人材投与に優れていて、優れた丞相だったといえるでしょう。負け戦もありますが、やはり曹操(猛徳)でなければあそこまで国は成長しなかったのではないかと思っています。
同じように秦も新王・政がいたから国が大きくなったと言っても過言ではありません。
そして反抗勢力である呂不韋と司馬一族も似ています。呂不韋は結局国を乗っ取ることはできませんでしたが、司馬一族は国を乗っ取り、国名を魏から晋に変えています。結果は違えど、両国の歩んだ道のりは似ています。
もしキングダムを読んでいて三国志を全く知らないという人はそういう視点で見ると三国志も楽しめるのではないでしょうか。
韓は袁術軍
■ 韓は袁術軍
韓は袁術軍
キングダムで弱小国と言ったら韓が真っ先に挙げられるのではないでしょうか。キングダムで韓の露出は今のところあまりありませんが、秦VS合従軍の際には韓軍は毒を使う小賢しい国という印象を与えました。
三国志で韓と似たような国は?と問われると私は袁術軍を推したいと思います。袁術(公路)は親の権力で持っていたような君主で、我儘で武力に富んではいないが姑息な手を使うといった感じであまりいい話は聞きません。
そういうせせこましさがなんとなく韓に似ていると思ってしまうのです。
もちろん反対意見もあると思いますが独断と偏見で言わせていただくと似ているなぁというのが正直な感想です。
斎は劉表軍
■ 斎は劉表軍
斎は劉表軍
今現在発行されているキングダムで最大の見せ場の一つと言えるのが秦VS合従軍です。主人公信のいる秦国が斎以外の六か国から同時に攻められてしまいました。元々斎はこの合従軍に関わるはずでしたが、斎王の独断と偏見で参加しないことに。後々秦王・政は斎が加わっていたらどうなっていたか分からないと発言し、感謝の念を伝えました。
理由は違えどこの「戦に積極的に参加しない」という態度を見せる君主が三国志にも存在します。それが劉表(景升)です。彼は袁紹(本初)と曹操(猛徳)の覇権争い(言ってみれば三国志の序盤で頂上戦争が行われました)
チャンスで攻めず、「優柔不断」というレッテルが張られましたが彼にはきっと何かしらの魂胆があったことでしょう。
劉表(景升)が亡くなったらすぐに曹操の軍に吸収されてしまいましたが、彼の時にそうならなかったのはやはり劉表(景升)の威厳や存在感という者があったのではないでしょうか。
そう考えると斎王と劉表(景升)は似ていると思ってしまうのです。
趙は劉備軍
■ 趙は劉備軍
趙は劉備軍
キングダムで趙と言ったら秦のライバル国で趙三大天・李牧、同じく三大天・龐煖のインパクトがものすごく強い人が多いのではないでしょうか。類まれなる能力の高さで他を圧倒しことごとく秦の前に立ちはだかる最強の敵として君臨しています。
これを三国志に置き換えると劉備軍です。劉備軍はあまり大きな国ではないにもかかわらず劉備軍は諸葛(孔明)、関羽(雲長)と言った英傑ぞろいでまさに少数精鋭と言った国です。
こういう国は主人公の国にしやすく、三国志でも劉備(玄徳)のいる蜀に焦点を当てられ物語が進められたリ、劉備軍の英傑たちだけよく書かれていることは多々あります。
キングダムで趙は敵国ですが違う見方をしたら主役になりえる国だと思います。
楚は袁紹軍
■ 楚は袁紹軍
楚は袁紹軍
キングダムで楚は超大国で秦VS合従軍の際でも最も強い国という位置づけで攻めてきました。しかし次々と大将が倒され結局合従軍を勢いづかせることが出来ませんでした。そして今のところ大国、大国という割には(あくまでキングダムが発行されている48巻までという訳ですが)大きな動きを出しておらず、そこまで強くないんじゃないか?という印象しか与えていません。
袁紹軍も同じで超大国でありながらこれと言った見せ場を出すことが出来ず反董卓連合の盟主として出陣した袁紹(本初)の求心力がなくあえなく瓦解、官渡の闘いでは人数的には圧倒的に多かったのにもかからわず最強のライバル曹操(孟達)にあっけなく敗れ早々に三国志の舞台から姿を消さざるを得なくなりました。
今後の展開により見方が変わるかもしれませんが似たようなものは感じられるのではないでしょうか。
燕は黄巾賊
■ 燕は黄巾賊
燕は黄巾賊
秦VS合従軍の時と言い、趙VS燕でも「燕は何してるの?」という位キングダムでは連戦連敗しているのが燕です。燕の将軍オルドは勝気な性格ですが、戦績を挙げられず結局戦で失敗に終わるという印象を持たされている人は多いと思います。
三国志で黄巾賊がこのようなポジションではないかと思っています。各地で反乱を犯していた黄巾賊は自信満々で戦を始めゲリラ戦を繰り広げていました。
しかし結局相手への驚異になる物の何を成し遂げるということもなく終わってしまい最終的にはいつの間にか舞台から消えてしまっているのが黄巾賊です。
2つともあまりいい意味で物語に爪痕を残すことが出来ないところが似ていると思います。
魏は呂布軍
■ 魏は呂布軍
魏は呂布軍
魏火龍七師、呉鳳明と言ったインパクトあるそして結構腹黒いといったイメージを与えて物語を楽しませてくれるのが秦の隣国、魏です。常に秦とせめぎ合いをし、趙国同様キングダムを楽しませてくれている国です。
こういった腹黒さ、一人一人の強さが際立つという意味では三国志では呂布軍に似ています。呂布(奉先)は裏切りを繰り返し信用のおけないやつというレッテルを貼られています。
しかしその強さと狡猾さはやはり魅力で「悪い奴」としながらも呂布のファンという人は少なくないです。「少々の悪があってもそれを上回る強さがあれば求心力がある」というのを見せつけてくれる魏と呂布軍は(呂布軍と言っても主に呂布(奉先)ですが)そっくりと言ってもいいと思います。
まとめ
■ まとめ
まとめ
キングダム国と三国志の軍の似ている点を挙げてみました。キングダムで「この国が好き」という思いがあっても三国志は知らないという方はぜひ三国志も読んでみてはいかがでしょうか。似ているところ、違うところがあり興味をそそらされることだと思います。キングダムも三国志も面白いのでどちらかしか知らないという方はもう片方も読んでみることをお勧めします。