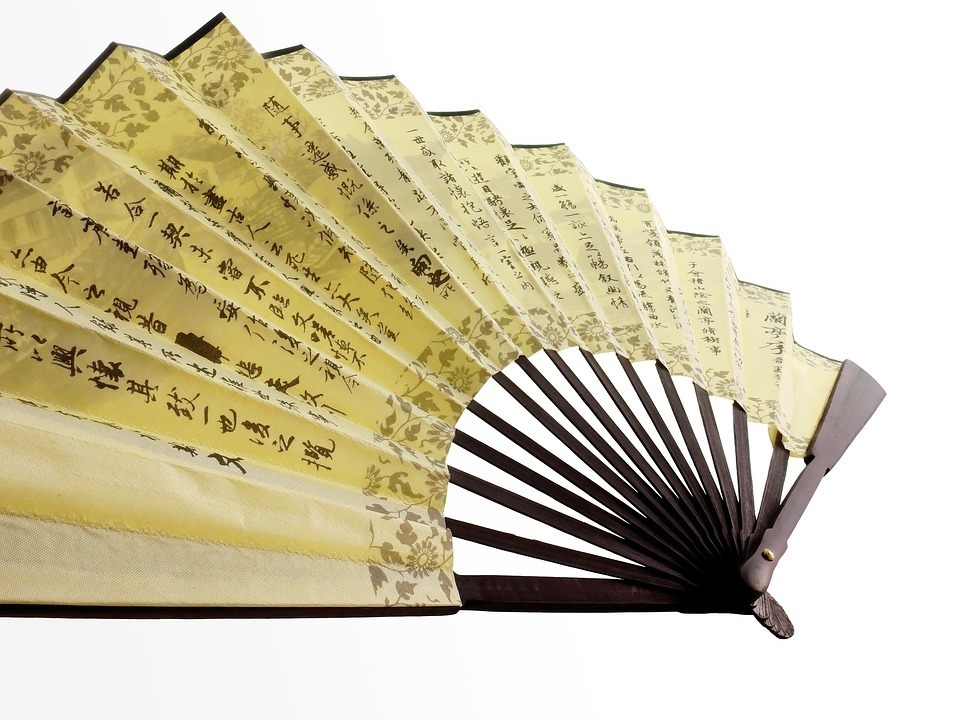①スタートから三国の争いだったわけではない
■ ①スタートから三国の争いだったわけではない
①スタートから三国の争いだったわけではない
まずは三国志のスタートについて。三国志と言っても元から三つの国が覇権を争っていたわけではありません。後漢王朝が滅び各地で覇権争いが行われます。これは各地で戦国武将が覇権を争っていた日本の戦国時代に似ています。
まず最初に頭角を現したのが董卓(仲穎)です。しかし彼の賄賂や暴政があまりにもひどく周りの人間は「こいつは止めなければいけない」と立ち上がるのです。そこで董卓VS反董卓連合という構図が出来上がります。
紆余曲折を経て董卓(仲穎)が倒れてから(反董卓連合が戦で勝ったわけではない)本当の群雄割拠が広がります。各地で争いが起き最終的に曹操(猛徳)率いる魏、孫権(仲謀)率いる呉、劉備(玄徳)率いる蜀の三つ巴になるのです。
言ってみれば三国になったのは中盤以降と捉えてもらって構いません。三国志を追っていくとその三国になるまでの各地での小競り合いが好きという人や、諸葛(孔明)が亡くなった後の激しい攻防が好きという人もいます。
自分独自の好きな位置から知識を広げていくというのが三国志の一番の楽しみ方だと思いますよ!
②曹操(猛徳)は最初からラスボスだったわけではない
■ ②曹操(猛徳)は最初からラスボスだったわけではない
②曹操(猛徳)は最初からラスボスだったわけではない
三国志というと劉備(玄徳)が正義、曹操(猛徳)がラスボスと捉えられることが多々あります。しかし上記で挙げたように三国志の長い歴史で三国になったのは中盤以降です。三国になってからは曹操(猛徳)が力を付けてラスボスのような存在として君臨していますが、最初は董卓(仲穎)から逃げたり、戦争で連戦連勝を治めていたりしたわけではありません。
実際曹操(猛徳)は何度も死にそうになり、その都度仲間に助けられたリ、悪知恵を働かせて生きながらえていたのです。
しかし三国志ではこの「死なないこと」が何より重要なポイントとなります。それゆえ曹操(猛徳)がラスボス的存在にまでのし上がった一番の要因と言えるでしょう。
③「死せる孔明、生ける仲達を走らす」の仲達とは?
■ ③「死せる孔明、生ける仲達を走らす」の仲達とは?
③「死せる孔明、生ける仲達を走らす」の仲達とは?
三国志が好きではない人でも「死せる孔明、生ける仲達を走らす」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。この言葉は永遠のライバルとでも言える諸葛(孔明)と司馬懿(仲達)の間柄を表している言葉です。諸葛(孔明)は死ぬ際、「自分が死んだことが分かったら司馬懿(仲達)が攻めてくるからその時は影武者を使ってあたかも生きているかのようにして司馬懿(仲達)を追い返せ」という策を残しました。そして諸葛(孔明)の読み通り、彼が死んだ後、司馬懿(仲達)は諸葛(孔明)にビビり急いで引き返したのです。
この言葉は諸葛(孔明)を称え司馬懿(仲達)をけなす言葉ではありますが、実際その後司馬懿(仲達)は魏が三国を統一する足掛かりをしっかり固め、孫である司馬炎(安世)が三国を統一した(要は覇者の祖父になった)のです。
つまり一時は笑われた司馬懿(仲達)ですが三国志一の勝者と言っても過言ではないのです!
④三国志の最後について
■ ④三国志の最後について
④三国志の最後について
さて、三国志の最後ですが、日本の場合諸葛(孔明)が死んだあと尻つぼみになってその後の記述が薄れます。(ストーリーによっては諸葛(孔明)が死んだからそこで終了というものもあるくらいです)これにより勝手に「やはり一番強かった曹操(猛徳)が三国を統一したのだろう」と解釈する人は少なくありません。恥ずかしながら私も最初そう思っていました。ところがこの前にすでに曹操(猛徳)は亡くなっています。
しかし諸葛(孔明)が亡くなった後ももちろん三国志は続きます。
まず諸葛(孔明)という大司令塔を失った蜀は衰退していきます。魏も司馬懿(仲達)が亡くなりますが彼の息子がしっかりと後を継ぎ魏の強さは揺るぎません。司馬懿(仲達)が亡くなった翌年、呉の君主孫権(仲謀)が亡くなり、ここから呉はおかしくなっていきます。
そして魏の中で司馬一族の力が強くなりすぎて曹一族を圧倒します。司馬炎(安世)が魏を乗っ取り晋という国を建国します。最終的にこの晋が三国を統一するのです。これが三国志の終焉です。ちなみにこの晋という国、長くは続きません…。
⑤劉備(玄徳)は人格者
■ ⑤劉備(玄徳)は人格者
⑤劉備(玄徳)は人格者
さて、ここで劉備(玄徳)という人物にフォーカスを当ててみましょう。魏の曹操(猛徳)や呉の孫権(仲謀)は家柄がよく、スタートからある程度恵まれた環境下に置かれていました。一方劉備(玄徳)のスタートはほぼ0からのスタートでした。
しかし彼の周りには関羽(雲長)や張飛(翼徳)をはじめとして趙雲(子龍)や諸葛(孔明)と言った魅力あふれる英傑たちが集まります。それはひとえに劉備(玄徳)が備えている「儀」「仁」「徳」によるものだと言われています。
「さぞ完璧な人格者だ」と思われがちですが、実はそうではない面もあります。確かに彼は同志に対しては熱いものがありました。
しかし「兄弟は手足のごとし。妻子は衣服のごとし」=「妻子は取り換えることが出来るが兄弟(ここで言う兄弟は契りを結んだ関羽(雲長)と張飛(翼徳)を指します)は一度失ったら戻らない」と言ったのです。
これを今の時代に言ったらモラハラで離婚ものですよね。劉備(玄徳)は確かに人格者だと思いますが、そうでない一面もあるということです。
⑥三国志の武将は硬派とは限らない
■ ⑥三国志の武将は硬派とは限らない
⑥三国志の武将は硬派とは限らない
覇権争いを行っている三国志の武将は全てを投げ打ってでも天下を統一することを目指していた!というのは嘘です。もちろん硬派な人間も多かったのでしょうが、女にうつつを抜かす武将も多々いました。(結局どの時代も女好きは多かったということです)
その代表格が董卓(仲穎)と司馬炎(安世)です。
董卓(仲穎)は董卓を倒そうとする反董卓連合に対して負けませんでした。(分かりやすく日本に置き換えると、織田軍対武田、上杉、伊達、毛利、徳川軍という感じです)
しかし貂蝉という一人の美女により董卓軍が崩壊。結局董卓(仲穎)側近である呂布(奉先)によって殺されてしまうのです。
一方司馬炎(安世)はというと三国時代を終わらせ中国を統一しました。王様になった司馬炎(安世)は1万人の宮女を囲っていました。司馬炎は後継者の育成を満足に行うこともなく毎日酒色にふけったのです。そのため三国を統一した晋は長いこと続きませんでした。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志の誤解されていたであろう点について簡単にまとめましたがいかがでしたか?
ちょっと三国志をかじれば「そんなの知っている」と言われてしまいそうですが、少しでも「へぇそうなんだ!」と思っていただけたら幸いです。
学べば学ぶほど自分の知らなかった三国志の知識が広がり「三国志って面白い」と思えるかもしれません。