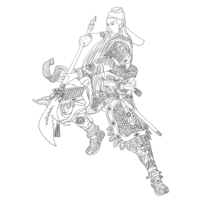助けてもらった劉備(玄徳)をないがしろに
■ 助けてもらった劉備(玄徳)をないがしろに
助けてもらった劉備(玄徳)をないがしろに
三国志の中で董卓(仲穎)の性質を知るのに欠かせないシーンがここです。黄巾賊との戦いでピンチに追いやられ命も危ういという状況になりました。しかしそこを劉備(玄徳)、関羽(雲長)、張飛(翼徳)らの助けにより危機を回避することになりました。しかし助けてくれたのがどこの馬の骨とも分からぬ劉備(玄徳)達だったので礼も言わず彼らのことなどないがしろにしてしまいました。もしこれが名家の袁術(公路)等だったら全然違うふるまいをしていたでしょう。要は自分が礼をすることによって得をするか否かという所をちゃんと考えているのです。初期の劉備(玄徳)は軍と言う軍を持たなかったため礼をするに値しないという判断だったのでしょう。
宦官らにわいろを贈り地位を買い取る
■ 宦官らにわいろを贈り地位を買い取る
宦官らにわいろを贈り地位を買い取る
董卓(仲穎)は相国(今風に言ってみれば内閣総理大臣)にまで上り詰めたわけですが、その地位を得られた最大の要因はお金の使い方にあると思います。キングダムを呼んでいる人なら秦の時代に呂不韋がその地位を得たわけですが、呂不韋と同じように金の使い方がうまく、周りを金で丸め込んでいたのです。黄巾の乱の際は連敗を喫し罰せられるところだったのですが、宦官らにわいろを贈りその罪を逃れることに成功しました。さらに西涼と言う地の太守の位を買い取り出世しました。そこで兵を養い続け、二十万の大軍を率いることが出来るほどにまで力を蓄えました。董卓(仲穎)は単なる銅片をお金にしてしまい貨幣価値をぐちゃぐちゃにしてしまった人物ではりますが、三国志の中で一番お金を使って出世した人物と言っても過言ではないでしょう。
劉弁=少帝を廃位させ、劉協=献帝を擁立した
■ 劉弁=少帝を廃位させ、劉協=献帝を擁立した
劉弁=少帝を廃位させ、劉協=献帝を擁立した
董卓(仲穎)は反董卓連合を作らせるほどに嫌われることとなりました。その要因として挙げられるのが帝の廃立と擁立です。元々帝の位置には少帝が座していました。しかし董卓(仲穎)にとっては兄の劉弁=少帝より弟の劉協=献帝の方が扱いやすかったため「少帝は帝の器ではない!献帝に変えるべきだ!」と言って帝を変えてしまったのです。もちろんこれに対して納得できない物達が立ち上がります。それでも董卓(仲穎)の権力は凄く反対派を抑え込む力がありました。結局少帝を廃位して献帝を擁立することに成功してしまったのです。それにより反対派はもう董卓(仲穎)を好き勝手やらせてはいけない!と言うことで反董卓連合を結成するのです。しかし結局反董卓連合は「董卓を倒した後自分達が有利になるように」と言う魂胆があったのでしょう。一枚岩になり切れず瓦解してしまうことになります。
対立する丁原の殺し方がエグイ
■ 対立する丁原の殺し方がエグイ
対立する丁原の殺し方がエグイ
上記の帝の変更劇(少帝→献帝)の際にもちろん董卓(仲穎)に反抗をする者はいました。その第一人者が丁原です。多くのお偉いさんが董卓(仲穎)に萎縮する中、丁原は「それは間違ってるだろ!」と面と向かって啖呵を切ったのです。物おじしなかった性格と言うのもあるかもしれませんが、そうできた一番の要因は最強のボディーガード呂布(奉先)がいたからだと思われています。三国志最強の男呂布(奉先)はこの時まだ武功を挙げるに至っていませんが董卓(仲穎)は呂布(奉先)に結構ビビっていました。そのため呂布(奉先)を仲間にしたいと考えました。呂布(奉先)に赤兎馬を与え言葉巧みに義父である丁原を殺させたのです。この件に関しては呂布(奉先)も相当ひどく、この裏切りにより裏切者のレッテルを張られるようになるわけですが、それを成し遂げた董卓(仲穎)の汚さは光りますね!
袁紹一族を皆殺しにする
■ 袁紹一族を皆殺しにする
袁紹一族を皆殺しにする
董卓(仲穎)は少帝を失脚させたわけですが、それだけでは飽き足らず母親の何太后と一緒に殺してしまいます。さらに暴政は加速し、宮中の女を好き勝手し、財宝まで奪ってしまいます。これに見かねた曹操(猛徳)が名だたる武将に檄文を送り反董卓連合を結成します。
この反董卓連合ですが、結成した際は曹操(孟徳)の一声でしたが盟主は袁紹(本初)でした。
一同が打倒董卓を掲げ洛陽へ目指しますが、もちろん董卓(仲穎)は激怒します。洛陽にいる袁紹の一族を皆殺しにしてしまいました。
こうなったら反董卓連合の結束が一気に強まるものですが、一枚岩になるということはなく、
汜水関、虎牢関で勝利を挙げ、洛陽から長安へ遷都させるまでに董卓(仲穎)を追い詰めますが結局倒すことなく反董卓連合は瓦解してしまいます。
(個人的な感想ですがこれは日本人と中国人と言う違いがあるのではないでしょうか。日本人なら盟主の家族が殺されたら哀れみ怒り、「なんとしてでも結束してあいつを倒そう!」となると思います)
さらにこの遷都の際、洛陽を焼き払い領民を引き連れます。しかもついてこれない老人、子供を途中で見殺しにするという最悪の所業を施すのでした。
兵たちに略奪、凌辱を許す
■ 兵たちに略奪、凌辱を許す
兵たちに略奪、凌辱を許す
こんな董卓(仲穎)はなぜあっさり殺されることが無かったのかと言うと私は兵の士気が異様に高かったからだと思っています。董卓(仲穎)は兵に略奪、凌辱を許していました。言ってみれば兵には旨味があり、「よしやってやろう!」と思ったことでしょう。言ってみれば「いくらでも銀行強盗していいからな!」と言われているようなものです。これは敵を多く作るかもしれませんが、見方も多く作ることができます。それゆえ結束力は高く、数で圧倒する反董卓連合につぶされずに済んだ要因と言えるでしょう。
これをカリスマ性と呼んでいいのかは分かりませんが、董卓(仲穎)が最強の軍を作り上げた所以です。
最終的に董卓(仲穎)は王允(子師)にはめられた呂布(奉先)に殺されますが、まさにやりたい放題やった人生だったと言えることでしょう。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志一悪名高いと言われる董卓(仲穎)がなぜそういわれているのかと言うのがなんとなく分かっていただけたら幸いです。そして「なぜそんな悪を簡単に打ち滅ぼすことが出来なかったか」という理由がまさにこの時代の深層心理という所ではないでしょうか。
いつの時代でもどこの国でも悪が栄えるのには理由があり、董卓(仲穎)を追っていくと「なるほどな」と思わされることが多いと思いますよ!