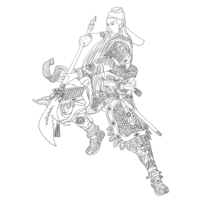李傕(りかく)と郭汜(かくし)
■ 李傕(りかく)と郭汜(かくし)
李傕(りかく)と郭汜(かくし)
なんとなくセットにされがちなこの二人。二人とも董卓の元で悪名を轟かせた武将です。幼馴染で仲が良く、二人で董卓のごとく、弱い者いじめの限りを尽くしていました。
董卓(とうたく)が王允(おういん)と貂蝉(ちょうせん)の策略により、呂布に倒されます。
董卓の仇討ちと称し、李傕は王允を葬りました。それも残虐な殺し方で八つ裂きにしたと言われています。また郭汜もやばい匂いを漂わせます。
なんとその後董卓亡き後、残った軍をまとめるものの、なんとこの二人、仲たがいをし、大きい戦争を始めてしまうのです。董卓軍は何かとお騒がせな軍で自分勝手という人物ばかりですね。
董卓(とうたく)
■ 董卓(とうたく)
董卓(とうたく)
董卓と言えば残虐、傍若無人、短気で「殺してしまえ」が口癖です。金で官職を買い取るあたりはキングダムの呂不韋(りょふい)そっくりです。ちなみに二人とも相国(国の実権を持つものと考えてください。帝を後退させようとしたり、それに反対したものを殺してしまったり、最強のボディーガード呂布を手に入れる際、養父を殺させたりと、董卓に関わったら命がいくらあっても足りません。三国志のオールスターと言ってもいい面々が連合軍を組んでも倒せなかった董卓はやばさだけでなく、強さも兼ね揃えていました。
しかし最後に倒された際に用いられたのがハニートラップ。最強のボディーガード呂布に殺されその人生に終止符を打ちました。あの場面で死ななかったら三国志は董卓、曹操、袁紹となっていたかもしれません。
孫休(そんきゅう)
■ 孫休(そんきゅう)
孫休(そんきゅう)
孫権の6男にあたり、三代目皇帝に着いた孫休は最初謙虚な人物でした。帝位についてくれという進言についてかたくなに拒否したが、三度も懇願されたため皇帝の座に就いたとされています。しかし皇帝の座に就くと徐々に変わっていきます。
孫綝が宮廷内で勢力を伸ばすと何度も恩賞を与えご機嫌取りをするようになったのです。しかし被害妄想が強かったのか、徐々に孫綝を疎ましく思ったり、その他の権力者についてもクーデターを起こすのではないかと危惧したりし、自己防衛を果たすような詔を何度も発令するようになりました。
ちなみに孫休の前の皇帝孫亮(孫休とは異母兄弟にあたる)が死んだのは自殺という説と、孫休が毒殺したという説があります。ちなみに、自殺をした説だと、護送をしていた役人の落ち度とみなし処刑までしているのです。この頃の呉は国として明らかにおかしく、孫堅、孫策、孫権が築き上げた呉の見る影もありません。
孫皓(そんこう)
■ 孫皓(そんこう)
孫皓(そんこう)
私が思うに三国志の歴史で一番ダメな奴がこの孫晧です。孫晧は呉のラストエンペラーという立ち位置だったのですが、やることなすことがとにかくダメな君主でした。宮廷内でたてつくものがいたら容赦なく斬りつけたし、宮中の女は2500人も抱えていたとされています。しかも卑劣極まりないことをしていたため声がかからないかびくびくしていたと言われていました。そんなものだから呉が晋に攻め込まれた時も必死で国を守ろうという人間は少なく士気は上がらなかったことでしょう。三国志の後半が尻つぼみになって記述が少ないのは前半にあったような「信」であったり「義」であったりとしたものが極端に薄れていたからだと思います。
そしてそれが最も当てはまる人物が孫皓です。孫皓は晋に攻め込まれ宮女をごっそり晋の皇帝、司馬炎に持っていかれました。
司馬炎も当時2500人の宮女を抱えていたため合わせて5000人の宮女を抱えることとなりました。そのため「三国志一のエロは誰か?」という問いに対し「司馬炎」という答えが出る所以なのです。
甘寧(かんねい)
■ 甘寧(かんねい)
甘寧(かんねい)
甘寧は若いころ賊の頭をしていました。(レッドクリフで中村獅童が演じた甘興は恐らくこの甘寧のことです)甘寧はいわゆる不良で腰の帯に鈴をつけていたため、甘寧が歩くとすぐに「奴が来た」というのが分かったと言われています。
相手がお偉いさんでもお構いなしに屋敷に忍び込み平気で財産を奪うという輩でした。心機一転戦で名を馳せようと思った甘寧ですが、誰からも嫌われ登用されることはありませんでした。しかしそんな甘寧を掬ったのが周瑜や呂蒙です。
彼らが孫権に推薦し、呉を支える武将にまで成長しました。更生したからよかったものの、その前は相当ひどかったらしく、乱暴の限りを尽くしました。
キングダムで言う所の桓騎と言ったところでしょうか。
許褚(きょちょ)
■ 許褚(きょちょ)
許褚(きょちょ)
許褚はとにかく横にでかい人物とされています。そのため許褚のイラストが出る際は必ずかなり太った人物像になる為、「こいつが許褚じゃないか?」と一瞬で分かります。
武勇に優れ曹操は「許褚がいなかったら私は死んでいた」という場面すらあるほど曹操から溺愛されていた人物です。賊と和睦を結ぶため牛と食料を交換させる際、牛が逃げ出そうとしたのでしっぽをつかみ百歩ほど引きずり歩いたら賊は牛を引き取らず逃げてしまうというエピソードがあるくらいです。
許褚は、曹操の親衛隊として仕えたわけですが、潼関の戦い(どうかんのたたかい)の際に馬超の軍に曹操が囲まれてしまいました。
そのとき船で必死に逃げようとするのですが、曹操を乗せた船に兵も競って乗ろうとしたため船が沈没しそうになりました。すると許褚は船に乗ろうとする仲間の兵を切り捨てていったのです。仕事熱心というか、君主思いなのはいいのですがここまでするやばい奴はあまりいません。
そして曹操が亡くなった際にはあまりのショックに声をあげ号泣し、血を吐いたと言われています。力が虎のようにあったが、頭が悪い「痴」であったため「虎痴」と呼ばれていました。中国語の発音では許褚と虎痴が似ているため、虎痴が名前だと思った人物がいるというエピソードもあります。
まとめ
■ まとめ
まとめ
三国志には強い人物、仁義に熱い人物がいる半面ただひたすらやばい奴も多く存在します。ここでは残虐性に富んだ人物を上げましたが、非道な人物はこのほかにもまだまだいます。
「こいつとは関わりたくない」と思うことで、ゲームに出てくるような強さや賢さだけでなく、「やばさ」という目安にしてもらえれば幸いです。恐らく当時の中国は人口が恐ろしく多く、無秩序状態だったため「命の重さ」というものがかなりあいまいなものだった気がします。
そのためえらい人物は民をいくら殺してもいいという錯覚に陥っていたのではないでしょうか。今の時代だったら号外が出るレベルの凶悪事件が日常茶飯事のように行われた時代。そしてその中でもトップクラスのやばい奴らは覚えていて損はないと思います!