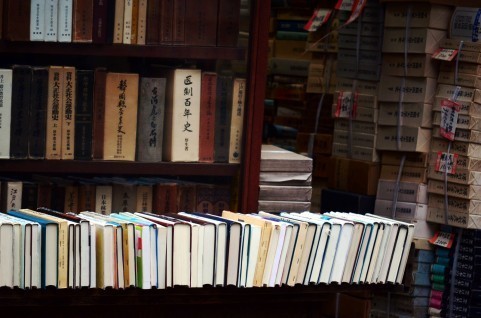メイキング取材を開始する
■ メイキング取材を開始する
メイキング取材を開始する
陳寿は司馬炎から第六品著作郎を任命され、その仕事の傍らで魏志・呉志・蜀志を書くための取材をしていました。陳寿が行った取材は実に本格的で、三国志を記す題材の中心となる魏・呉・蜀に関する古い記録や後漢時代の資料集め、戦場や城の跡地の訪問。さらには、現地に住む高齢者にインタビューしたり、偉人の子孫の家を訪れて対談を行っていたとされています。おそらく、子孫の家を訪問したのは家伝となっているものや話を聞くためであったと推測します。
魏志・呉志・蜀志を記す
■ 魏志・呉志・蜀志を記す
魏志・呉志・蜀志を記す
陳寿は第六品中正に昇任(昇進すること)すると、魏志・呉志・蜀志の制作に取り掛かりました。この3つの著書がいわゆる正史三国志であり、魏志30巻、呉志20巻、蜀志15巻の65巻を総称して「三国志」と名付けました。
陳寿が「三国志」を記したばかりの頃は、私撰(自発的に記した書物)の歴史書でしたが、彼の死後約500年後、唐の太宗によって「正史」(正当な歴史書)とされました。
制作期間はどれくらいなのかは分かっていませんが、泥沼から引っ張り上げてくれた張華に見せているので、それほど長い年月はかからなかったようです。
三国志が完成した当初は高い評価を得ていた
■ 三国志が完成した当初は高い評価を得ていた
三国志が完成した当初は高い評価を得ていた
三国志が完成した当初は、これを読んだ皇帝、大臣、役人たちはこぞって三国志を高く評価し、
これを著作した陳寿のことを「事実をありのまま著わすことに優れ、良史(考古学)の才能がある」と称賛しました。
恩人の評価
■ 恩人の評価
恩人の評価
張華も三国志を大変気に入り、三国志の著作は国家の偉業であるとして陳寿を中書郎の役職に任命するよう上奏しました。さらに、「陳寿に晋の歴史書を書かせたい」とも述べたそうです。
武将からの評価
■ 武将からの評価
武将からの評価
「破竹の勢い」の生みの親である鎮南将軍の杜預(どよ)も三国志を読んでおり、陳寿の書く文章に
感心したそうです。杜預は勇猛果敢な武将で、呉と晋の天下分け目の大戦にてなかなか呉軍を倒すことができず、撤退を考えた司馬炎に多くの臣下が「降伏しましょう」と進言しているのにもかかわらず、徹底抗戦を主張しました。彼は後に詩人の大家となる杜甫の先祖だけあって、文才にも秀でていたそうです。
そんな彼が陳寿の文才を高く買って、司馬炎に散騎侍郎を任命するように上奏しました。しかし、このとき既に寿良(じゅりょう)という者がこの役職を得ていたため、詔で下知された役職は侍御史でした。
己の非力さを痛感した同僚
■ 己の非力さを痛感した同僚
己の非力さを痛感した同僚
夏侯淵の曾孫にあたる夏侯湛は、陳寿と同時期に「魏書」と題する三国志の魏志と同じような趣向の書物を執筆していました。
夏侯湛は三国志を読んで、陳寿の文才の非凡さと己の才能のなさを痛感し。「臣の魏書は寿のこれに及ばない。臣は寿より優れた文をかくことはできぬ」と言うと涙ながらに己の記す「魏書」をビリビリに破り捨ててしまいました。そして、それからはまったく手をつけなくなってしまったそうです。
三国志メイキング中の悪事が露呈する
■ 三国志メイキング中の悪事が露呈する
三国志メイキング中の悪事が露呈する
晋の司空を務めていた張華や皇帝の司馬炎からの高い評価を得て有頂天になっている陳寿は、三国志を執筆するための取材で悪事を働いていたことが明るみに出てしまいました。
取材先での賄賂要求
■ 取材先での賄賂要求
取材先での賄賂要求
陳寿が三国志を執筆するために、古戦場・名所巡りや地方に住む遺臣、遺児にインタビューをして資料採集をしていたことは先に述べました。この取材で賄賂を要求していたことが公にさらされることになったのです。
陳寿は曹操と卞皇后の第3子にして詩聖と呼ばれた曹植の臣下、丁儀と丁廙(ていよく:丁翼とも表記される)兄弟の息子たちにインタビューをあらかたしたあと「私に千石頂けるのでしたら、私が執筆している魏志に丁儀伝や丁廙伝といった具合にあなた方のお父上に関する列伝を立ててしんぜましょう」と交渉したようですが、丁兄弟の息子たちは「貴様に千石くれてやるようなら、父上の伝記は書かなくてよい」と断固拒否しました。そのため、陳寿は丁兄弟の列伝を立てなかったそうです。
丁兄弟は曹操の寵愛を受けた曹植の手となり足となり周りの臣下や大臣を抱き込んで、曹植を曹操の後継者に擁立しようとした派閥リーダーだったので、魏主となった曹丕に恨まれて粛清(死刑)されてしまいました。そのため、魏志の列伝として取り上げられるべき人物でした。
陳寿のこういった行動は公平さに欠けるということで、歴史家としてあるまじき行為であるとして非難されました。
かつての先輩の再就職を妨害する
■ かつての先輩の再就職を妨害する
かつての先輩の再就職を妨害する
李福の息子の李驤(りじょう)は、譙周を師と仰ぐ同門の先輩でした。蜀の臣下として仕えていたころは、二人は仲がよかったようなのですが、蜀が滅んで晋の時代になると仲違いをして決別。李驤が晋に再就職をしようとすると、採用担当官をしていた陳寿はこれを拒み先輩の再就職を妨害しました。そのため李驤は晋への再就職を諦めざるを得なくなり、在野の名士として余生を送ったそうです。
これらのせいで陳寿は「己の利益ばかりにとらわれている器の小さいヤツだ」と悪評を噂されるようになりました。
対抗勢力のイジメに遭う
■ 対抗勢力のイジメに遭う
対抗勢力のイジメに遭う
陳寿の恩人である司空の張華と荀彧と同じ一族である荀勗(じゅんきょく)は、晋の朝廷内でNo2の座を争い合うライバル同士でした。張華は、三国志の素晴らしさを褒め称え、りんじゅを中書郎へ昇任させようと上奏します。
対して荀勗は、三国志のうちの魏志に気に入らない記述(荀彧、荀攸のくだりか?)があったようで、陳寿が都に留まり続けることを好しとしませんでした。そして、長廣太守として地方に左遷しようとして、太守任命を上奏しました。この結果、陳寿はまさかの長廣太守に任命されてしまいました。ところが、「年老いた母がいるため、太守の任はとても務まりません」と母親の介護を理由に、
左遷から逃れることができました。
お母さんの埋葬先がアウト!!
■ お母さんの埋葬先がアウト!!
お母さんの埋葬先がアウト!!
当時(儒教)の常識では、「故人の遺体はたとえどんなに遠く離れていても必ず故郷に埋めるべき」とされていました。しかし、陳寿の母親は遺言として「私が死んだら洛陽に骨を埋めてほしい」と遺言をしました。そのため、陳寿は母親の希望を尊重して故郷ではなく、洛陽に遺体を埋葬しました。
このことはすぐに洛陽中に広まり、陳寿はまたまた「親不孝者」の折り紙をつけられてしまいました。陳寿は父親の葬儀と母親の葬儀で計2回禁忌を犯したことになるため、またも路頭に迷うはめになります。
あっさり職場復帰
■ あっさり職場復帰
あっさり職場復帰
張華や三国志ファンの役人たちの口添えのおかげか、詳しい理由は不明ですが、数年で陳寿は太子中庶子に抜擢され、官職への復帰を果たします。
太子中庶子の役職は皇太子の側近として仕える役目を担っており、王子付き秘書や執事のような存在です。その太子が即位すると、再び散騎常侍を兼任しました。
後ろ盾を失う
■ 後ろ盾を失う
後ろ盾を失う
司空の張華は陳寿を九卿(きゅうけい)に昇任させようと上奏するのですが、西暦300年に起きた張王司馬倫の乱にて、陳寿の恩人張華は誅殺されてしまいました。
酸いも甘いも味わった生涯に終止符を打つ
■ 酸いも甘いも味わった生涯に終止符を打つ
酸いも甘いも味わった生涯に終止符を打つ
張華が誅殺されてからの晋朝は、忠臣、賢臣を次々と排斥していき荒廃し始めました。陳寿は特に失脚することもそれ以上に昇任することもなく、65歳のとき洛陽にて酸いも甘いも味わった人生に終止符を打ちました。
筆者の陳寿評
■ 筆者の陳寿評
筆者の陳寿評
筆者が「晋書陳寿伝」、「華陽國志陳寿伝」を読んだ限りでは、下記のように陳寿を評価します。
・頑固(世渡り下手)な性格
・常識にとらわれない傾奇者
・物事を簡潔かつ理解しやすい文章を書くことが得意
・事実をそのまま記すことに長じている
・歴史オタク
陳寿は後世の朱熹や儒学者に「諸葛亮やその息子諸葛噡を三国志中で侮辱している」、「元蜀臣のくせに曹魏を正統としたのは裏切り行為だ」と批判されていますが、前者の文句がつけられている原文は侮辱しているとは思えないし、後者は制作した時代が晋なのでその前身である曹魏を正統としなければ処刑されてもおかしくありません。
いずれにしても陳寿が三国志を残さなければ大ヒットゲームはおろか、不朽の名作になる三国志演義も存在しなかったことでしょう。