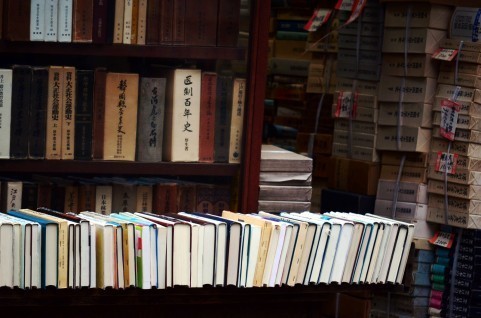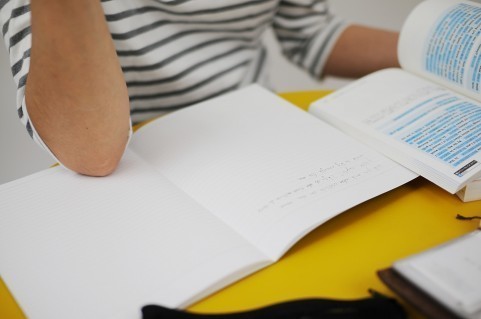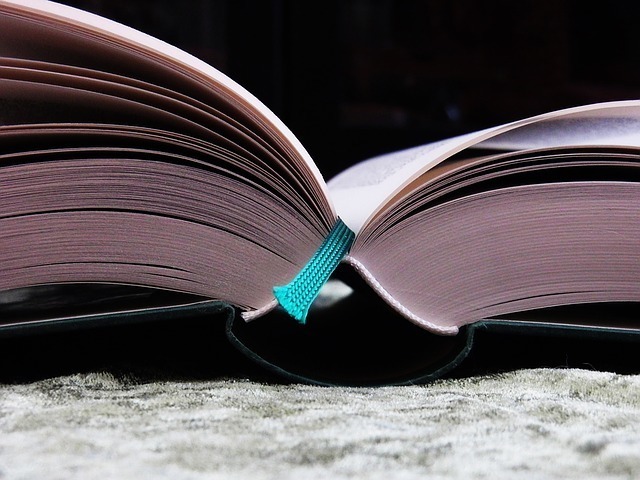正史三国志と三国志演義の違い
■ 正史三国志と三国志演義の違い
正史三国志と三国志演義の違い
みなさんは三国志と三国志演義の違いを明確にご存知でしょうか?
まずは、作者の違いを説明すると「三国志」の著者は陳寿(ちんじゅ)という晋の史家です。「三国志演義」の著者は陳寿が亡くなってから約1000年後の作家・脚本家の羅貫中(らかんちゅう)です。
「三国志」は紀伝体という体裁で記されており魏志30巻([本紀(皇帝に関する伝記)]4巻、[列伝(武将や官吏の伝記)]26巻、呉志20巻、蜀志15巻から構成されている正式な歴史書です。「三国志」は司馬遷の「史記」、班固の「漢書」、范曄の「後漢書」と並んで、中国の歴史書二十四史の中でも高い評価を得ています。
それに対し、「三国志演義」は元末明初の作家・脚本家の羅貫中が創作した歴史通俗小説、もしくは時代小説のジャンルに分類されるれっきとした読み物です。羅貫中は陳寿の残した「三国志」とそれに裴松之(はいしょうし)が詳しくするために民間伝承の寓話や説話、地方の雑記などから注釈を加えた「裴松之注三国志」、講談、演劇、漫談などの脚本や台本を参考にしつつ、自ら虚構を加えて記した物語です。
そのため、陳寿の「三国志」は報告書のようにただ事実だけが簡潔に淡々と綴ってあるだけの書物。羅貫中の「三国志演義」は骨組みを史実に則って組み上げて、ところどころに虚構を加え物語が面白くなるように作られた書物です。
正史三国志の著者 陳寿
■ 正史三国志の著者 陳寿
正史三国志の著者 陳寿
正史三国志の著者は姓を陳(ちん)名を寿(じゅ)字を承祚(しょうそ)と言います。三国時代の真っただ中に誕生し、当初は蜀に仕えて蜀が滅びた後は晋の武帝(司馬炎:司馬懿の孫・司馬昭の息子)に仕えた官僚です。
陳寿は晋に仕えているときに「三国志」を書いたので、晋の前身である魏を正当として著わしています。また、ほぼリアルタイムな時代に記されており、劉備(玄徳)や曹操の配下で戦って生き残った元兵士などの老人に取材するなど信憑性が高い歴史書を残しました。
就職する前
■ 就職する前
就職する前
陳寿は、建興11年(西暦:233年)蜀の領地である益州の巴西(はせい)にて、かつて馬謖配下の武将であった陳式の子として生まれます。彼の誕生した年は、蜀の名宰相諸葛亮孔明が五丈原で陣没した年と同じです。
陳寿は青年期から学問に励み、独学で勉強に励みました。しかし、自力で勉強することに限界を感じたのか譙周(しょうしゅう)に弟子入りを志願します。
譙周は、六経から天文学まで幅広く学問を修めた人物で、勧学従事(蜀宮廷内の図書館役員)に就いていました。譙周に弟子入りした陳寿は、彼のもとで様々な学問を学び、師匠と同じ職に就きます。
不遇の青年期
■ 不遇の青年期
不遇の青年期
陳寿が就職したときの蜀の朝廷はなかなか厳しい状況でした。それは、劉禅を厳しく指導してきた忠臣の董允(とういん)が亡くなり、宦官の黄晧(こうこう)が劉禅に寵愛されて実権を握り、専横政治を行います。この黄晧(こうこう)こそが蜀の滅亡を招く諸悪の根源でした。
劉禅の弟の劉永(劉備の息子の中でもまともな人物)と姜維は左遷され、諸葛亮の息子の諸葛瞻、董厥、樊建の3名は政務に携わっていたものの互いをかばい合うだけで黄皓の専横、政治の混乱を止めることができませんでした。しかし、若い陳寿はそれが許せずいっちょまえに黄皓に対して幾度も文句を言ったため、度々左遷されたり降格処分にされたりしました。
そんなとき、父親の陳式が病死してしまいます。
服喪中に大事件を起こす
■ 服喪中に大事件を起こす
服喪中に大事件を起こす
父の葬儀のため、陳寿は実家に帰省して服喪の休暇をもらいました。儒教の習慣で喪中にやってはならないことのひとつを陳寿は喪中に行ってしまうという大事件を起こします。
喪中にやってはいけないものとしては「飲酒すること」、「肉を食べること」、「宴会を催すこと」、「自分を労わること」などです。
陳寿は喪中に病気を患ってしまい、女中に丸薬を作らせて服用したのを地元住民に目撃されてしまったため、村人から「親不孝者」のレッテルを貼られてしまい軽蔑の眼差しを向けられるようになります。
当時の中国では親不孝な者は白眼視されたり罵倒されるだけでなく、就職が難しくなることもありました。
村人から軽蔑されてもなんとか3年の月日が流れ、喪が明けることになりました。そして、久々の出勤をしようとする陳寿にさらなる不孝が襲います。それは、蜀王朝の滅亡とそれに伴う失業です。
人生のどん底を味わう
■ 人生のどん底を味わう
人生のどん底を味わう
蜀が滅亡したことで故郷も職も失ってしまった陳寿は母親や家族を養うために仕事を探します。しかし、すでに親不孝者の折り紙がついている彼を雇ってくれるところはどこにもありませんでした。
魏が晋にとって代わられたとき、「自分にもやっと日の目を浴びられる時が来た!!」とひとすじの希望を持った彼ですが、残念ながら官僚になることができませんでした。
そんな人生のどん底を味わい泥沼からやっと手が出ているような状況の中、陳寿を泥沼から引きずり出してくれる救世主が現れます。
救世主 張華
■ 救世主 張華
救世主 張華
張華は晋の高官で文学界の巨匠としてその名を知られていました。そんな彼が陳寿の文才を高く評価、「陳寿の才能が世に埋もれてなくなるのは勿体ない。それに喪中に薬を飲んだだけなんだから批判するにあたいしないだろう」ということで、官僚に登用しました。
張華に救われた陳寿は粉骨砕身バリバリ仕事をこなし、その傍らで諸葛亮の実績を記した書物を執筆。これを張華に見せたところ張華は書物の内容を大いに褒めてくれて、「陛下は孔明が好きだからこれを献上したら?」という提案をしました。陳寿がいう通りにすると、司馬炎がこの書物を気に入ってしまい、陳寿を著作郎(ちょさくろう)に任命しました。陳寿はこれがきっかけでどんどん出世していきます。
前編のまとめ
■ 前編のまとめ
前編のまとめ
三国志の著者である陳寿は敗戦の将の子どもとして生まれ独学で学問に励みたゆまぬ努力で蜀の官僚になることができました。しかし、真っ直ぐな性格が災いを招き不遇の時代を送ります。ひょんなことから「親不孝者」のレッテルを貼られて失業し、苦悶に喘ぐ日々を送ります。
前編だけでも波乱に満ちた人生を送っていますが、これはまだまだ半分です。さてさて、これから陳寿はどうなってしまうのでしょうか?後編へ続きます。