テレビドラマ パリピ孔明 第一話
■ テレビドラマ パリピ孔明 第一話
テレビドラマ パリピ孔明 第一話
孔明は、三国志時代 志半ばで病死しますが、なんと、現代の日本で生き返ります。
目が覚めたら、渋谷の繁華街、そして、渋谷のクラブで駆け出しのシンガーソングライター・月見英子と出会います。
英子は、自分の歌を聴いてくれる人がいないことに悩んでいました。が、孔明が歌に感銘し、英子の歌声に可能性を見出し、彼女の軍師になることを決意します。
さて、劉備から英子へと引き継がれる天下取り。
孔明が現代の文化やテクノロジーに驚きながらも、それを自分の戦略に取り入れる姿が、コミカルでありながらも、親しみやすさを感じました。
孔明の天才的な戦略と英子の歌声が、これからの物語にどのように絡んでいくのか?どうなるか? 三国志時代のエピソードとリンクして、三国志好きになること間違いなしです。
才能とは学習の結果 現れるもの
■ 才能とは学習の結果 現れるもの
才能とは学習の結果 現れるもの
英子が自分の歌を誰も聞いてくれないと悩んでいる時に孔明が言った言葉。
「才能とは学習の結果、身に付くものだと考えております」
「才能とは学習の結果 現れるもの」という言葉は、藤原和博氏の著書「才能は努力でつくられる」の中で、述べていました。
藤原氏は、才能は生まれつきあるものではなく、努力によって伸ばすことができるものであると主張しています。
そして、才能とは、学習によって身につけた知識や技術、そしてそれらを活用する能力であると述べています。
この言葉は、才能を神格化するのではなく、誰もが努力によって才能を伸ばすことができることを示すものとして、多くの人に受け入れられています。
3つの要素を踏まえ、誰でも才能を伸ばし、活躍できる社会を創りましょうね。
・興味や関心
才能を伸ばすためには、まず、その分野に興味や関心を持つことが重要です。興味や関心があれば、自ら学び、努力する意欲が湧きやすくなります。
・努力
才能を伸ばすためには、継続的な努力が必要です。才能は、一朝一夕に身につくものではありません。日々の努力を積み重ねることで、初めて才能が開花するのです。
・環境
才能を伸ばすためには、適切な環境も重要です。才能を伸ばすための機会やサポートが得られる環境であれば、より効率的に才能を伸ばすことができます。
そして、孔明は、こう続けます。
「英子も歌をやめるは必要ない。。。
(古代三国志の時代は)言いたいことも言えず、戦さ場に出陣した者は、死んでいった。今、生きてるうちに語るべきであろう。」・・・夢を実現するまで努力していこう。
お酒の一気飲み リズムで説明
■ お酒の一気飲み リズムで説明
お酒の一気飲み リズムで説明
クラブイベントで、孔明が、音楽の差について英子に聞きました。
なぜ、昨日は、うるさかったのに、今日(イベントの始まり)は、静かな曲なのですか?
英子は、言いました。
「音楽には、テンポがあり、人は、テンポ、リズムによって盛り上がるからだよ」
音楽、お酒、歌・ダンス、リズムと盛り上がりの相乗効果ですね。
英子が説明したBPM(Beats Per Minute)は、音楽におけるテンポの単位です。
BPMは、1分間に刻まれる拍数を表します。BPMの数値が高いほどテンポは速くなり、数値が下がるほどゆっくりしたテンポとなります。
高いBPMは活気や興奮を表現しやすく、アップビートな楽曲では楽しさや陽気な感じがします。
低いBPMは静寂や哀愁を表現しやすく、バラードやメロウな楽曲では感傷的な雰囲気を演出します。
パーティなどのBGMも、このようなことを考えて構成するとよいと思います。
孔明は、酒豪、張飛について例えていました。
張飛をノセるために、お酒を飲む時に、拍手のテンポをあげると、お酒を飲むスピードがアップするのです。
皆さんも経験ありませんか?
日本でも、一気飲みが流行ったことがありましよね。
お酒の一気飲み中に、拍手のテンポをあげることで、盛り上げると同時にモチベーションをあげるからです。
お酒の一気飲みは、一種のステイタス、酒の強さを示すためだったり、社交の手段だったりしました。張飛は、このパターンです。
古代中国や日本では、儀式や習慣として行われることもありました。例えば、古代中国では、新年や祭りなどの際に、一気飲みが行われていました。また、日本では、相撲の土俵入りや、剣道の試合前の儀式として、一気飲みが行われていました。
具体的な例としては、古代中国では、酒の量を競う「酒宴」や、酒を早く飲む競争「酒速」が行われていました。また、日本では、江戸時代には、下級武士が主催する「大酒会」や、学生が行う「飲み会」で、一気飲みが行われていました。
現代では、一気飲みの危険性が広く知られるようになり、その機会は減少しています。しかし、依然として、飲み会や宴会などで、一気飲みが行われることがあります。
なお、一気飲みは、急性アルコール中毒の危険性が高く、命にかかわることもあります。そのため、一気飲みは絶対に避けるべきです。
石兵八陣(せきへいはちじん)
■ 石兵八陣(せきへいはちじん)
石兵八陣(せきへいはちじん)
対バン イベント!! チャンス?ピンチ?
ある有名アーティストと英子が、対バン イベントをすることになりました。
違う部屋で同じ時間に演奏するのですが、当然、人気のあるアーティストに客を奪われます。
この時に、孔明は、三国史 三国時代の石兵八陣(せきへいはちじん)の現代版で戦います。
皆さんも鏡の迷路などの経験ありませんか?
ステージを回したり、照明を変え、ディスプレイやオブジェの配置や案内人の移動などにより、お客さんが、英子のステージから出られなくなる仕組みを作ったのです。
照明の変化
照明の明るさや色を変化させることで、迷路の壁や通路を表現することができます。例えば、壁は暗く、通路は明るくすることで、迷路感を演出することができます。また、照明の色を変化させることで、迷路の道筋を示すこともできます。
複数のディスプレイ・鏡
複数のディスプレイを組み合わせることで、複雑な迷路を表現することができます。例えば、ディスプレイを縦横に並べて、大きな迷路を作成することができます。また、ディスプレイに異なる画像を表示することで、迷路の構造を変化させることもできます。
複数のオブジェ
複数のオブジェを組み合わせることで、立体的な迷路を表現することができます。例えば、柱や壁、床などのオブジェを配置することで、迷路の構造を複雑化させることができます。また、オブジェの形状や大きさを変化させることで、迷路の難易度を調整することもできます。
今回は、クラブイベントなので、照明の変化と複数のディスプレイで、幻想的な迷路のようでした。
ただし、客が、英子のステージに留まったのは、”英子の歌の力”なんだよ!という孔明の言葉が今回のクライマックスでした。
石兵八陣(せきへいはちじん)は、『三国志演義』に登場する架空の陣です。
関羽の弔い合戦である夷陵の戦いは、孔明の反対を押し切った劉備の感情にまかせた戦いでした。
敗戦を想定していた孔明が仕掛けた伝説上の陣形です。
劉備の率いる蜀軍が敗走することを見越して、追撃途中の魚腹浦にたくさんの石が陣のように配置されました。
陣内では定期的に突風や波が起こるようになっていました。
陸遜は、激しい風と砂嵐で、山のように積み重なった石によって道に迷い、追撃を諦めたのです。
泣いて馬謖を斬る
■ 泣いて馬謖を斬る
泣いて馬謖を斬る
孔明が、現在に表れて、住むところもなかったわけですが、偶然にも英子が勤めるライブハウス「BBラウンジ」のオーナーの小林が、三国志オタクで、孔明と三国志談義で盛り上がります。
上機嫌になった小林は、孔明をアルバイトとして採用しました。
この時の話題が、「泣いて馬謖を斬る」(内容は別記事を参考にしてください) でした。
ドラマでは、孔明いわく、「馬謖は勝つつもりだった」と言っていました。
が・・・
今回、偶然にも見逃し配信で1話から見ることが出来ました。
2話以降もリポートしていこうと思います。
一緒に学んでいきましょう。





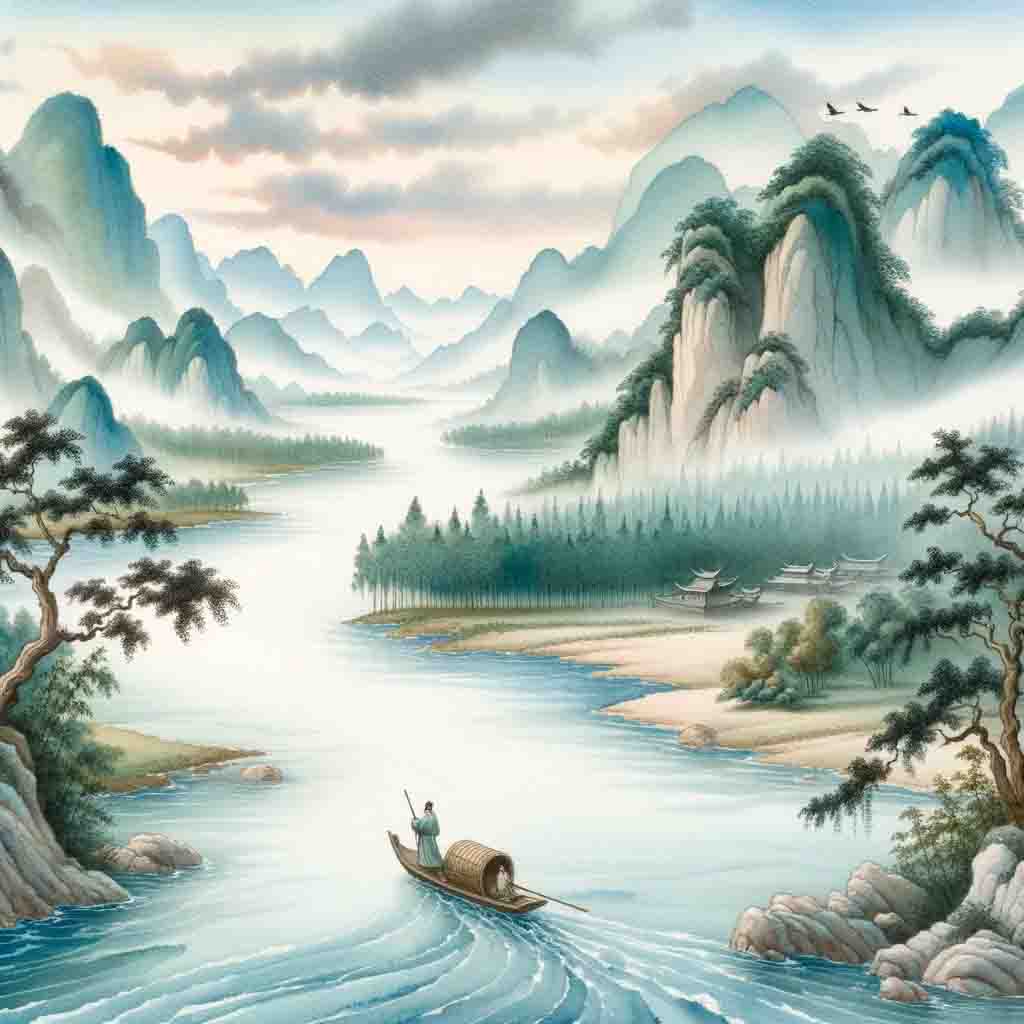
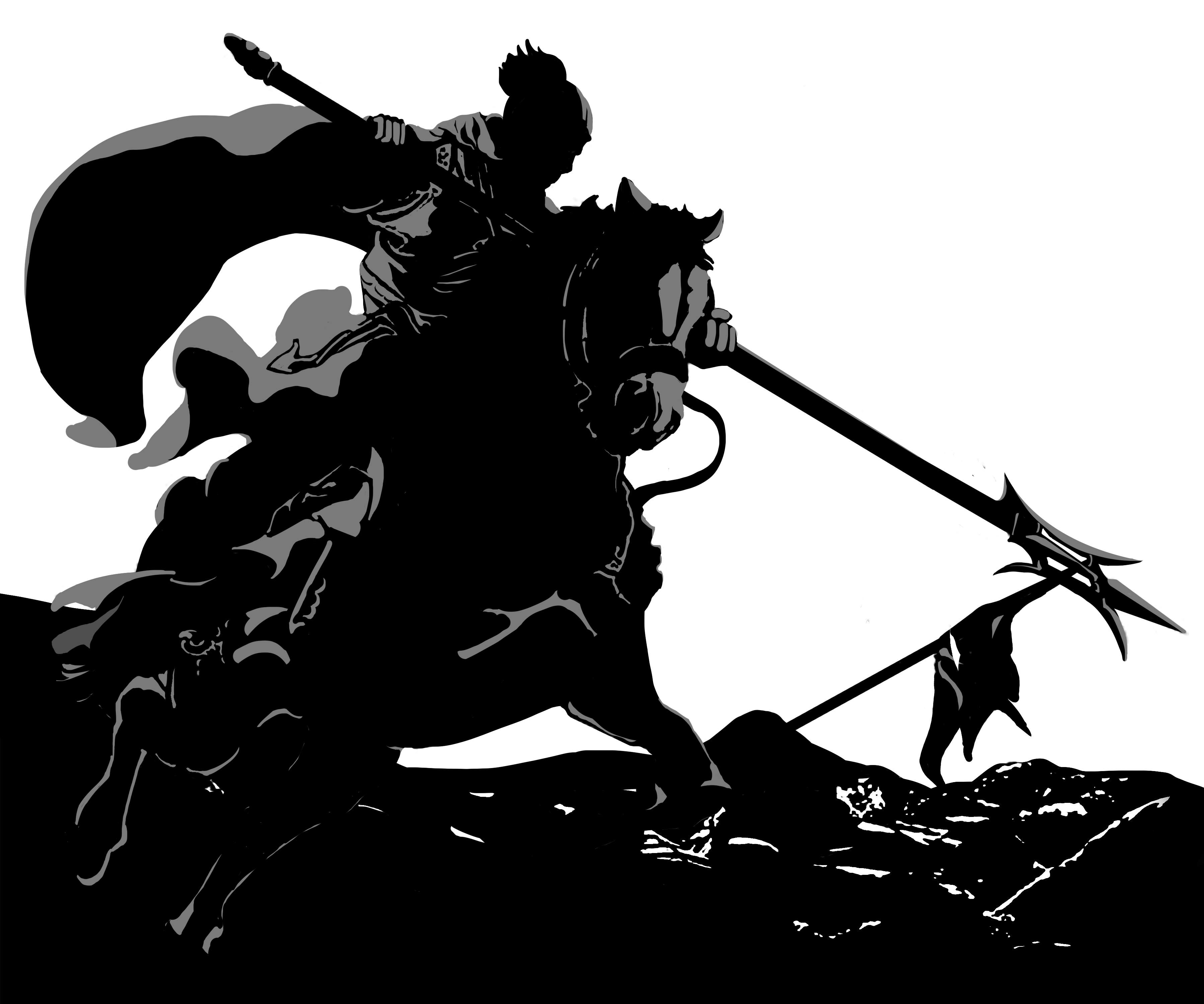




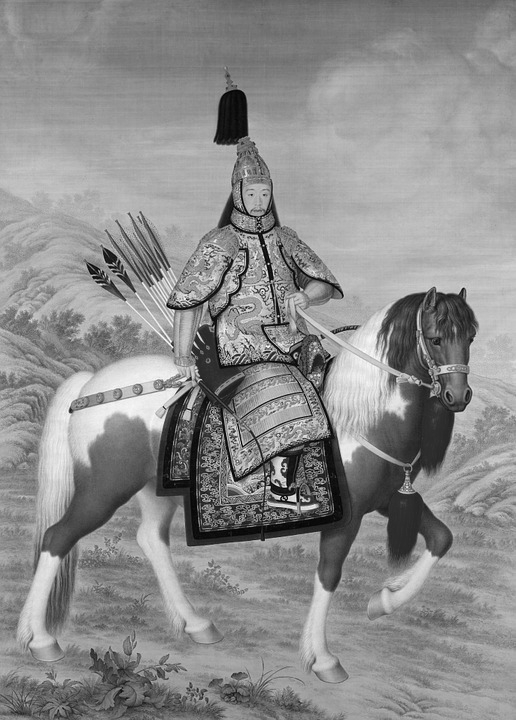



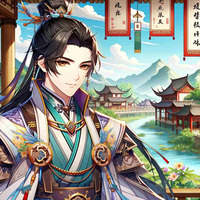











古代の雑学を発信