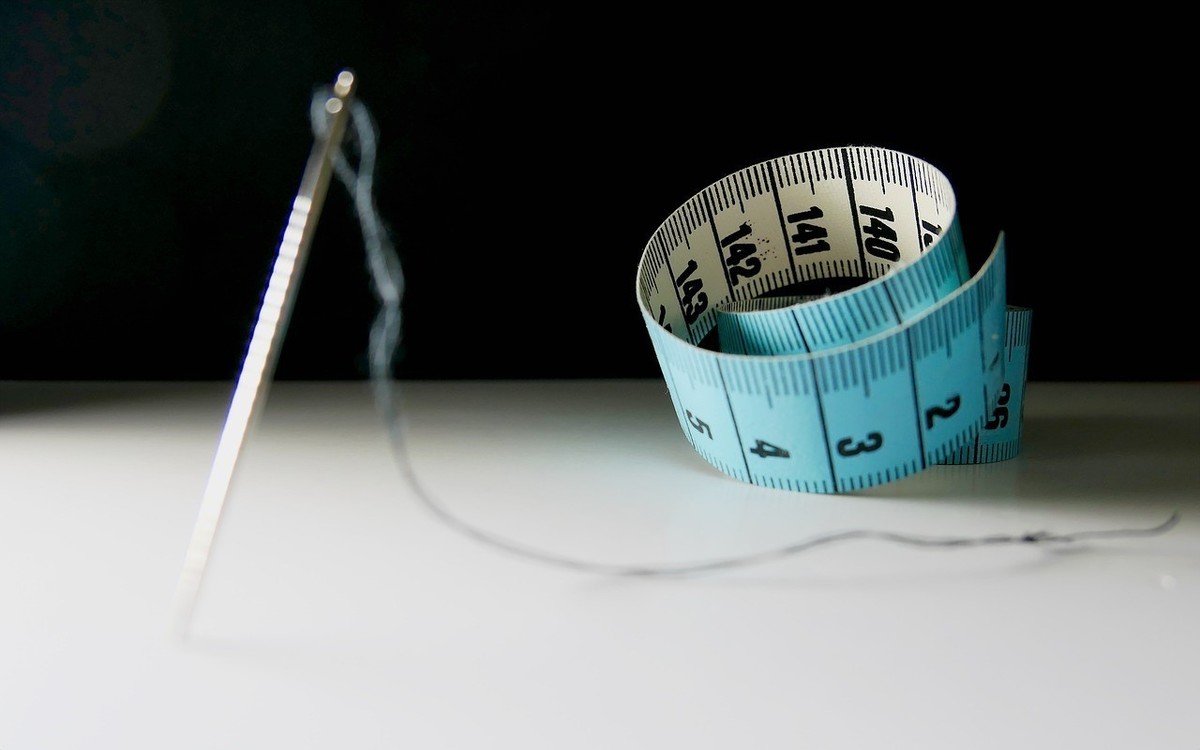足の毛を抜かれて足が遅くなった武将の噂
■ 足の毛を抜かれて足が遅くなった武将の噂
足の毛を抜かれて足が遅くなった武将の噂
wikiからの抜粋になりますが、周倉という人物はご存知でしょうか?実際存在したか否かわからない架空の人物とされています。その周倉は関羽雲長の赤兎馬と同じ速さをもって戦場を自らの足で走って従軍したとされています。
とある日に、関羽雲長と周倉を引き離すために呂蒙子明が友人を買収し、周倉の足の速さの秘密を調べることにします。その秘密を調べているとどうやら周倉の足の裏には3本の毛が生えているということがわかったのです。
これが秘密かどうかはわからないまでも友人はさっそく周倉を酔わせて足の毛を抜いてしまいます。するとたちまち周倉は走れなくなり、つには呂蒙子明は関羽雲長を捕らえてしまうのでした。架空の人物ですが、中々面白い話ですよね。架空とはいえ、実際に足の裏に毛が生えている足の速い人を見かけても抜いてあげないでくださいね。
民間に伝わる趙雲子龍の最期
■ 民間に伝わる趙雲子龍の最期
民間に伝わる趙雲子龍の最期
趙雲子龍には愛妻である孫夫人がおりました。これは民間に伝わっている噂にしかすぎませんが、ある時、愛妻の孫夫人は趙雲子龍に対して貴方の身体には傷がひとつもないということを指摘します。これに対して趙雲子龍は長年戦場にいて怪我のひとつもしたことがないことを誇らし気に語ります。
どのようなつもりかはわかりませんが、孫夫人は冗談のつもりだったのか裁縫針で趙雲子龍の身体を突き刺してしまいます。するとなぜか血が泉のように噴き出してついには趙雲子龍は絶命してしまいます。本当か嘘かはわかりませんが、本当ならばとても恐ろしい話ですね。
趙雲子龍ほどの武将もほんの一瞬スキを突かれればたちまちに命を落とすということがわかるエピソードです。とはいえ、裁縫針で刺されたくらいで血が泉のようだなんて作り話もいいとこだって思いますよね。信じるか信じないかはあなた次第です。
龐統の顔が醜いというのは真っ赤な嘘
■ 龐統の顔が醜いというのは真っ赤な嘘
龐統の顔が醜いというのは真っ赤な嘘
龐統といえば顔が醜いとされている武将ではありますが、この顔が醜いという話は正史などでは一切語られていません。記述には確かにさえない風貌とはあるものの、醜いとはいっていないのですよね。冴えないことを醜いというのはあまりにもイメージを広げすぎています。しかしこれにはどうやら思惑があるらしいんです。
というのもやはり、龐統といえば諸葛亮孔明と並びもてはやされた人物としても知られています。ただ創作上はどうしても諸葛亮孔明を唯一無二の存在にしたいが故に龐統をあえて醜いブサイクキャラにすることで差を生ませたのではないかと思われています。実際にどうかは定かではありませんが龐統からすれば迷惑な話と言えますよね。
歴史というのは、その後に書くものによって創作や脚色が加わり間違ったイメージで伝わることは珍しくはありません。単にさえないというだけで醜いと言われてしまうのも考え方なのでしょうが、それにしても龐統からすれば失礼極まりないですよね。
走ったほうが馬に乗るより早い周倉
■ 走ったほうが馬に乗るより早い周倉
走ったほうが馬に乗るより早い周倉
前述にも出てきている周倉ですが、関羽雲長が赤兎馬に乗っているすぐ横を自分の足で走っているという創作上の武将です。関羽雲長が一日赤兎馬で千里駆ける傍らで、周倉は一日に千里走ります。その姿をみてさすがの関羽雲長も不憫に思ったのか周倉に馬を与えようとしたそうです。
しかし、千里駆ける名馬はなかなか見つからず、やっとの思いで一日九百里駆ける馬を見つけることができたのでこれを関羽雲長は周倉にプレゼントするのですが、馬にまたがると周倉は今までの速さが嘘かのように関羽雲長から離されていったのでした。
馬よりも走ったほうが速いなんて周倉って本当に人間なのでしょうか?むしろ馬の乗り方が下手だという面もみえるとますますそのように見えてしまいますよね。 というかこれで引き離されたことが要因となって関羽雲長が命を落としたのだとしたら本当に笑いごとじゃないと個人的には思いました。
正史で予想されていた身長と見つかった死体の身長が同じという武将がいる
■ 正史で予想されていた身長と見つかった死体の身長が同じという武将がいる
正史で予想されていた身長と見つかった死体の身長が同じという武将がいる
正史で語られる身の丈なんてものは大体の場合は正確な尺度でないということが多いとみられていますが、朱然という武将に関しては正史で語られていた身長と見つかった死体の身長が同じだということがありました。これは非常に驚くべき事実と言えます。
正史では身長は169センチと語られていたのですが、実際に見つかった死体の身長を測ってみると同じく169センチということで寸分の狂いもありません。どのように測ったのかはわかりませんが、こんなに一致するもんなのかというのは誰もが思うことですよね。
当然ながら、かといって2メートルと言われている人が2メートルというわけではありません。また、創作の中では身長を大きめに設定されてしまうことなどもあります。日本の戦国時代の一部を描いた花の慶次では主人公の前田慶次は誰がどうみても大男ですが、実際の身長は160センチ程度だと言われています。
正史でここまで身長を正確に語られているところをみると朱然という人物が当時それだけ目立った人物だったのではないかと考えられますよね。とはいえ、朱然という名前を聞いたことがあるかと問われれば大概の人は知らないと答えるであろうというほどマイナーです。もっと朱然という人物を皆さんに感じてもらいたいと思いました。
本当か嘘かわからないマイナーエピソードは都市伝説!?
■ 本当か嘘かわからないマイナーエピソードは都市伝説!?
本当か嘘かわからないマイナーエピソードは都市伝説!?
本当だか嘘だかわからないほどのマイナーエピソードを紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?中国の昔話ってどうも誇張してるだとかという気がしてなりません。しかし、こういった噂が立つということはある程度似たようなエピソードはあったのではないかと思います。
三国志の世界では亡くなった関羽雲長が亡霊となって出てきたせいで呂蒙子明は病気に追い込まれたなどといった呪いのようなエピソードなどもたくさん転がっています。目には目を歯には歯をといった具合で何かされたら必ず復讐する。悪いことをすると自分にもかえってくるというのが根底にあるのかもしれません。
ネット上でこうしたマイナーエピソードを探すと今回は紹介できなかったものがたくさん転がっています。皆さんももしも気になったらネット上から拾ってみてはいかがでしょうか?もしかすると面白いエピソードが見つかるかもしれません。信じるか信じないかは貴方次第です!