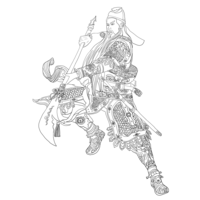若くして名声を得る劉焉
■ 若くして名声を得る劉焉
若くして名声を得る劉焉
劉焉(君郎)は益州出身ではなく、江夏で出生したといわれています。前漢の皇帝一族である劉余の末裔に当たります。劉焉は分家筋とはいえ、立派な家柄といえ、早くから国家に貢献する役目を担っていました。このことから劉焉は若い頃から出世を重ねていきますが、自身の学問の師匠でもある祝公の喪に服して、すべての官職を辞職しました。
劉焉はその後学問に励みながら、人々に学問を丁寧に指導していき、周囲の名声を自然と得ていきます。劉焉は才能ある賢人として推挙されており、都に仕えることになりました。劉焉は県令や刺史、太守などを歴任しており。当時は天下に覇を唱えようとする欲は無かったといえるでしょう。そのことからもますます人望を得ていくことになります。
中央の混乱を避けて益州に派遣されるよう画策
■ 中央の混乱を避けて益州に派遣されるよう画策
中央の混乱を避けて益州に派遣されるよう画策
劉焉が使えていた霊帝の時代には、政治の実権を握っていたのが宦官たちでした。賄賂による高官たちの腐敗する様や、有権者の暗殺など、政治は混乱を極めていきます。また、大規模な黄巾の乱による地方の反乱によって、各地の刺史や太守の支配力が弱体化しており、劉焉は州牧を設置して、国家の有益となるよう、清廉な人物を地方に派遣することを提案しています。
都が荒れていたことを受けて、劉焉は自身がこのまま都で出世するよりも、地方に居た方が安全と考えていました。劉焉は中国南部の交州に派遣されることを期待していましたが、侍中の董扶が近づき、劉焉に益州で天子の気があると告げたことから、劉焉は益州で任務に就くことを願うようになりました。
刺史を監督する立場で希望通りに益州へ赴任
■ 刺史を監督する立場で希望通りに益州へ赴任
刺史を監督する立場で希望通りに益州へ赴任
やがて各地の刺史が殺害される事態になり、益州刺史も失政が評判となるにつれて、劉焉は益州刺史を取り調べる形で赴任することになりました。自身の希望通りに事が運んだことを受けて、劉焉は天子の気運というのを自分のことを指しているに違いないと思うようになっていたことでしょう。気を良くした劉焉は董扶同行させています。
この董扶は益州出身でもあり、劉焉を利用して故郷である益州へ帰りたかったのか、それとも天子の気が後の劉備(玄徳)のことを指していたのかは分かりませんが、彼がいなかったら劉焉が益州に行って国土を安定させることもなかったといえるでしょう。
益州の反乱を機に実権を掌握
■ 益州の反乱を機に実権を掌握
益州の反乱を機に実権を掌握
184年には黄巾の乱の首謀者である張角が亡くなり、乱そのものは各地の群雄によって終息を迎えていきました。しかし、まだまだ小規模の反乱は残っており、この益州でも馬相によって反乱が起こっていました。当時の益州刺史は重税を強いて益州民から反発を喰らっており、馬相ら反乱軍によって殺害されていました。勢いに乗る馬相は益州の3郡を制圧して自ら天子を自称するなど、万規模の軍勢を持つまでに至りました。
しかし、益州従事の賈龍によって隙を突かれて殺害されており、反乱自体は鎮圧されました。この後、賈龍によって招き入れられた劉焉は寛容さを前面に推しだして住民や役人たちを懐柔していき、善政を敷きました。しかし、劉焉は次第に野望が芽生えてきて、都の権威が届きにくい益州で独立する構想を練っていきます。
漢中を支配
■ 漢中を支配
漢中を支配
各地では黄巾の乱や都での荒廃、また袁術などの圧政によって難を逃れてくる民衆が数万規模で益州に入ってきました。劉焉はそれを受け入れ、兵士として編成していき、【東州兵】と名付けて屈強の軍団を作りました。
また、劉焉は漢中を支配して都から益州を切り離しておこうと考えます。当時の漢中は五斗米道という道教が普及しており、劉焉は教祖である張魯(公祺)に照準を付けており、その母を取り入れます。張魯の母は美貌の持ち主でもあり、実はこの母が劉焉を利用して張魯を出世させようと画策していました。
どちらの思惑もあって張魯は劉焉から漢中に派遣され、橋を落として中央と分断することに成功します。張魯督義司馬に任命し、漢中に派遣して橋を切って道を遮断し、官吏を殺して中央と分断させた。劉焉は先に都へ張魯のせいで中央と連絡が取れなくなったと虚偽の報告をしており、明らかに独立のために張魯を利用していました。
権力を手中にして没落していく
■ 権力を手中にして没落していく
権力を手中にして没落していく
漢中を制圧した形になった劉焉ですが、このやり方に反発する益州の豪族たちも出てきます。しかし、独裁者となってきた劉焉は反乱を許さず、豪族ら10人以上を弾圧していきます。もともと劉焉を迎え入れた賈龍らは、黄巾の乱などで荒れた益州の地を復興させたいと願っており、劉焉の専横に対して反乱を起こしました。しかし、東州兵の活躍もあって反乱は鎮圧されて賈龍は殺害されました。
劉焉は益州の広大な領土を手に入れた過信からり驕るようになり、周囲にその威厳を示しました。劉焉の後継者となる子息は4人いたとされており、その内3人が都で使えていました。後漢の献帝は劉焉を諌めようと、四男の劉璋を派遣していますが、劉焉は聞く耳を貸さずにおり、むしろ劉璋を都に返すこともありませんでした。
窮地におちいる劉焉
■ 窮地におちいる劉焉
窮地におちいる劉焉
劉焉は西涼の将軍である馬騰と手を組み、長男の劉範とともに長安を襲撃しようとしました。董卓亡き後の勢力争いで中央は混乱していたこともあって、作戦は成功するかに見えましたが、事前に露見され馬騰は敗北し、劉範や次男の劉誕も処刑されました。かろうじて難を逃れた劉焉の孫は代々交流があった役人の龐羲によって救出されて益州入りを果たしています。
追い打ちをかけるように落雷によって劉焉の居城は焼け落ち、子どもを無くした心痛も重なって劉焉は病に倒れます。劉焉は後継者を決めることなく194年に死去します。後を継いだのは三男ではなく、暗愚と評価されていた四男の劉璋が後継者となりました。これは周囲の実力者たちが劉焉よりも扱いやすく、権力を握りやすいために行ったともいわれています。
まとめ
■ まとめ
まとめ
劉焉は独立を果たせないままに死去し、子どもらが相次いで亡くなり、後継者となった劉璋にも帝王学を学ばせることも出来ずにいて、晩年は不遇ともいえました。しかし、劉焉が平定した広大な益州の領地は、多くの有望な勇士を育てたり、受け入れたりして、法正や張昭、孟達、黄権や劉巴、李厳といった後の劉備の入蜀に貢献することになる優秀な人材を確保することにつながっていきます。