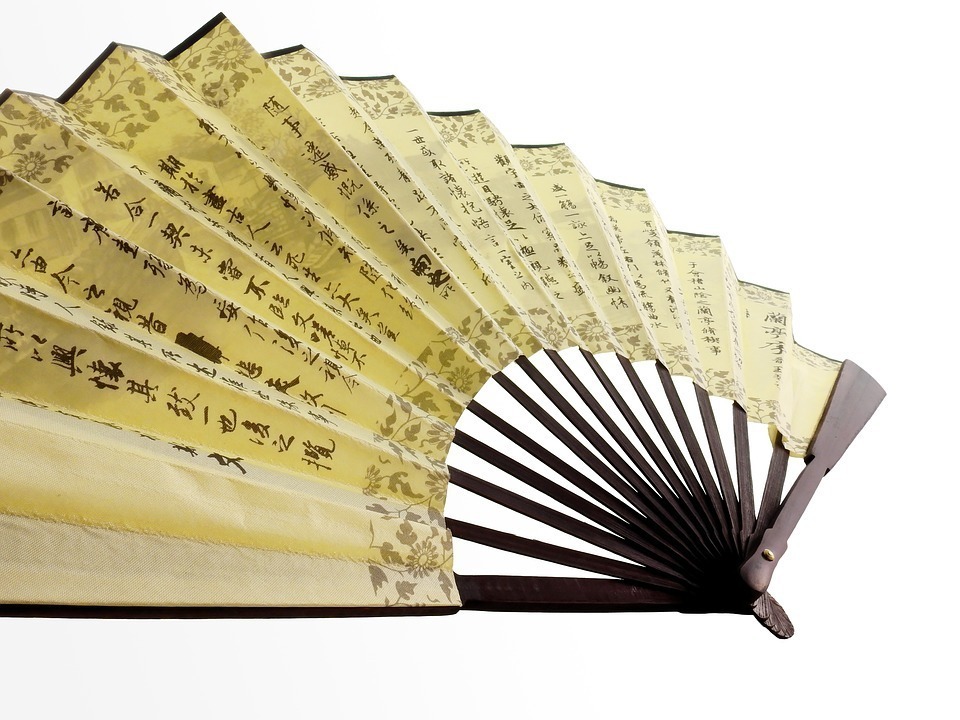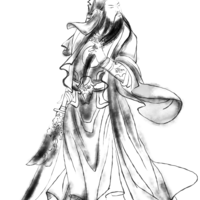劉繇(りゅうよう)のイメージ
■ 劉繇(りゅうよう)のイメージ
劉繇(りゅうよう)のイメージ
劉繇、字は正礼。青州東萊郡の生まれです。生年が156年ということは曹操や孫堅とほぼ同じ世代になります。「三国志演義」での扱われ方はひどく、実に凡庸な君主として描かれています。猛将である太史慈の武勇を活かしきれず、攻め込んでくる孫策に大敗し、落ち延びていきました。言葉はよくないですが、雑魚です。三国志のゲームが開発された初期の頃も同じような評価で、能力値がとても低く設定されています。やはり三国志演義の影響力は大きく(それを基にして書かれた三国志作品もおおいため)、劉繇のイメージは最悪といっても過言ではありません。無能であるが故に孫策に攻め込まれても仕方がないといった感じなのです。しかし「三国志正史」での劉繇は違います。実はこの劉繇、なかなかの英雄ぶりなのです。このギャップに驚く三国志ファンも多いのではないでしょうか。
劉繇の祖先
■ 劉繇の祖先
劉繇の祖先
別に祖先が偉いからといってその子孫まで高く評価する必要はありませんが、劉繇は漢皇族の血を受け継いでいます。そのあたりは三国志に登場する劉備(玄徳)や劉表、劉焉などと同じですね。劉繇の祖先として真っ先に名前があがるのは斉の孝王です。もちろん行き着く先は漢の初代皇帝である高祖なのですが、劉繇はその嫡流ではありません。高祖の長男である劉肥は庶子であったために皇太子にはなれず、斉の国王となりました。さらにその長男である劉襄が跡を継ぎますが、子ができずに断絶してしまいます。残された土地は劉襄の弟たちに分け与えられました。斉の孝王はその中の一人になります。劉将閭という人物です。
斉の孝王
■ 斉の孝王
斉の孝王
斉の孝王の名前が高まったのは、劉氏一門の中で内紛が発生したときになります。江戸幕府と外様大名の関係を思い出していただくとイメージが湧くのではないでしょうか。江戸幕府は地方の国力を割く政策を行っています。謀叛や反乱を起こさせないためです。漢の朝廷は同じようなことを実施しました。これに立腹したのが高祖の兄の子・呉王の劉濞です。劉濞は巧みに諸国の王と結束し、反乱を起こしました。やられる前にやるという覚悟です。斉の孝王の兄弟も呼応して挙兵していますが、斉の孝王は朝廷を裏切りませんでした。最後まで城を守り抜きます。朝廷からの援軍によって城の包囲も解かれましたが、斉の孝王は反乱に与していたと疑われ自害することになるのです。後に疑いが晴れて家は再興されました。このことで斉の孝王は忠義に篤い王として歴史にその名前を刻んだのです。
劉寵(りゅうちょう)と劉輿(りゅうよ)
■ 劉寵(りゅうちょう)と劉輿(りゅうよ)
劉寵(りゅうちょう)と劉輿(りゅうよ)
斉の孝王からさらに下ってくると劉寵という人物が登場してきます。三公のひとつである太尉にまで昇進した後漢末期の名臣です。法の適用と民を労わる治世を行い民衆に支持されています。母親の看病のために地方の行政担当を退くことになった際には、それを阻止しようという住民たちに道をふさがれたという記録が残されています。この劉寵の弟が劉輿であり、劉輿の子が劉繇となります。劉輿は兄ほど民衆に支持されたわけではないようですが、山陽郡の太守を務めていました。劉繇の一族は名前の知れ渡ったエリートだったわけです。
劉岱(りゅうたい)と劉繇(りゅうよう)
■ 劉岱(りゅうたい)と劉繇(りゅうよう)
劉岱(りゅうたい)と劉繇(りゅうよう)
劉輿の子には他に劉岱という人物もいます。三国志に登場する英雄のひとりですので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。反董卓連合にも諸侯のひとりとして参戦しました。激しい気性だったようですが、孝に篤く、正義感も強かったと伝えられています。この劉岱が劉繇の兄なのです。やはり弟の劉繇も武勇に優れていたようで、19歳ながら、賊徒に捕らえられた叔父を救うべく兵を率いて攻め込んで救出に成功しています。劉岱、劉繇の兄弟はそのような背景もあって民衆うけは良かったようです。その後、劉繇の才能も認められており、地方の行政に何度か携わっていますが、不正に対して厳粛で、抵抗のために職をなげうったり、弾劾したりしています。兄の劉岱に負けず劣らず劉繇も正義感が強かったようです。
劉岱の死と劉繇の南下
■ 劉岱の死と劉繇の南下
劉岱の死と劉繇の南下
兗州の刺史であった劉岱は、青州に端を発した黄巾の残党100万の侵入に対し、迎撃しようと出陣して戦死しました。劉繇もこの戦いに参加していたといわれています。敗戦した劉繇はそのまま徐州へ落ち延びました。このとき徐州の牧であった陶謙が朝廷に推薦し、劉繇は揚州の刺史に正式に任命されたのではないかと推測されています。しかし揚州には巨大な軍事力を持った袁術が居座っていました。そのため州府のある寿春を避けて長江を渡り、呉郡に拠点を置きます。地元の民衆は清廉な劉繇の登場に沸いたようです。多くの名士が中央の戦乱から逃れ、劉繇を頼って呉郡に来ています。太史慈はそのひとりです。他にも人物鑑定で名高い許劭や呉の初代丞相となる孫劭などがいます。
袁術との対立
■ 袁術との対立
袁術との対立
袁術は劉繇の勢力下にあった呉景や孫賁を切り崩します。劉繇の兄の劉岱はもともと袁紹と昵懇の間柄で盟友でした。この袁紹と袁術は同じ一族でありながら仲が悪く、家督争いを繰り広げていましたから、袁術は劉繇を袁紹派と見ていたのかもしれません。互角に近いせめぎ合いをしていた劉繇でしたが、袁術の配下である孫策によって敗北することになります。劉繇は会稽郡の王朗を頼ろうとしましたが、許劭の進言もあり、西の豫章郡へ落ち延びていきます。
まとめ・劉繇の死とその子孫
■ まとめ・劉繇の死とその子孫
まとめ・劉繇の死とその子孫
孫策に敗れ、落ち延びた先の豫章郡で病没した劉繇ですが、家が滅びることはありませんでした。孫策の跡を継いだ孫権が劉繇の子・劉基を重用したからです。最初は東曹掾、そして輔義校尉、建忠中郎将、大司農、光祿勲と出世していきます。船上の酒宴の際には孫権と同じ傘を差し掛けることを唯一許されていたほどの厚遇でした。これはかつて劉繇が呉郡で民衆の支持を受けていたことを、支配者となった孫権が巧みに利用しようとしたのかもしれません。劉基が孫権の酒宴の席での横暴を諫めた話も残っています。劉基の娘は、孫権の子でその寵愛を受けた孫覇に嫁いでいます。
ほぼ同じ世代である劉繇と孫堅の孫同士が結ばれることになるのです。残念ながら呉の皇帝には即位できませんでしたが、三国の一国である呉でその存在感を示したことは間違いありません。