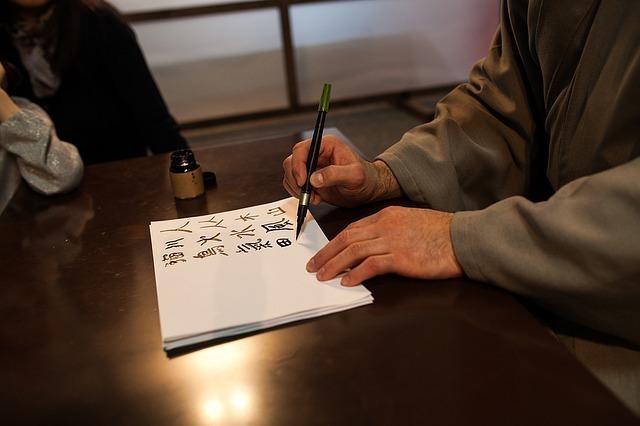三国志って?
■ 三国志って?
三国志って?
三国志とは、後漢末期から晋国が成立するまでごろ(西暦180~280年ごろ)を描いた中国の歴史書です。この時代は、魏・呉・蜀という三つの大国がそれぞれぶつかり合っていたため、三国時代と呼ばれて居るのですが、その三国時代を記述した歴史書なので「三国志」というわけです。
古代中国では王朝が変わると、それがどういった経緯で成立した王朝なのかを記録した歴史書が編纂され、正史として構成に残されることが一般的でした。
こうした書物は、正統な歴史書という意味の言葉=正史と呼ばれます。三国志もそうした伝統にのっとって、西晋の前身である魏国の歴史をメインに、その他の二国の歴史も同様に記されている正史です。
その成立は西晋によって中華が統一された後のことで、西暦280年以降のこととされています。著者は西晋に仕えた完了だった陳寿というひと。陳寿は元は蜀の出身でしたが、その後は西晋に仕えた人物です。
ちなみに「三国志」は非常に優れた歴史書との評価が高く、この「三国志」が書きあがってしまったのをみて、当時「魏書」を執筆している途中だった夏侯湛は、自身が書いた書を悔しさのあまり破り捨ててしまったという逸話も残っているほどです。
正史「三国志」
■ 正史「三国志」
正史「三国志」
初めて三国志に触れたひとにとって、三国志というものをより分かりにくくしているのが、「三国志」と「三国志演義」の違いでしょう。
そうなんです。三国志と一口にいっても、その言葉が指しているものは、実は二種類があるのです。
まず「三国志」の方ですが、これは前述した、陳寿が記した歴史書のことです。他と区別するために「正史三国志」と呼ばれることもあります。
その特徴は、そのほとんどが人物の伝記形式で綴られていること。魏書であれば曹操や曹丕といった主要人物から、日本ではあまり一般には知られていないマイナー武将まで、様々な人物の人生をひたすらに記録したことが大きな特徴です。
そのため、気に入った人物がいるという方はその人物の章だけを読めばよく、非常にありがたい構成となっています。
もっとも、一方でそういった構成のおかげで歴史的な前後関係が分かりづらいということが、とっつきづらいという印象を与えてしまう原因でもあるのですが……
また、もうひとつの特徴は魏・呉・蜀の三国をそれぞれ扱っているということもあげられます。正史は権力側の要請によって綴られるものですから、一般的にはほとんどは勝者の歴史部分をメインにしか記録されません。
しかし三国志では、魏書・呉書・蜀書といった三部立てで、それぞれの歴史を(ある程度は)公平に記しているといわれています。
ここで注意が必要なのは、「正史=正しい歴史」というわけではないということ。正史はあくまで「正統な歴史」という意味なのであって、三国志以外のその他の正史では、とても歴史とは呼べないような荒唐無稽な話が結構な割合ででてくることもあります。
これに対し、陳寿は出来る限り正しい歴史を記すために、事実関係に非常にこだわって三国志を編纂したといわれています。信憑性の薄い史料を徹底的に排除し、確からしいことしか載せなかったため、三国志は非常に簡潔な内容となっているのです。
そのため現在残っている正史三国志では、後の世に裴松之という人物が膨大な量の注釈をつけて、歴史を補強してくれています。現在に残っている三国志の逸話には、実は元々の陳寿の書には記述が無く、裴松之によって付け足されたものも数多くあるのです。
「三国志演義」
■ 「三国志演義」
「三国志演義」
さて、それでは一方の「三国志演義」は何かというと、正史三国志をもとにして作られた時代小説のことです。
非常にざっくりとした言い方をしてしまえば、三国志演義は正史三国志の二次創作小説だといってしまっても良いかもしれませんね。
その成立ははっきりしていませんが、およそ明代になってからのことだといわれていますので、実際の三国時代から約1000年後のことになります。
その作者も定かではなく、一般的には、施耐庵あるいは羅貫中によるものとされていますが、ハッキリしたことは分かっていません。
三国志演義は、元々は民衆の間で説話や談話として語り継がれていた三国時代の歴史物語を書物としてまとめたもので、そのスタンスは非常に分かりやすくなっています。
正史三国志が歴史書(記録)として書かれていたのに対して、三国志演義は楽しんで読まれるための読み物だったため、後漢の血を引くといわれる劉備(玄徳)を正義の主人公に、一方魏国の曹操を悪者側として書かれていることが大きな特徴です。
これは、漢王朝の血を引き仁義に篤い劉備(玄徳)の人柄が民衆の好みに合致していたためであり、受け入れられやすいように、また物語として楽しんで読めるようにという作者の意図があったからだといわれています。
こうした成立過程や著者の意図もあり、三国志演義は正史と比べて非常にドラマチックな書かれ方をしています。
超絶武勇の武将が一騎当千の活躍をしたり、智謀を駆使して計略を張り巡らせる、というシーンは、実は三国志演義によって作られたフィクションのものも多いのです。
といっても大筋は正史三国志をベースに作られているので、全くの出鱈目ということはもちろんありません。正史による歴史の流れをおおむね網羅し、それらを大衆向けに俗説や創作によってアレンジしたという程度のことなので、歴史を知るという意味では三国志演義でも十分だといえます。そういった意味でも三国志演義は、やはり三国志の二次創作作品といったところなのかもしれません。
ちなみに三国志演義は、水滸伝や西遊記と並んで中国四大奇書にも数えられる名著と言われています。「奇書」とは、非常に稀なほどにクオリティが高い書物という意味であり、奇妙な書物という意味ではないのでご注意を。
まとめ
■ まとめ
まとめ
正史三国志と三国志演義の違いについて解説してきました。混同されやすいこの二つの違いを把握することが、三国志を深く知る第一歩目です。これから三国志作品にふれた際には、それが正史の話なのか演義の話なのかを意識してみるといいかもしれませんね。
そんな正史と演義ですが、初心者の方が始めて触れるとしたら、圧倒的に三国志演義がおススメです。物語としての完成度が非常に高く読みやすいので、きっと三国志にハマれるはずですよ。
日本では漫画や小説でも演義をモチーフにしたものが多いので、是非探してみてくださいね。