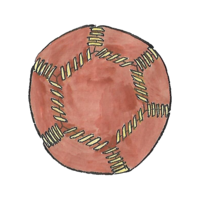民衆の間では同性愛が流行っていたという真実
■ 民衆の間では同性愛が流行っていたという真実
民衆の間では同性愛が流行っていたという真実
日本では同性愛の文化は公家から発祥し、それを真似する形で武士や民衆といった形で流れていったわけですが、前漢の時代はまだしも、三国時代では同性愛という文化を武将の間ではまったくもって聞きませんし、そういった文献もありません。ある程度身分の高いものは女性に不自由することがなかったからなのか、歴史上そういった事実があったことを隠したいのかはわかりませんが聞きませんよね。
ただ、実は民衆の間では漢の時代から流行っており、お気に入りの恋人を持つというのは一種のステータスとなっていました。ちなみに、既婚者であっても同性の恋人を持つのは容認されており、妻などは同性の恋人を旦那が持つことに対して文句をいうことができなかったと言われています。もし、これが現代であれば気持ち悪いとか生理的に受け付けないなどと言われたりして離婚でしょうね。三国時代の女性は寛大です。
SEXは健康を保つために夫婦間では義務付けられていた。
■ SEXは健康を保つために夫婦間では義務付けられていた。
SEXは健康を保つために夫婦間では義務付けられていた。
礼記によれば、セックスは健康を正常に保つために良いとされており、結婚した後、夫は妻が50歳になるまでは最低でも5日に一度のペースでセックスしなさいとあります。この頃からセックスは女性の健康を保つ上で重要な役割があると信じられていたんですね。驚きです。
また、前後漢代の頃には花嫁道具の中にセックスの教本のようなものが入っていたと言われています。この教本というのは文章だけでなく挿絵付きであったとされています。性交時の細かい体位や突き方や回数など夫婦の性生活にとって必要であろうことをレクチャーするものでした。いやらしいものというのではなく保健の教科書のようなものであったと思われますね。
伸ばし放題だった髭や髪の毛
■ 伸ばし放題だった髭や髪の毛
伸ばし放題だった髭や髪の毛
中国でもっとも影響力のある宗教といえば儒教ですが、その影響は少なからず民衆にもありました。もちろん武将にも同じように影響していました。儒教社会では身体の一部を損なうことは良くないとされていました。これは髪の毛や髭といったものも同じでした。
特に、頭というのは古代の中国では力の源と信じられていたために、人前に頭の肌を晒すような行為は恥だとされていました。禿げているだとかスキンヘッドだとかはこの時代は恥だったということですね。なので当然、男の人も長く髭を伸ばして長髪だというのが当たり前だったようです。
ですので、散髪などといった行為そのものは重罪になる可能性も高く、民衆の間では特に散髪は行われなかったものとみられています。伸びすぎればかなり鬱陶しいと思うんですが、そんな理由だけで軽はずみに散髪をするととんでもない罰が待っていたようなので正直怖いです。たかが散髪、されど散髪、宗教の教えは絶対ですからね。逆に散髪や髭をそるのが嫌いな現代の人は儒教の信者だといっておけば良いのかもしれません。冗談ですが。
三国時代の成人年齢
■ 三国時代の成人年齢
三国時代の成人年齢
日本では成人の年齢を男女とも18歳に設定するといった議論が行われていましたが、三国時代の中国はどうだったかご存知でしょうか?実は、成人の年齢にはこの当時、男女に大きな開きがありました。それでは成人の年齢を見ていきましょう。
三国時代の男子の成人年齢は20歳でした。これは現代の日本と同じですね。10代を終えて20歳という節目で成人を迎えるといった形です。大学生で言えばちょうど大学二年生あたりの年齢になります。ただ、当時の日本を考えれば遅めではないでしょうか?例えば日本の戦国時代の元服なんかかなり若かったですよね。
一方、女性の成人年齢は15歳でした。男性と比べれば5歳も女性の方が成人を早く迎えます。理由は定かではありませんが、女性の妊娠適齢期は17歳程度と言われているので身体的に成熟しきるのが女性の方が早いという判断なのだと思われます。この当時に成人式があったかはわかりませんが、あったとしたら大学二年生男子と中学3年生女子の成人式ですからね。想像してみると物凄い開きがありますね。
三国時代のお金
■ 三国時代のお金
三国時代のお金
三国志の時代のお金って見たことありますか?おそらく見たことがないという人が大半でしょう。最初は金属でできた硬貨も流通していたようですが、戦時中ともなると金属が不足してきたために硬貨を作れなくなることもありました。この時代では董卓が質の悪い硬貨をつくってその価値が地に落ちたのも有名ですね。硬貨の代わりに実はあるものが使われていたんです。
硬貨の代わりに使われていたものとは、布地や塩といった日常生活で使うもので、尚且つ持ち運びのできるものでした。確かに硬貨は所詮は硬貨でしかありませんが、塩や布地なら間違いなく価値はありますし、お金の代わりに使うのなら適していると言えますしね。金属が不足していたこともあり、この時代には民衆の間ではあまりお金という概念がなかったこともあったのかもしれません。
まとめ
■ まとめ
まとめ
今回は三国志の武将というわけではなく、三国時代の民衆の生活にスポットライトをあてて紹介してきましたがいかがだったでしょうか?本来ならば三国志といえば呂布奉先や関羽雲長のような豪傑たちが華々しい活躍をみせるというようなロマンあふれるものといった印象ですが、その裏にはこうした民衆の生活があることを忘れてはなりません。
こうした民衆がいたからこそ、その時代は成り立っていますし、こうした民衆を含めて三国志の世界と言えます。三国時代の武将たちはこうした民衆の目にはどのようにうつっていたかといったような民衆視点の三国志も気になりますよね。兎にも角にも民衆を知るということは三国志を本当の意味で知ることになるということは何となくわかりました。
今回調べていて、もっともびっくりしたのは同性愛が民衆の間で容認されていたということです。近年では理解が進んできましたが、バイセクシュアルやホモセクシュアルといったものに関しては現代では偏見や差別がまだたえないですよね。その中で民衆の間で容認されるどころか、進んで同性愛者をつくることが良いことだとされていたことが驚きでした。
まぁとはいえ、男性同士、女性同士で性的な意味で愛し合うというよりも、おそらく行き過ぎた親友、お気に入りの友人をつくりましょうといったことだとは思うので、そう考えれば同性で心の通じ合った愛すべき人をつくりましょうという考えは個人的には悪くはないんだろうなと思いました。誰が誰を愛するだとかは自由なはずなので三国時代の人々はそのあたりは心が広かったんだなと感じました。まだ、他にも民衆に関しては色々あると思うので、調べてお伝えすることがあれば良いと思います。