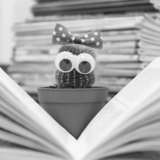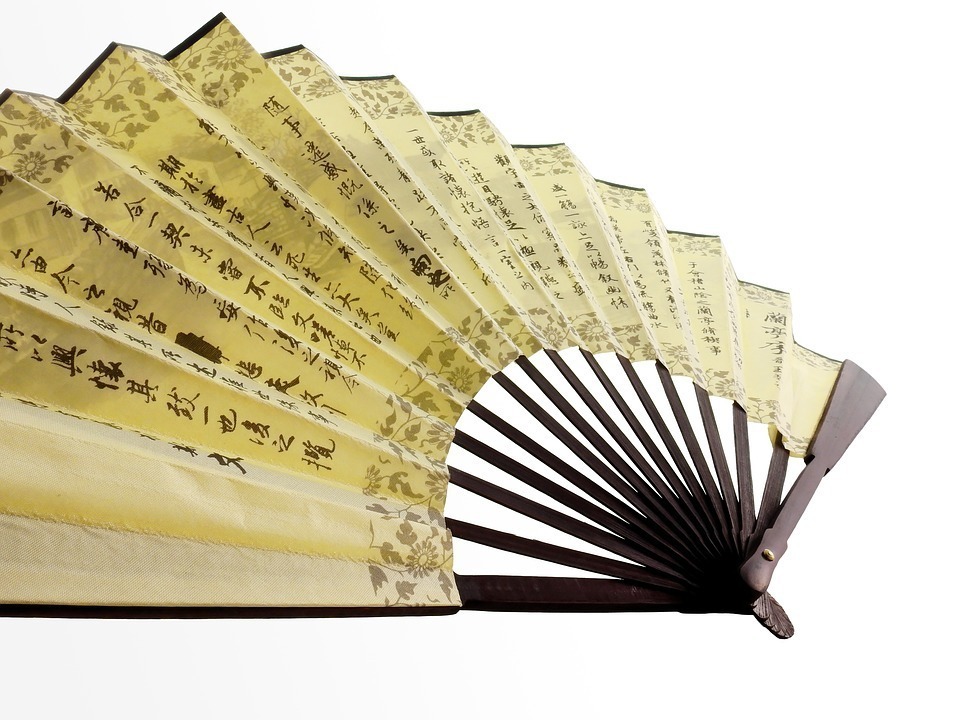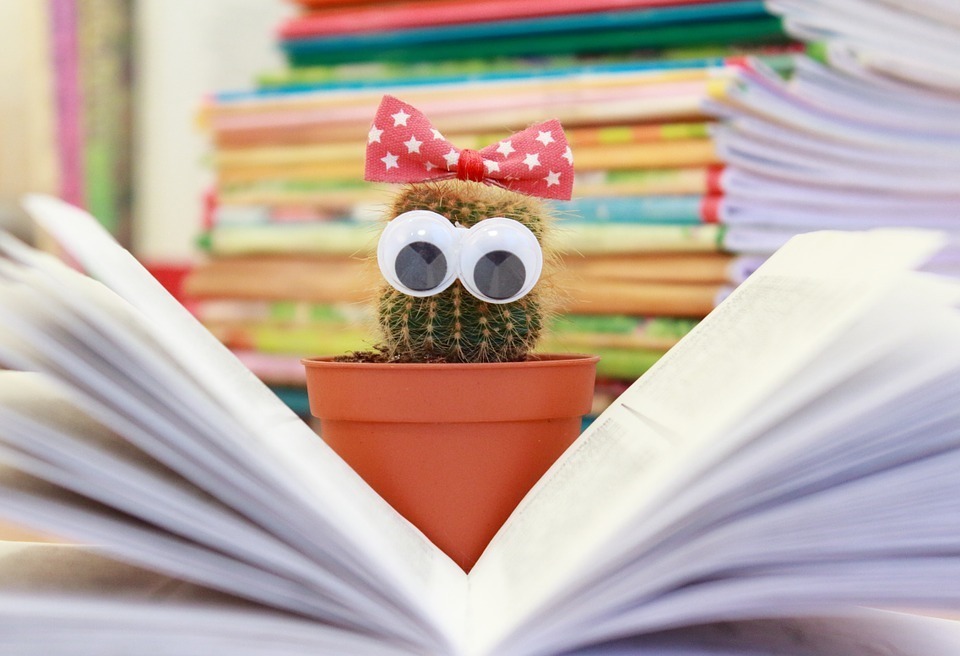何気にしれっとやばい奴
■ 何気にしれっとやばい奴
何気にしれっとやばい奴
キングダムでも三国志でもやばい奴はいろいろ存在しますが、今回は「あまりやばそうに見えないのに実はしれっとやばいことをしでかしている奴」を紹介したいと思います。キングダム代表は呉鳳明(ごほうめい)しれっと軍略の師匠をあたかも自分であるかのように振る舞い相手に斬らせ自分は生き残るというやばい奴です。一方三国志では董卓の腹心李儒(りじゅ)がそのポジションを与えられると言ってもいいのではないでしょうか。誰もが「董卓は悪人だ!」と思う中実はその董卓をある程度コントロールで来ていた李儒は地味ながらもやばい奴でした。李儒が董卓の策や案に対して「それはやめろ」と言ったら董卓は辞めることが多かったのにしれっと黙認しているのが李儒です。
nなぜ董卓はあそこまで李儒の言うことを聞いていたかというのは定かではありませんが、李儒が董卓の何らかの弱みを握っていてあそこまでコントロールすることができたと考えるのが一番面白いです。
これはかなりいい勝負をしていますが若干呉鳳明の方がやばいかなという感じです。
何もできなかった総大将
■ 何もできなかった総大将
何もできなかった総大将
春申君(しゅんしんくん)はキングダムで信に向けて合従軍(秦以外の全ての国が手を結んで総攻撃を仕掛ける連合軍)を造った際に総大将として祭り上げられた楚の宰相です。キングダム最強の軍師の一人超の李牧(りぼく)も一目置く存在で、春申君と李牧が合従軍を造ったと言っても過言ではありません。一方三国志にも反董卓連合というものがありました。言ってみれば三国志版合従軍と言ったところでしょう。全員が董卓を倒そうと結集しました。しかし総大将である袁紹(えんしょう)は何の手も打てず反董卓連合は解散する羽目になりました。この二人の場合まだ春申君の方が仕事をしていたと思います。そのためこの勝負はキングダムの勝ちです。
もはや伝説となっている大将軍
■ もはや伝説となっている大将軍
もはや伝説となっている大将軍
キングダムで廉頗(れんぱ)は超でめちゃくちゃ強い大将軍でした。しかしなんと自軍に標的にされてしまうという目に遭ってしまいます。それでも包囲網をかいくぐってその戦に勝利し、魏に亡命します。その後も信達の前に現れるという伝説的な大将軍としてキングダムで重要な役割を担っています。一方三国志では張遼が伝説的な人物です。孫権率いる呉の超天敵人物で、最後まで張遼を倒すことができませんでした。呉では「遼来来(りょうらいらい)」などと言う言葉がはやってしまったと言われているくらいです(日本で言う鬼が来たぞ!的な言葉です)
この勝負張遼の方がインパクトがある感じがするので三国志の勝ちとしましょう!
地味だけど功績は凄すぎる
■ 地味だけど功績は凄すぎる
地味だけど功績は凄すぎる
キングダムでは呂不韋(りょふい)四柱の一角を担っていた蔡沢(さいたく)。彼は七つの王国の一つである斉(せい)と話をつけ、戦をしないのに軍を撤退させるという超スゴ技を見せた人物です。秦王・政(せい)も蔡沢がいなかったら国が滅んでいたかもしれないと言っていたほどです。一方三国志では呉の魯粛(ろしゅく)がそのポジションに当たるのではないかと思っています。周瑜の後継者として知られ、赤壁の戦い時には孫権と劉備の同盟を結ばせることに成功しました。彼がいなかったら赤壁の戦いは敗れていて呉はそこでついえていたかもしれません。
この勝負甲乙つけがたしと言った感じでドローとしたいと思います!
〇〇の弟部門
■ 〇〇の弟部門
〇〇の弟部門
政の弟成蟜は王位を略奪しようとたくらんだ、どうしようもない弟です。最終的に政に抑え込まれ幽閉されますが、後に成蟜の力が必要だと感じた政は彼を牢屋から出し、お互いに力を合わせることにしました。一方三国志では袁紹の弟袁術がどうしようもないダメ弟でした。名門の家柄である故ボンボンに育ってしまった袁術はわがまま言い放題で周りの者は誰もついてきませんでした。反董卓連合軍結成時には補給係というポジションを与えられましたが、足を引っ張るばかりでした。結局最後までどうしようもない袁術に対し、改正した成蟜の方がまぶしく映る為この勝負キングダムの勝ちとしたいです!
力はあるのに不運な奴
■ 力はあるのに不運な奴
力はあるのに不運な奴
キングダムで力はあるのに不運な奴と言えば蒙驁(もうごう)ではないでしょうか。白老とも呼ばれており人のよさそうな爺さんは負け戦が多い凡人と言われていました。しかし、求心力があり人はいいのにどこかもう一つ足りないと言った感じでいまいち武功を上げることができない将軍でした。一方三国志では諸葛瑾(しょかつきん)がそのポジションに当たるのではないでしょうか。人が良く孫権から大いに買われていたものの打ち出す政策がことごとく破たんに終わってしまうという不運ぶりです。蒙驁は中華最強を自負している蒙武(もうぶ)を息子に持ち、諸葛瑾は三国志一の天才孔明を弟に持つなど境遇は似ています。しかしどちらが上かという勝負になると諸葛瑾が上だったのではないかと思います。
最強のNO.2対決
■ 最強のNO.2対決
最強のNO.2対決
キングダムで軍師NO.2と言えば昌平君ではないでしょうか。趙(ちょう)の李牧(りぼく)がキングダム最強の相手(前半に限るかもしれませんが)でNO.1だとしたら三国志のNO.1はなんといっても孔明でしょう。そしてじゃあNO.2は?と聞かれたらやはり司馬懿(しばい)ではないでしょうか。キングダムにせよ、三国志にせよ、何を持ってNO.1か?という判断が難しいところですが、共に軍最高司令官のポジションを与えられています。この勝負はかなり拮抗していると思いますが、孫が天下統一を果たし、三国志の覇者となった司馬炎(しばえん)ということを考えるとこの勝負は三国志の勝ちというのがふさわしいのではないかと思います!
まとめ
■ まとめ
まとめ
勝手にキングダムVS三国志七番勝負をしてみました。
今回は
何気にしれっとやばい奴 呉鳳明VS李儒 ドロー
何もできなかった総大将 春申君VS袁紹 春申君(キングダム)
もはや伝説となっている 大将軍 廉頗VS張遼 張遼(三国志)
地味だけど功績は凄すぎる 蔡沢VS魯粛 ドロー
〇〇の弟部門 成蟜VS袁術 成蟜(キングダム)
力はあるのに不運な奴 蒙驁VS諸葛瑾 諸葛瑾(三国志)
最強のNO.2対決 昌平君VS司馬懿 司馬懿(三国志)
です。
何度も言いますがあくまでも私の独断と偏見です。
今回の勝負は3勝2敗2引き分けで三国志の勝ちとしていただきます。
それにしてもお互い登場人物が多く、似ている功績の人物が多いのでとてもいい架空勝負ができてしまいます。
こういった所を見るとある程度「歴史は繰り返されるものだな」というのが分かります。